
飯田市大瀬木にて 撮影日 170918
◎ 飯田市の特産のリンゴをデザインしている。下の大きなリンゴの中に市章を入れている。ひらがなの「い」をふたつ組合せて「田」で「いい田」、飯田。
T-25は耐荷重25t。ひらがなで「おすい」と表記している。

飯田市大瀬木にて 撮影日 170918
◎ 飯田市の特産のリンゴをデザインしている。下の大きなリンゴの中に市章を入れている。ひらがなの「い」をふたつ組合せて「田」で「いい田」、飯田。
T-25は耐荷重25t。ひらがなで「おすい」と表記している。

871 飯田市大瀬木の火の見櫓 撮影日 170918
■ 3脚44(面取り)型の火の見櫓 下伊那郡阿智村から飯島町に向かう途中、飯田市内で出会った。櫓の上部はかなり細い。櫓のプロポーションに違和感あり。やはり上方から末広がりのカーブが好ましい。
見張り台の高さは約12m(梯子桟の数とその間隔により求めた値)、踊り場無しの外付け梯子でこの高さを昇り降りするのは怖いだろう。

3本の柱と平面が4角形の屋根の取り合い。不安定な感じは否めない。
脚部のみブレースは等辺山形鋼。 
脚部に吊り下げた半鐘


下伊那郡阿智村伍和にて 撮影日 170918
◎ アヤメを図案化したデザインという説明がネット上にある。アヤメの花弁数などが正確に表現されてるのかどうか・・・。

970 下伊那郡阿智村伍和の火の見柱 撮影日 170918
■ 阿智村には今年(17年)の7月22日に出かけた。その時は火の見櫓を見つけることができなかった。帰宅後ネットで調べると辛うじて火の見柱(半鐘を吊り下げた消火ホース乾燥塔)があり、その場所にはマンホール蓋もあることが分かった。で、今日(0918)改めて出かけてきた。
消火ホース乾燥塔の鋼管柱にアングルピースの腕木を溶接し、丸鋼のつっかえ棒を付けている。切妻の小屋根の下に他の部分と同じ緑色の塗装をした半鐘を吊り下げている。

撮影日時 170918 05:22AM 爪の先のような月と明けの明星
大型の台風18号が弓形の列島をトレースするように移動していく
毎年繰り返される豪雨災害
甚大な被害を受け、なおもここで生きる
この国に生まれた者の宿命・・・

■ しばらく前までは金曜日に出かけていたが、仕事の関係で土曜日に出かけることにした週末のサードプレイス、松本市梓川のカフェ バロ。
今日(16日)も仕事帰りに立ち寄った。カウンターのいつもの席に着き、美味なミックスベリーのケーキとコーヒーを味わう。こうして仕事モードを解き、リラックスモードへ。
同じカウンターの常連さんは内科医のM先生と、学校の先生をしておられたFさん。
話題が平出遺跡に及び、私が縄文時代の竪穴式住居は茅葺きではなかったことを話す。そう、登呂遺跡はじめ、復元されている竪穴式住居は茅葺きだが、実はそうではなかった。私はこのことを講談社の「日本の歴史」で知った。以前このことについて書いたが、ここに再掲する。

講談社の『日本の歴史01 縄文の生活誌』/岡村道雄にこのことに関する記述がある。以下少し長くなるが引用する。
**「カヤ葺きの家」も、問題をはらんでいた。文化人類学者が北方民族の例を引いて、〝縄文時代の住居は土葺き〟であったと示唆したにもかかわらず、登呂遺跡(静岡県の弥生時代集落跡)の竪穴住居の復元以来、カヤ葺きの家が一般的な集落景観として固定していったようだ。焼失した竪穴住居が全国で多く発掘され、焼け落ちた柱材の上に焼けた土が載っているのを見ても、なかなか偏見は変わらなかった。カヤ葺きだけでなく、土葺き屋根も相当普及していたのである**(230、231頁)
茅葺きの存在も認める記述だが、これは定説に対する配慮というか遠慮かもしれない。縄文時代の住居は樹皮・草木で葺いた屋根の上に土を被せた土葺き屋根だったと理解していた方がよさそうだ。
縄文住居を復元する際、今現在の道具を使わないことにすれば、茅を刈り取ることも非常に困難で、葺いた後、屋根の表面を整えることもできないことが分かるはずだが、このような実験考古学的な手法で行わないことに問題があるのかもしれない。
中学校の、いや、小学校か、授業で、ずっと後の時代に稲作が始まって、稲穂だけを石器でほとんどちぎるようにして収穫していたことも教わった。だから縄文時代には茅を刈るような道具はなかったと判断するのが妥当だろう。だが、当時は縄文住居の屋根の葺き方に関する説明が不合理であることに気がつかなかった・・・。

荒川区南千住で見かけたコンクリート蓋 撮影日170910
3脚6〇型の火の見櫓のグラフィックな表示と見るのには無理があるか、3脚〇6型と区別がつかないかな・・・。
あることに関心を持つとすべてのことをそこに関連付けて考えようとする。一見何の関係もないことが繋がることがある。

(再)塩尻市片丘南内田の火の見櫓 撮影日170914
■ 4脚64(面取り)型の火の見櫓で、総高は約17m。とんがり屋根のてっぺんにダンゴ、そして避雷針と風向計。櫓内に納めた簡易な踊り場が2ヶ所、脚は短い。1段目のブレースは山形鋼。見張り台には半鐘が無く、上の踊り場に設置してある。
平面が4角形の櫓に6角形の屋根という数少ない組合せ。見張り台は何角形か。単純に辺の数で判断する、と割り切れば8角形ということになる。私は正4角形の隅を面取りしたものと捉えて、この見張り台は4角形とするのが妥当だと考えている。だが、隅切りも大きくなれば判断に迷うことになる。木造の住宅の和室の柱も面取りをしてあるが、4角形の柱であって、8角形の柱だとは見ない。ただし算数の問題なら4角形では不正解。要は捉え方の問題。
簡易な踊り場、半鐘が下げてある。見張り台の半鐘を移設したか。
脚部 CB造の小屋を納めている。傾斜地のため4本の脚の長さの長さが異なる。脚の長さが違うのは珍しいかもしれない。

撮影日時170915 05:27AM
「二度と来ない今日という一日を大切に」
ラジオ深夜便のアンカーの言葉
朝起きるとリビングの窓から東の空を見る
今朝の空には秋の雲が浮かび、ベージュ色に染まっていた
「今日も何か好いことがありますように」
西山卯三展

■ 西山卯三については「寝食分離」を提言した建築学者、ということくらいしか知らなかった。銀ブラして、京橋のLIXILギャラリーで開催中の「西山卯三のすまい採集帖」を見た。
西山卯三が昭和のすまいを地道に調査し、漫画家を志望するほどの画力で記録し続けていたことをこの展覧会で知った。





入院した時も病室の様子を詳細にスケッチしていた。
西山卯三は尊敬すべき記録魔だったのだ。記録することに意義があることを再認識した。
狛犬5 拝殿前の獅子山の狛犬



向かって右側、阿形の狛犬 力強い後ろ足と大胆な造形の尾 この狛犬を彫った石工は相当な力量の持ち主だったに違いない。

向かって左側の吽形の狛犬には子どもがいる。
子どもを見る顔の表情は優しい。
尾の表面が欠けているのは残念
狛犬6 神殿狛犬

3基の庚申塔

延宝6年(1678年) 如意輪観音と三猿

寛文13年(1673年)聖観音 説明看板には庚申信仰と阿弥陀信仰の習合が見られるとある。

文化8年(1811年)青面金剛塔
素盞雄神社
■ 9月9日(土)、大学のOB会に参加してその夜は都内のホテルに宿泊した。翌10日(日)の早朝、荒川区南千住の素盞雄(すさのお)神社へ出かけた。

天王社の大銀杏:この木の皮を煎じて飲むと、乳の出が良くなるという伝承がある子育て銀杏。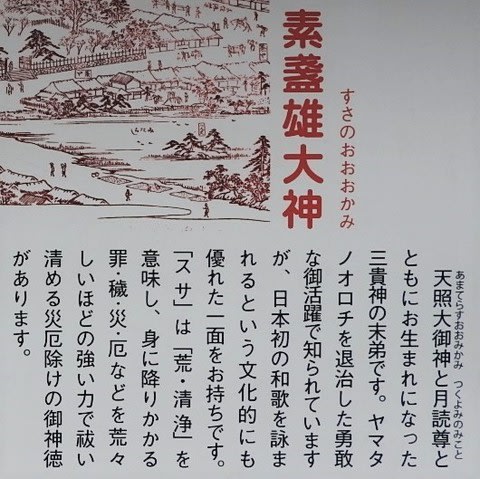

神社の御祭神は素盞雄大神と飛鳥大神の2柱
素盞雄大神は伊耶那岐命が禊で鼻を洗ったときに生まれた神様。ちなみに天照大御神は左の目、月読尊は右の目を洗ったときに生まれた(手元にある「古事記」橋本治/講談社で調べた)。
狛犬1

境内で最初に目にしたのは、灯籠台座の狛犬のレリーフ。
狛犬2
富士講 浅間神社の狛犬

宝暦10年(1760年)生まれ、狛犬マニアに「はじめちゃん」と呼ばれる古い狛犬
狛犬3
3基の庚申塔と狛犬


