
(再)塩尻市片丘南熊井 3柱66型トラス脚 2024.04.15
期間限定 火の見櫓と桜

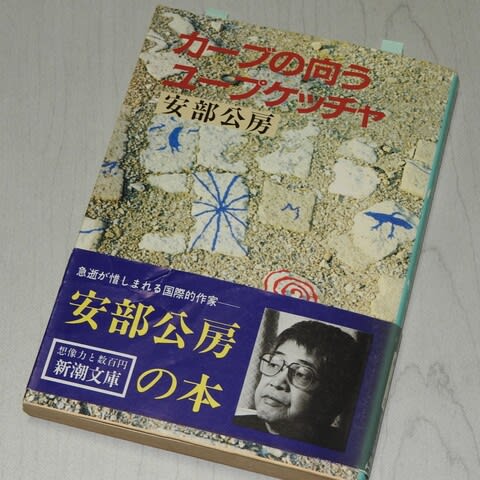 360
360
■ 安部公房の『カーブの向う・ユープケッチャ』(新潮文庫1988年12月5日発行、1993年2月15日4刷)を読んだ。
収録作品の『カーブの向う』は『燃えつきた地図』の原型、『ユープケッチャ』は『方舟さくら丸』の原型、『チチンデラ ヤパナ』は『砂の女』の原型となった短編。このように収録されている9編中3編が安部公房の代表作の原型作品であるのにもかかわらず、この文庫は現在絶版。なんとも残念。
『砂の女』の原型となった短編のタイトルのチチンデラ ヤパナって一体何? ネットで調べるとニワハンミョウという昆虫のことで、体長10~13mm。河川敷や海岸、畑地などの砂地に生息しているということが分かった。なるほど砂地か・・・。
『砂の女』には火の見櫓が出てくる。『チチンデラ ヤパナ』にも出てくるかもしれないな、と思いながら読み始めた。**とつぜん視界が開いて、小さな集落があらわれた。高い火の見櫓を中心に、小石でおさえた板ぶきの屋根が不規則にかたまった、貧しいありふれた村落である。**(126頁)やはり出てきた。
『手段』は駅の改札口の近くに設置されている「簡易交通障害保険自動販売機」にまつわる物語。主人公の男がこの自販機が扱う保険に詳しいという老人に声をかけられる。で、男は娘の修学旅行の費用が必要だと、老人に話すことに。保険の約款には怪我の部位、程度によって支払われる保険金が異なること、そして、それぞれの保険金額が示されている。
駅のホームに電車が進入してきて、男は・・・。星 新一も扱いそうなテーマだけど、だいぶテイストが違う。
『完全映画』この作品が「SFマガジン」に発表載されたのは1960年(昭和35年)のこと。予見的な作品。
『子供部屋』 **壁のコンクリートに這わせてあった水道管から、水もれがしはじめたんですよ。しだいに地下室が水びたしになりはじめる。やむなく、子供たちを隅の箱にかくして、水道屋を呼ばざるを得ませんでした。ところが子供たちが、箱の隙間から、工事人夫が作業をしている所を見てしまったんですね。**(212頁)
なんだか、『箱男』を思わせるこの描写。この作品が「新潮」に発表されたのは1968年(昭和43年)のことだった。で、『箱男』の発表が1973年(昭和48年)。この頃から『箱男』をイメージしていたのかもしれない・・・。
密度の高い作品集。繰り返す、絶版は残念。
手元にある安部公房の作品リスト(新潮文庫22冊 文庫発行順 戯曲作品は手元にない。2024年3月以降に再読した作品を赤色表示する。*印は絶版と思われる作品)
年内に読み終える、という計画でスタートした安部公房作品再読。4月14日現在6冊読了。残りは16冊。3月に出た『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』(新潮文庫)を加えたとして17冊。5月から12月まで、8カ月。2冊/月でほぼ読了できる。少しペースダウンして他の作家の作品も読もう。
『他人の顔』1968年12月
『壁』1969年5月
『けものたちは故郷をめざす』1970年5月
『飢餓同盟』1970年9月
『第四間氷期』1970年11月
『水中都市・デンドロカカリヤ』1973年7月
『無関係な死・時の壁』1974年5月
『R62号の発明・鉛の卵』1974年8月
『石の眼』1975年1月*
『終りし道の標べに』1975年8月*
『人間そっくり』1976年4月
『夢の逃亡』1977年10月*
『燃えつきた地図』1980年1月
『砂の女』1981年2月
『箱男』1982年10月
『密会』1983年5月
『笑う月』1984年7月
『カーブの向う・ユープケッチャ』1988年12月*
『方舟さくら丸』1990年10月
『死に急ぐ鯨たち』1991年1月*
『カンガルー・ノート』1995年2月
『飛ぶ男』2024年3月

■ 安部公房の『けものたちは故郷をめざす』(新潮文庫1970年5月25日発行、2021年5月10日26刷)を読んだ。3月から始めた安部公房作品再読の5作品目。
ドナルド・キーンは、安部公房の代表作『砂の女』(新潮文庫)の解説文の書き出しで前衛作家、安部公房という紹介をしている。そう、安部公房は前衛的な作風で知られている、シュールレアリスムの作家。それで、「え、これ安部公房?」、『けものたちは故郷をめざす』を読み始めると、まずこんな感想を抱く。リアルな描写で読みやすい。
主人公の少年・久木久三の父親は久三が生まれた直後に死に、母親は戦争の犠牲になった。先の大戦、敗戦前夜、天涯孤独の身となった彼は極寒の中国大陸を南進する、帰国を目指して。同行の男は正体不明、国籍さえ定かではない。
極寒の荒野を飢えと疲労の身を引きずるように彷徨うふたり。心理描写と身体感覚の描写は読む者を一緒に彷徨うような気持ちにする。私は暗い気持ちで読み進んだ。
この小説を読んでいてやはり日本への引き揚げの様子を描いた藤原ていの『流れる星は生きている』(過去ログ)を思い出した。
中国国内の地名が出てくるとネット上の地図でその場所を確認してもみた。まだ、こんな所か。生きて故郷日本にたどり着くことができるのだろうか・・・。
先が気になって、昨日(9日)はおよそ300頁の本作の後半、半分を一気に読んだ。『砂の女』もそんな読み方をしたことがあったかと思うが、安部公房の作品では珍しいことだ。
この長編小説の最後、久三は日本船の中の狭い間隙に監禁されてしまうという絶望的な状況に陥る。なんという悲劇。
最終場面の描写を引用する。**・・・・・ちくしょう、まるで同じところを、ぐるぐるまわっているみたいだな・・・・・いくら行っても、一歩も荒野から抜け出せない・・・・・もしかすると、日本なんて、どこにもないのかもしれないな・・・・・(後略)**(302頁)
そして最後の一文。**だが突然、彼はこぶしを振りかざし、そのベンガラ色の鉄肌を打ちはじめる・・・・・けものになって、吠えながら、手の皮がむけて血がにじむのもかまわずに、根かぎり打ちすえる。**(303頁)
この一文をどう解するか。絶望的な状況の更なる強調か。絶望的な状況を打破しようという久三の強い意志の表現か・・・。私は後者だと解したい。
*****
「喪失」あるいは本人の意思による「消去」は安部公房の作品を読み解くキーワードだ。このことは次のように例示できる。『夢の逃亡』は名前の喪失、『他人の顔』は顔の喪失、『砂の女』『箱男』は存在・帰属の消去。異論もあろう。言うまでもなく、これは私見。
そして『けものたちは故郷をめざす』は故郷の喪失。故郷とは何か、そしてその喪失とは・・・。安部公房は自身の戦争体験をベースに書いたと言われるこの作品で、読者に何を訴えたのか。
根なし草の寂しさか。否、久三の最後の窮地を日本の敗戦直後の状況の暗喩的な表現だと捉えて、上掲した最後の場面もやはり暗喩的な表現と捉えれば、その答えを知ることができるだろう。
手元にある安部公房の作品リスト(新潮文庫22冊 文庫発行順 戯曲作品は手元にない 2024年3月以降に再読した作品を赤色表示する。*印は絶版と思われる作品)
『他人の顔』1968年12月
『壁』1969年5月
『けものたちは故郷をめざす』1970年5月
『飢餓同盟』1970年9月
『第四間氷期』1970年11月
『水中都市・デンドロカカリヤ』1973年7月
『無関係な死・時の壁』1974年5月
『R62号の発明・鉛の卵』1974年8月
『石の眼』1975年1月*
『終りし道の標べに』1975年8月*
『人間そっくり』1976年4月
『夢の逃亡』1977年10月*
『燃えつきた地図』1980年1月
『砂の女』1981年2月
『箱男』1982年10月
『密会』1983年5月
『笑う月』1984年7月
『カーブの向う・ユープケッチャ』1988年12月*
『方舟さくら丸』1990年10月
『死に急ぐ鯨たち』1991年1月*
『カンガルー・ノート』1995年2月
『飛ぶ男』2024年3月
次にどの作品を読もうかな、と迷ったが『カーブの向う・ユープケッチャ』を読むことにした。
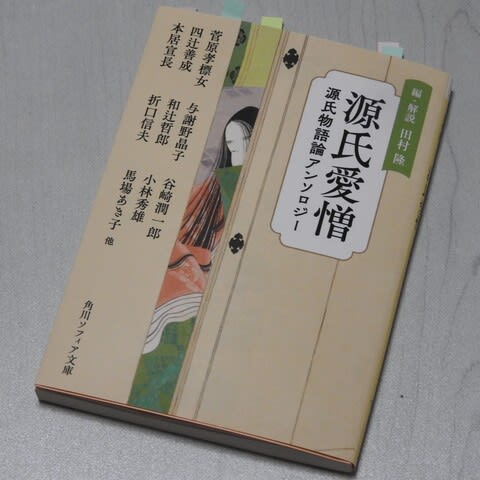 360
360
■『源氏愛憎 源氏物語論アンソロジー』編・解説 田村 隆(角川ソフィア文庫2023年)を読んだ。
古典や近現代作家他の源氏評の一部を抜粋して集めた評論集。しばらく前、松本駅近くの丸善で偶々この本を目にして迷うことなく買い求めた。『源氏物語』関連本は出来るだけ読もうと思っているので、やぐらセンサー、もとい源氏センサーが作動したのかもしれない。1000年も前、平安時代に書かれた『源氏物語』は名作という評価ばかりではない。様々な評価があることも名作の証なのかもしれない。
本書はⅠの古典篇とⅡの近代篇から成り、古典篇には現代語訳はないものの、解説文があるので分かりやすい。
平安末期に編まれたという「宝物(ほうぶつ)集」は仏教説話集。本書に次のようなことが掲載されている。
**ちかくは、紫式部が虚言(そらごと)をもつて源氏物語をつくりたる罪によりて、地獄におちて苦患(くげん)しのびがたきよし、人の夢にみえたりけりとて(後略)**(35頁) 紫式部が地獄に落ちた、なんて! ひえ~、びっくり。
『源氏物語』を三度現代語訳した谷崎潤一郎は次のように光源氏を評している。
**源氏物語の作者は光源氏をこの上もなく贔屓にして、理想的の男性に仕立て上げているつもりらしいが、どうも源氏という男にはこういう変に如才のないところのあるのが私には気に喰わない。**(143頁)
まあ、一部を切り取るだけではいけないので、他の人の評論の部分的な引用は控えよう。
近現代篇には15人の源氏評が収録されている。その中では円地文子の「源氏物語の構造」と題した評がもっとも教科書的というか、読んで納得できるものだった。
*****
「源氏物語」は通俗的でドロドロな恋愛小説ではないか、などという評がもしあるとすれば、それはこの物語の表面的な部分しか、読んでいない、とぼくは分かったような指摘をしておきたい。そんな小説であれば1000年も読み継がれるはずがない。
円地文子は「宇治十帖」を**たいへんよくできた中篇小説で、構成としては正篇よりもまとまっているだろうと思います。**(171頁)と評している。しかしその直後に**正篇がなかったならば、宇治十帖の光彩というものは、極端に薄れるでしょう。**(172頁)と指摘している。
NHKの100分de名著「源氏物語」4回分の再放送(4月7日午前0時40分~)を録画で見た。国文学者で平安文学、中でも「源氏物語」と「枕草子」が専門だという三田村雅子さんが解説していた。三田村さんは物語最後のヒロイン浮舟が好きだと言っていた。浮舟には紫式部の願いが投影されているとも。
『源氏物語』(もちろん現代語訳)をもう一度読む気力は無い。だが、「宇治十帖」は再読してもいいかなと思い始めている。
 490
490
1509 佐久市根岸 平井公民館 4柱4〇型ロングアーチ脚 2024.04.02
■ 今月(4月)2日、久しぶりのヤグ活(火の見櫓めぐり)を佐久市内でして、20基観察した。この日の走行距離は193km、歩数はおよそ8,000歩だった。ヤグ活は思いの外歩く。本稿はその最後、20基目の火の見櫓の紹介。
下の3カットはほぼ同じ範囲を写している。(※ 私のパソコンの画面では3カット横並び表示)
・左はほぼ真横から撮った。坂道の脇に立つ火の見櫓だったので坂を登って少し遠くから撮った。立地的に撮影可能であれば撮るアングル。立面的な形状が分かりやすい。
・中は屋根と見張り台を1カットで撮る時、よく使うアングル。ほぼ毎回このアングルは撮る。立体的な形状が分かりやすい。
・右は火の見櫓のごく近くから見上げて撮った。見張り台や屋根の平面形が分かりやすいが、あまり撮らない。
火の見櫓の見え方は当然のことながら、アングルによってかなり違う。何を伝えたいのか、そのことを伝えるのにはどんなアングルが良いか。情報伝達の手段としての写真を考えて撮りたい。自省。



踊り場。折り返し梯子を掛けるのに必要なスペースをバルコニー型の踊り場(カンガルーポケットと呼んでいる)によって確保している。このタイプは東信・北信地域に多い。見張り台と同様に下膨れの手すりが設置されている。
脚は典型的なロングアーチ。これなら判断に迷うことはない。逆さU形。好きなカーブ。

1508 佐久市大沢 4柱44型たばね脚 2024.04.02
■ 火の見櫓は道路脇に立っていることが多い。電柱も同様であることから、上掲写真のように電線が邪魔になることが少なくない。他に適当なアングルが見つけられなければ仕方ない、周辺の様子が分かればよい、とあきらめて撮る。

半鐘を囲むようにスピーカーが設置されている。これは切ない。前稿、佐久市取手町の火の見櫓のような位置に設置するのが好ましい。
「昭和四十一年五月二十五日 警鐘楼建設 施工 平嶋鉄工所」屋根の裏面に建設年月日他が記されていた。こういうの初めて見た。漫然と見ていると見落とすこともあるだろう。気がついた自分に◎ 

踊り場の様子。上下の梯子の方向が180度違う。共に櫓内で設置されているので、上下で向きを変えない直進型の設置は無理。
コンクリート塊の基礎が大きく露出している。こういう基礎を見かけないわけではないが、それ程多くはないと思う。

1507 佐久市取手町 4柱4〇型トラス脚 2024.04.02
■ 気がつくままに記す。
屋根が少し小さいという印象。屋根上の派手な飾りは今回のヤグ活で何回か見た。蕨手が小さい。
柱のところに木槌を掛けてある。木槌があると現役感があって好い(実際に使われているかどうかは別として)。
見張り台の内側の手すりの様子がよく分かる。
スピーカーの設置場所はここ、見張り台の下が好ましい。屋根下より存在感が軽減される。
踊り場の上下で梯子の向きが変わっていない。下の梯子の手すりを上の梯子まで伸ばしている。これは移動しやすいだろうな。
脚部 トラス脚かロング3角脚か判断に迷う。迷うというとは明確に定義されていないということ。さて、どうする・・・。 280
280
火の見櫓の隣の百番観音堂に吊り下げられていた鐘。

1506 佐久市平賀 上宿公会場 4柱44型たばね脚 2024.04.02
■ この火の見、全体のバランスが良いと思う。いいなぁって思う姿かたちって、ひとつじゃないんだな。やはり、みんなちがって みんないい。
緩勾配の方形屋根 避雷針に飾り無し ちょこんと小さな蕨手。見張り台の手すりのシンプルなデザイン。見張り台の開口上部の柱にも手すりを付けている。
必要最小限の踊り場。
典型的なたばね(束ね)脚。アーチ部材のカーブも好い。

佐久市茂田井にて 2024.04.02
地面の蓋の後方に立つ火の見櫓は後ろに迫る落葉樹林と同化していて、姿かたちがよく分からない。
◎ ひらがなで「もたい」とだけ表記されているマンホール蓋。漢字では茂田井。江戸時代にはひとつの村としてまとまっていた茂田井は現在行政上、立科町茂田井と佐久市茂田井とに分かれている。佐久市と立科町にまたがるこの地区で特定環境保全公共下水道事業を運営している川西保健衛生施設組合(構成団体は佐久市、東御市、立科町)の蓋。下に載せた立科町の蓋と同じデザインで「たてしな」という表記だけが違う。
マンホール蓋の外周にはスズランがデザインされている。シラカバ、その後ろは女神湖か。背景には蓼科山が描かれている。円形の中にうまく納めたデザインだと思う。

1505 佐久市内山 4柱4〇型ロング3角短脚 2024.04.02
国道254号脇から見た火の見櫓。2022年7月に群馬の火の見櫓めぐりから帰る時もここを通ったが、もっと遠くからこの火の見櫓に気がついていたと思う。
屋根と見張り台の手すりの間の空きが少ない。手すりが高いのか、屋根が低いのか・・・。見張り台の床面から屋根下端(軒先)までの高さは2mくらいが標準ではないか、と思う。どうも手すりが高いようだ。
正面から見ると櫓のフォルムが分かりやすい。櫓の上に見張り台と屋根が載っている感、強し。見張り台に対し、それを支える櫓上端のサイズが小さいように感じる。こういうバランスもありだ。



1504 佐久市内山 肬水神社(石宮神社)のすぐ近く 4柱44型ロング3角短脚 2024.04.02
■ 2022年の7月、群馬県で火の見櫓めぐりをした。帰路、国道254号で下仁田町から佐久に入った。その時、この火の見櫓と出会った。車を停める適当な場所も見つからず、夕方ということもあり、観察をあきらめて通り過ぎた。また、来よう。
今月(4月)2日に佐久に出かけたのはこの辺りで見かけていた数基の火の見櫓を見たかったから。火の見櫓の後方に懸崖造りの肬水神社(石宮神社)の社殿があるが、そちらの観察はパス。
岩盤の崩落防止のためだろう、アンカーが設置されている。その前に立つ火の見櫓は強固な印象。背景によって火の見櫓の印象は変わる、ということだろうか・・・。
ロング3角短脚。この形が直線的に下方に広がる櫓の脚としてよく似合っていると思う。やはりデザインはいいとこ取りではダメ、ということだ。火の見櫓から学ぶことは多い。

1503 佐久市内山 4柱8〇型たばね脚(柱材とアーチ形の補強部材を脚元まで束ねている)
2024.04.02
■ 背が高くて、かなり細身の火の見櫓。なんだか不思議な、表現のしようがないような雰囲気が漂っている。なぜだろう・・・。

カンガルーポケットな踊り場 見張り台と同じように下膨れした手すり、蔓状の飾りも同じ。
基礎コンクリ―トが雑草で覆われている。ちょっと悲しい・・・。

1502 佐久市内山 4柱44型複合脚(正面たばね脚、残り3面交叉ブレース)2024.04.02
■ 今回見てきた火の見櫓の大半が、この火の見櫓と同様に見張り台床面の開口上部の柱廻りに手すりを設置している。これは安全対策として好ましい。発錆していない火の見櫓は見ていて気持ちが良い。端正なつくりの火の見櫓。
踊り場の様子 梯子の切り替えスペースとして、これがミニマムな設え。
複合脚 正面のみたばね脚で開口を確保し、残り3面は交叉ブレースを設置している。

◎ 佐久市下水道組合の地面の蓋 佐久市前山にて 2024.04.02
佐久市の花・コスモスがデザインされている。几帳面なデザイナーの作品とみた。