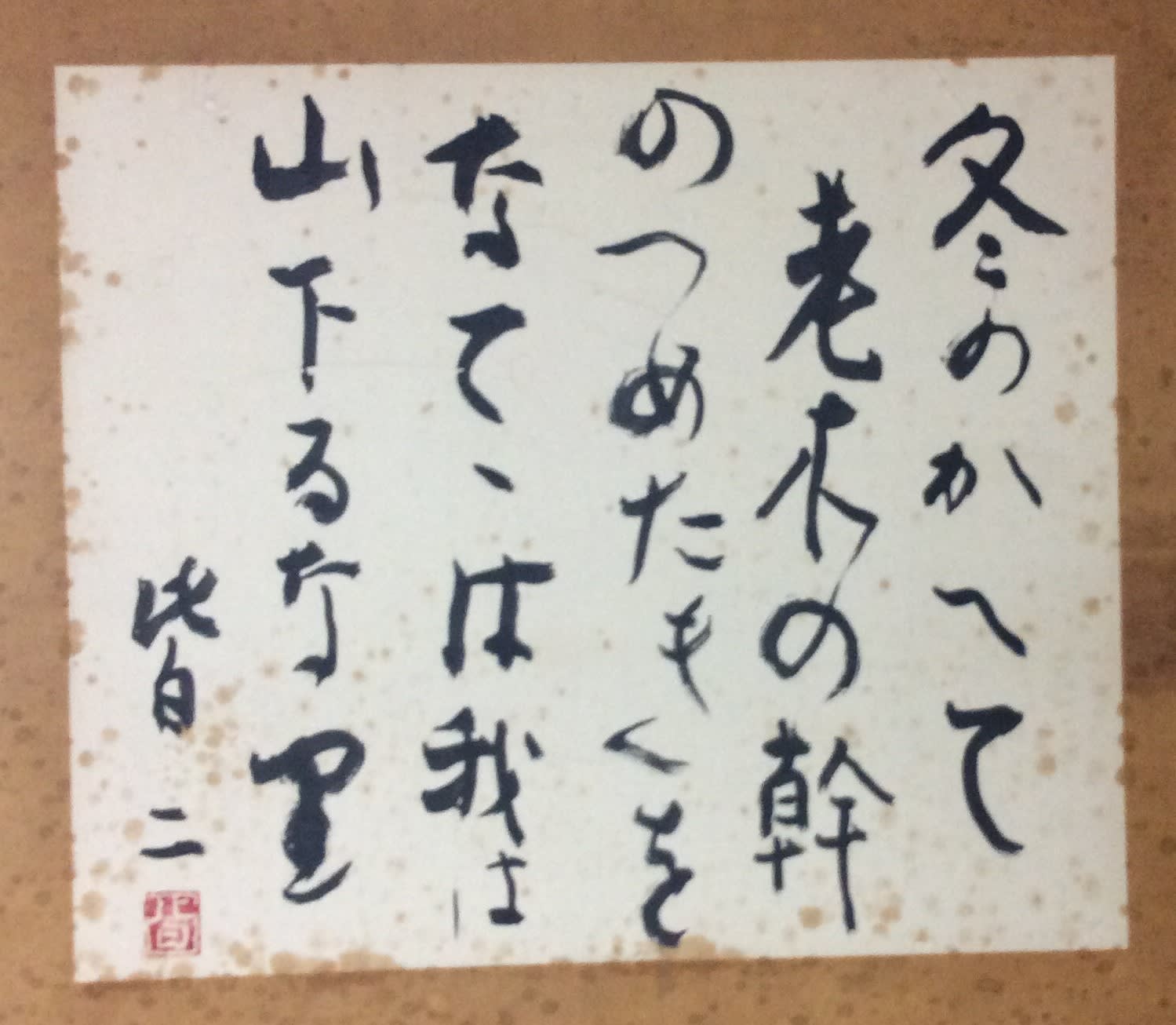72年前の今日、日本は連合国に無条件降伏。
昭和天皇がラジオで終戦の詔勅を放送。
私は2歳。オジサンの背中で聞いていたそうです。
詔勅というのは天皇が臣民に下す文書。
国民はみな天皇の赤子という地位に置かれているのです。
昭和18年生まれの私は、天皇の赤子だったのです。
敗戦によって新しい憲法が施行されます。
私は主権ある国民に生れ変ったわけです。
今、安倍さんたちは、再び、国民を臣民とするような
憲法に変えようとしています。
二度と臣民となることは御免こうむりたいものです。
昭和天皇がラジオで終戦の詔勅を放送。
私は2歳。オジサンの背中で聞いていたそうです。
詔勅というのは天皇が臣民に下す文書。
国民はみな天皇の赤子という地位に置かれているのです。
昭和18年生まれの私は、天皇の赤子だったのです。
敗戦によって新しい憲法が施行されます。
私は主権ある国民に生れ変ったわけです。
今、安倍さんたちは、再び、国民を臣民とするような
憲法に変えようとしています。
二度と臣民となることは御免こうむりたいものです。