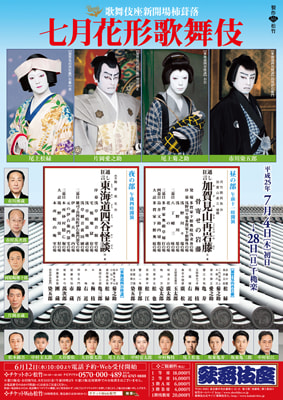あけぼの山農業公園のハスは八重咲き。時間も正午を過ぎていたが、綺麗な花を見ることが出来た。ツボミも多数あるので、まだまだ息長く楽しめそうだ。
ハス科ハス属
2013年7月19日午後12時半過ぎ





閲覧有難うございました。
コメント欄閉じています。
メモ
・ハスは多年性水生植物。
・蜂の巣状の花托に果実が実ることからハチス→ハスという名になったと言われている。
・根の部分(実際は地下茎)は食用、蓮の根すなわち蓮根(レンコン)と呼ばれる。
・原産地はインド亜大陸とその周辺(現在のアフガニスタンからベトナムを含む)。
・地中の地下茎から茎を伸ばし水面に葉を出す。
・草高は約1m、茎に通気のための穴が通っている。
・水面よりも高く出る葉もある(スイレンにはない)。
・葉は円形で葉柄が中央につき、撥水性があって水玉ができる(ロータス効果)。
・花期は7~8月で白またはピンク色の花を咲かせる。
・インドの国花。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より