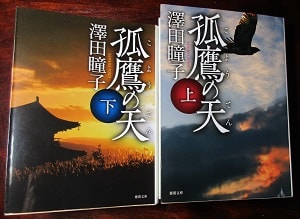
澤田瞳子さんのデビュー作で、第17回中山義秀文学賞を受賞した『孤鷹(こよう)の天』。
(上)【藤原清河の家につかえる高向斐麻呂は唐に渡ったまま帰国できぬ父を心配する娘・広子のために唐に渡ると決め、大学寮に入学した。儒学の理念に基づき、国の行く末に希望を抱く若者たち。奴隷の赤土に懇願され、ひそかに学問を教えながら友情を育む斐麻呂。そんな彼らの純粋な気持ちとは裏腹に、時代は大きく動き始める】
(下)【仏教推進派の阿倍上皇が大学寮出身者を排斥、儒教推進派である大炊帝との対立が激化。斐麻呂が尊敬する先輩・桑原雄依は、寝返った高岡比良麻呂を襲撃、斬刑に処せられた。雄依の親友で弓の名手・佐伯上信は、雄依の思いを胸に大炊帝、恵美押勝らと戦いに臨む。「義」に準ずる大学寮の学生たち、不本意な別れを遂げた斐麻呂と赤土。彼らの思いはどこへ向かう?】
奈良時代の下級貴族の教育機関であった学生寮には様々な境遇の学生がいたが、いずれも個性的な人物として描かれ、その人間性が浮かび上がる。
藤原光明子(阿倍上皇)が皇后位に昇ったとき、眉に火のついた焦り方で藤原家は長屋王の一族を滅ぼした。これは『穢土荘厳』(杉本苑子)でかつて読んだが、その政変で唯一生き残った長屋王の孫・磯部王が登場する。かつて大学寮に人一倍長く在籍し、阿倍の世で唯々諾々と任官を続けている。
そんな彼が、阿倍上皇を前にして斐麻呂の命を救ったはかりごとは痛快でもあった。
その場で道鏡は、磯部王の口車にのせられ御仏の慈悲、教導を説き、恩赦を口にする…。道鏡も、黒岩重吾が描いた道鏡像とは異なる。
より良い国づくりを思い、それぞれが信じる「義」のために命を投げ出して、時勢と戦う者たちの生きざま。
一つの根から出だ枝葉だが、この世をどのように過ごすかは、各々異なる。それぞれがこうと信じた義で戦い、破れ、泥にまみれた。それでも歯を食いしばって立ち上がった遺業。
「激動する世につれ、自在にたくましく生き抜け」。最晩年、比良麻呂はこう木簡に記し、斐麻呂に託した多くの書籍の中の一冊に挟んで残した。
この時代の作品に登場する牛馬のごとく扱われる境遇のの存在は、いつも悲しく絶望的で重く心に沈む。額に所属を示す焼印を捺され、生涯苦役を強いられる。牛馬以下、物品の価格で売り買いされる奴隷だ。良民になりたい赤土。学問に貴賤はない。狂った歯車。…彼の存在は最後まで心を離れなかった。戦で瀕死の状態を生き延び、赤土は唐に渡っていた、とみられる。一羽の鷹のごとく、自分の生きるべき地を見つけ、降り立った…。
 不明なことの多い時代を背景に、作家の新しい解釈、発想を楽しめる歴史小説。そんな世界を読むことができた喜び。堪能したなあ~と胸を満たしている。
不明なことの多い時代を背景に、作家の新しい解釈、発想を楽しめる歴史小説。そんな世界を読むことができた喜び。堪能したなあ~と胸を満たしている。















