大徳寺高桐院の三齋公の墓所は、利休遺愛の石燈篭である。秀吉の所望を逃れるためわざと蕨手が欠かれた。この石燈篭と、加藤清正から贈られた「袈裟形おり蹲」という蹲を、三齋は参勤の折には熊本から持ち運んだと言う。「鷺絵源三郎久重覚書」にも、この石燈篭が八代にあることを書き記している。さて三齋は正保ニ年十二月二日八代に於いて亡くなった。翌年一月廿四日遺骨が高桐院に分骨された。三齋の遺言であった。「松江(八代)城秘録」に次のような記録がある。
三齋様被仰候ハ御逝去被成候ハ御骨ハ大徳寺ニて高桐院へ指上御秘蔵之石燈爐御座候間それを御こツの上に被置候様ニと日比高桐院へ御約定ニ而御座候・・とある。
三齋様被仰候ハ御逝去被成候ハ御骨ハ大徳寺ニて高桐院へ指上御秘蔵之石燈爐御座候間それを御こツの上に被置候様ニと日比高桐院へ御約定ニ而御座候・・とある。

















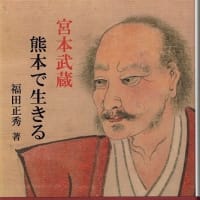







となります。なにとぞよろしくお願いいたします。