荒木左馬助(荒木村重・孫)の事について、烏丸大納言の二月五日付の書状が忠利の手元に届いたのは、有馬一揆における決戦の日(二月廿七日)のさな中の事である。慌しい中で書状に目を通した事が、次の返信の書状に窺える。
二月五日荒木左馬助殿御事伝之書状二月廿七日相届拝見仕候
先以其元相替儀無御座候由珍重奉存候 仍有馬表之儀去月廿七
日・八日両日ニ事済申候 手前も三之丸を通り本丸にも乗込大将
四郎首も我等手へ討捕申候間可御心安候 次ニ左馬助殿之儀被
仰下候廿七日本丸きわ迄押詰申候刻二之丸ニて初而御しる人ニ
罷成候 其後陳場へ御尋も無之候故其時之首尾をも然々不承候
其上我等有馬埒明申候故上使衆御差図ニ而罷帰申付而相当之
御用をも不承近比御状之印も無御座迷惑仕候 猶重而可申上候
恐惶謹言
三月五日
烏丸大納言様
御報
後に烏丸大納言の肝煎りにより細川家家臣となる、荒木左馬助の消息が窺える貴重な書状である。左馬助が有馬の陳中にあることが窺えるが、上使の何方かに付いての出陣で在ったのだろう。幕臣としての道は義母の不幸な事件で潰え、細川家家臣(細田氏)となる人の貴重な史料で、何度も目を通したはずの「熊本縣史料--近世編三(部分御舊記)」から見つけ出して吃驚している。
参考: 荒木左馬助ハ攝津守村重の孫ニて、父ハ新五郎と申候、左馬助幼少にて親ニ離れ、
浅野但馬守殿江罷在候へ共、御直参を願ニ而京都に居住、烏丸光広卿前廉村重と
御入魂の訳を以江戸に被召連、光尚君へ被仰談候、則忠利君より被仰立、公儀江
被召出候、其比御城女中あらきと申人子無之ゆへ左馬助を養子可仕旨上意有之、親
類ニ而も無之候へとも上意ゆへ親子のむすひいたし候、然処右之女中故有て今度流
罪被仰付候間、左馬助も其儘被差置かたく御預ニ成、後熊本ニて果候
大日本近世史料-細川家史料(-1289-)忠利より肥後(光尚)宛て書状
(頭注)烏丸光廣荒木村常ノ召出ヲ肝煎ス、光廣死去ノタメ忠利ヨリ松平信綱へ依頼ス
荒木左馬殿之事、内々烏丸大納言(光廣)殿御肝煎候へとも、御死去二候、肥後ニも
内々御頼候へとも、大納言殿御座候間可被候とて、ひかへ候へとも、大納言殿御は
て候へハ、可被使用無之候ニ付、申候、一筋にても候條、いかようの躰にても、御奉
公成事ニ候ハゝ、御肝煎被成可被候由、松伊豆(松平信綱)殿迄書状遣はづニ、此方
申合候、其方と談合之上可申候へ共、其元へ申遣、其返事之間候へハ、伊豆殿御番
はつれ候故、加藤勘介(重正)殿と申合、如此候、其方判紙にて状を調可遣候、遣候
ハゝ、留を見せ可申候、恐々謹言
(寛永十五年)十二月廿 越中
忠利(花押)
肥後殿
進之候
(寛永廿一年)五月十日御老中より之奉書
一筆申入候、荒木左馬助事、母不届有之付、其方へ被成御預候間、其国可被指
置候、扶持方等之儀委細留守居之者迄可相達候、恐々謹言
五月十日 阿部対馬守
阿部豊後守
細川肥後守殿 松平伊豆守
(綿考輯録・巻六十一)
二月五日荒木左馬助殿御事伝之書状二月廿七日相届拝見仕候
先以其元相替儀無御座候由珍重奉存候 仍有馬表之儀去月廿七
日・八日両日ニ事済申候 手前も三之丸を通り本丸にも乗込大将
四郎首も我等手へ討捕申候間可御心安候 次ニ左馬助殿之儀被
仰下候廿七日本丸きわ迄押詰申候刻二之丸ニて初而御しる人ニ
罷成候 其後陳場へ御尋も無之候故其時之首尾をも然々不承候
其上我等有馬埒明申候故上使衆御差図ニ而罷帰申付而相当之
御用をも不承近比御状之印も無御座迷惑仕候 猶重而可申上候
恐惶謹言
三月五日
烏丸大納言様
御報
後に烏丸大納言の肝煎りにより細川家家臣となる、荒木左馬助の消息が窺える貴重な書状である。左馬助が有馬の陳中にあることが窺えるが、上使の何方かに付いての出陣で在ったのだろう。幕臣としての道は義母の不幸な事件で潰え、細川家家臣(細田氏)となる人の貴重な史料で、何度も目を通したはずの「熊本縣史料--近世編三(部分御舊記)」から見つけ出して吃驚している。
参考: 荒木左馬助ハ攝津守村重の孫ニて、父ハ新五郎と申候、左馬助幼少にて親ニ離れ、
浅野但馬守殿江罷在候へ共、御直参を願ニ而京都に居住、烏丸光広卿前廉村重と
御入魂の訳を以江戸に被召連、光尚君へ被仰談候、則忠利君より被仰立、公儀江
被召出候、其比御城女中あらきと申人子無之ゆへ左馬助を養子可仕旨上意有之、親
類ニ而も無之候へとも上意ゆへ親子のむすひいたし候、然処右之女中故有て今度流
罪被仰付候間、左馬助も其儘被差置かたく御預ニ成、後熊本ニて果候
大日本近世史料-細川家史料(-1289-)忠利より肥後(光尚)宛て書状
(頭注)烏丸光廣荒木村常ノ召出ヲ肝煎ス、光廣死去ノタメ忠利ヨリ松平信綱へ依頼ス
荒木左馬殿之事、内々烏丸大納言(光廣)殿御肝煎候へとも、御死去二候、肥後ニも
内々御頼候へとも、大納言殿御座候間可被候とて、ひかへ候へとも、大納言殿御は
て候へハ、可被使用無之候ニ付、申候、一筋にても候條、いかようの躰にても、御奉
公成事ニ候ハゝ、御肝煎被成可被候由、松伊豆(松平信綱)殿迄書状遣はづニ、此方
申合候、其方と談合之上可申候へ共、其元へ申遣、其返事之間候へハ、伊豆殿御番
はつれ候故、加藤勘介(重正)殿と申合、如此候、其方判紙にて状を調可遣候、遣候
ハゝ、留を見せ可申候、恐々謹言
(寛永十五年)十二月廿 越中
忠利(花押)
肥後殿
進之候
(寛永廿一年)五月十日御老中より之奉書
一筆申入候、荒木左馬助事、母不届有之付、其方へ被成御預候間、其国可被指
置候、扶持方等之儀委細留守居之者迄可相達候、恐々謹言
五月十日 阿部対馬守
阿部豊後守
細川肥後守殿 松平伊豆守
(綿考輯録・巻六十一)

















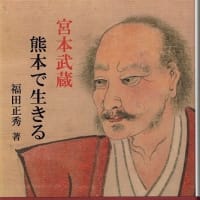







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます