先のブログ「熊本の儒学がたどった道」のなかで、「細川護貞さまは、昭和10年以降太平洋戦争に至る日本の取り返しのつかない愚行は、その師・狩野君山の言として「みんな宋学(朱子学)のせいだ」という認識を共有されている。」と書いた。
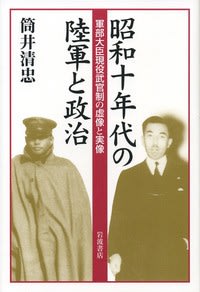
最近私は、「昭和十年代の陸軍と実像-軍部大臣現役武官制の虚像と実像」という本を購入して読んでいる・
「1936年に復活した軍部大臣現役武官制によって陸軍は暴走し、日本は戦争への道を歩んでいくという歴史認識が定着して久しい。この見方はいかに誤っているのか。陸相のポストをめぐり陸軍と首相が対立した昭和10年代の全ケースを精査し、その対立の内実を初めて解明した本書は、昭和史の常識を覆す注目の書。」とあるが、2・26事件直後から米内内閣の倒閣までを詳しく取り上げている。著者の筒井清忠氏は「軍部大臣の現役武官説が陸軍の暴走を可能にした」説に疑義を感じながらこの著を上梓された。その内容は私の認識を打ち砕くものであった。
その時代の一時期は、護貞さまにとっては政治の中枢に身を置いておられた。岳父である近衛文麿の秘書官であられた。
その詳細は護貞さまの著「情報天皇に達せず(細川日記=黙語録)」に詳しい。
又、護貞さまが親しくされておられた原田熊雄(細川護貞著「思い出の人々」)の女婿・勝田龍夫の著「重臣たちの昭和史」も、元老西園寺公望の三羽烏といわれた近衛文麿・木戸幸一・そして原田熊雄などの話をもとに天皇周辺の実相に迫っていて、かって一気呵成に読了したが名著だと思っている。
又、半藤一利の「昭和史」「日本のいちばん長い日」も親しみやすく読了した。
ただ、これらの深刻な内容のそれぞれの著作から、「朱子学」の匂いを嗅ぎ取ることは浅学菲才の爺には100%できない。
君山のこの見解に関する簡明な論考などないものかと思っている。君山は我が祖母の叔父にあたる人だが、とにかく話が難しくてついていけない。



















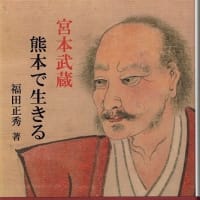





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます