頼母佐英貴君之傳 始平吉様
一、慶長五年七月田邊御籠城立行君ハ木附表江被成御座候興道君ハ忠興公江御従被成
関東江御越被成候此時丹後宮津ニ而立行君二御次男御出生頼母佐様ニ而御座候御
母君ハ御万様と奉申候宮津を御出被成京都江兼而御知音之寺あり天龍寺の塔頭良安
寺と云此寺を御志被成御家司葛西左衛門入道行善ニ御臺所人壱人御茶頭壱人其外下
々少々被召連御越被成候事
一、元和五年八月平吉様御家督被仰出候頼母佐英貴君と奉申候事
一、忠利公御備立を定置給ふニ付而英貴君御馬乗中御知行附を被差出候其節之御馬乗中
左之通ニ御座候事
一、八百石 葛西惣右衛門 一、六百石 八坂又助
一、弐百石 葛西九兵衛 一、弐百石 斎木菅沼と改半右衛門
一、弐百石 徳永一兵衛 一、弐百石 沢太郎兵衛
一、弐百三拾石 生地久兵衛 一、弐百石 長坂五郎兵衛
一、弐百石 立川四郎兵衛 一、弐百石 門司喜左衛門
一、弐百石 上林長右衛門 一、弐百石 武藤十右衛門
一、弐百石 中山半右衛門 一、百八拾石 岡部(本 上田)形右衛門
一、百五拾石 斎木半助 一、百五拾石 木部清大夫
一、百五拾石 松田善大夫 一、百五拾石 舟木次右衛門
一、百五拾石 中山羽右衛門 一、百五拾石 名玉善右衛門
一、百五拾石 松田(赤尾ト改)嘉右衛門 一、百三拾石 奥田杢右衛門
一、百弐拾石 原田庄右衛門 一、百石 豊■十兵衛
一、百石 西尾吉右衛門 一、百石 岡田作左衛門
一、百石 菅 五大夫 一、百石 山田作右衛門
〆弐拾八人
一、寛永九年十月四日忠利公御途上不及御献上物家光公台命其方父三齋ハ度々當家ニ忠
節を謁し且又其方多年吾西丸已来親切之奉公他ニ勝事祝着せり仍而今度父子之勤労
を常ニ忘ざる験ニ肥後國十ニ郡五拾壱万九千餘石并ニ豊後國三郡弐万餘国都合五拾四
万国を遣すとの上意有又三齋様を召て右之上意有其方ハ八代之城二居られよ然時は細
國ニ於て何事有る共心安しとの上意にて御座候事
一、同年十ニ月肥後國へ御入國被成其後忠利公熊本二おゐて大身小身之面々江屋舗を被
下候英貴君ニ三ノ丸御屋敷並河志广居住之屋敷御拝領京町村坪井竹部ニ而下屋敷御
拝領御約束通御城主之御格ニ而御府中ニ御蔵屋敷被成御免竹部下屋敷ニ而御拝領坪
井蔵と唱申候事
一、忠利公京町口之要害御巡見被成候へ而英貴君を召て京町御下屋敷割等御覧被成此所
ニ外郭を御築せ給ふべし然ハ此所は薩州より豊前海(ママ)道之物口なり西ニ大身之屋敷
を取置べし東ハ其方下屋敷なる間人の知たる者ゆへ此所ニ葛西惣右衛門を可置旨御意
御座候ニ付奉畏候段御請被仰上候惣左衛門儀ハ 三齋様御代より御懇意被成毎度御前
ニ被召出其後忠利公も惣左衛門前御通之節羽毎度御目見被仰付遠方迄抔被召連御事
も度々御座候事
一、忠利公御意ニよつて京町御下屋敷浦出居外堀東方崖上迄堀通シ申筈之御縄張ニ而
御座候此所御普請英貴君御時分之御人数ニ而御動被成候其節御鉄炮頭斎木菅沼と改半
右衛門御普請相勤候処右之外堀東之方崖上ニ而堀はじ通り畑三枚堀残し置候ニ付半右
衛門江様子御尋被成候処半右衛門申上候ハ堀通し申候得而者崖上ニ而大雨之節水落
候て崖抜可申候間只今残居候分者先堀残置可然段申上候ニ付御見聞被成候処尤成儀
ニ被思召上候ニ付其通ニ被仰付置候其御成就仕忠利公御巡見被成候節右之所之儀御
尋被成候ニ付英貴君右之通ニ被●上候若御用之節ハ御縄張之通何時ニ而も堀切を可申
段被●上候処忠利公尤ニ被思召上候御用之時ハ堀切土手を築キ可申間夫迄ハ英貴君
へ御預被成候段御意御座候ニ付英貴君半右衛門江其所直ニ御預被成候ニ付今以半右
衛門子孫支配仕来申候又後年四郎右衛門貞親君 実相院様と奉申候 御代綱利公 妙應院様
京町御茶屋ニ被為入候節御茶屋詠次口より野得御慰ニ御出被成候節も右之被堀残置候
訳合委ク被仰上候其後重而被為入候節之ために右三枚之内壱枚ハ道ニ被仰付其所ニ須
戸口を御明被成飾之様ニ出入不支候様被仰付候事
一、寛永十年正月元旦年頭之御規式御座候英貴君豊前已来御禮申上来候面々を被差出候
御家司葛西惣右衛門御鉄炮頭以下斎木菅沼半右衛門・生地久兵衛・長坂五郎兵衛・立川
四郎兵衛・岡部上田形右衛門・武藤十左衛門・中山半右衛門・斎木半助・木部清太夫・門
司喜左衛門 右之面々年始五節句御禮申上候事
一、忠利公御大國御拝領被成候ニ付而英貴君江三千五百石之御加禄を給る都合壱万八千
石又忠利公御意被成候ハ其方家ハ武蔵守已来長岡之称号を授来候へ共於當家ニ有吉
之名字者無隠旧臣なり将軍様ニもよく御存知なり先年内膳を大樹公御尋之節も長岡内膳
と申上候得ハ有吉たるかと上意ニ付有吉なる由を申上候ケ様之事も有之候ニ付時代押移
當家重代之名字なきが如くなるべし同ハ有吉の苗字相續可然候夫共ニ称号致度候ハゝ
いつとても勝手次第ニ可改儀心次第と御意致成候ニ付家筋之名字相續可仕旨御請被仰
上候事
一、寛永十四年八月藤崎八旛宮江忠利公・光利公 後光尚公真源院様と奉申候 御武運御長久の
ため英貴君松井佐渡殿被仰談ニ而神前ニ鉄之燈籠を御寄進被成り永ク神籠を被献依之
御代ニ御懈怠なく被献候又御祭礼ニ社僧等之乗馬かざり馬を被差出又後年鋒三本を御
寄進被成候事
一、慶長五年七月田邊御籠城立行君ハ木附表江被成御座候興道君ハ忠興公江御従被成
関東江御越被成候此時丹後宮津ニ而立行君二御次男御出生頼母佐様ニ而御座候御
母君ハ御万様と奉申候宮津を御出被成京都江兼而御知音之寺あり天龍寺の塔頭良安
寺と云此寺を御志被成御家司葛西左衛門入道行善ニ御臺所人壱人御茶頭壱人其外下
々少々被召連御越被成候事
一、元和五年八月平吉様御家督被仰出候頼母佐英貴君と奉申候事
一、忠利公御備立を定置給ふニ付而英貴君御馬乗中御知行附を被差出候其節之御馬乗中
左之通ニ御座候事
一、八百石 葛西惣右衛門 一、六百石 八坂又助
一、弐百石 葛西九兵衛 一、弐百石 斎木菅沼と改半右衛門
一、弐百石 徳永一兵衛 一、弐百石 沢太郎兵衛
一、弐百三拾石 生地久兵衛 一、弐百石 長坂五郎兵衛
一、弐百石 立川四郎兵衛 一、弐百石 門司喜左衛門
一、弐百石 上林長右衛門 一、弐百石 武藤十右衛門
一、弐百石 中山半右衛門 一、百八拾石 岡部(本 上田)形右衛門
一、百五拾石 斎木半助 一、百五拾石 木部清大夫
一、百五拾石 松田善大夫 一、百五拾石 舟木次右衛門
一、百五拾石 中山羽右衛門 一、百五拾石 名玉善右衛門
一、百五拾石 松田(赤尾ト改)嘉右衛門 一、百三拾石 奥田杢右衛門
一、百弐拾石 原田庄右衛門 一、百石 豊■十兵衛
一、百石 西尾吉右衛門 一、百石 岡田作左衛門
一、百石 菅 五大夫 一、百石 山田作右衛門
〆弐拾八人
一、寛永九年十月四日忠利公御途上不及御献上物家光公台命其方父三齋ハ度々當家ニ忠
節を謁し且又其方多年吾西丸已来親切之奉公他ニ勝事祝着せり仍而今度父子之勤労
を常ニ忘ざる験ニ肥後國十ニ郡五拾壱万九千餘石并ニ豊後國三郡弐万餘国都合五拾四
万国を遣すとの上意有又三齋様を召て右之上意有其方ハ八代之城二居られよ然時は細
國ニ於て何事有る共心安しとの上意にて御座候事
一、同年十ニ月肥後國へ御入國被成其後忠利公熊本二おゐて大身小身之面々江屋舗を被
下候英貴君ニ三ノ丸御屋敷並河志广居住之屋敷御拝領京町村坪井竹部ニ而下屋敷御
拝領御約束通御城主之御格ニ而御府中ニ御蔵屋敷被成御免竹部下屋敷ニ而御拝領坪
井蔵と唱申候事
一、忠利公京町口之要害御巡見被成候へ而英貴君を召て京町御下屋敷割等御覧被成此所
ニ外郭を御築せ給ふべし然ハ此所は薩州より豊前海(ママ)道之物口なり西ニ大身之屋敷
を取置べし東ハ其方下屋敷なる間人の知たる者ゆへ此所ニ葛西惣右衛門を可置旨御意
御座候ニ付奉畏候段御請被仰上候惣左衛門儀ハ 三齋様御代より御懇意被成毎度御前
ニ被召出其後忠利公も惣左衛門前御通之節羽毎度御目見被仰付遠方迄抔被召連御事
も度々御座候事
一、忠利公御意ニよつて京町御下屋敷浦出居外堀東方崖上迄堀通シ申筈之御縄張ニ而
御座候此所御普請英貴君御時分之御人数ニ而御動被成候其節御鉄炮頭斎木菅沼と改半
右衛門御普請相勤候処右之外堀東之方崖上ニ而堀はじ通り畑三枚堀残し置候ニ付半右
衛門江様子御尋被成候処半右衛門申上候ハ堀通し申候得而者崖上ニ而大雨之節水落
候て崖抜可申候間只今残居候分者先堀残置可然段申上候ニ付御見聞被成候処尤成儀
ニ被思召上候ニ付其通ニ被仰付置候其御成就仕忠利公御巡見被成候節右之所之儀御
尋被成候ニ付英貴君右之通ニ被●上候若御用之節ハ御縄張之通何時ニ而も堀切を可申
段被●上候処忠利公尤ニ被思召上候御用之時ハ堀切土手を築キ可申間夫迄ハ英貴君
へ御預被成候段御意御座候ニ付英貴君半右衛門江其所直ニ御預被成候ニ付今以半右
衛門子孫支配仕来申候又後年四郎右衛門貞親君 実相院様と奉申候 御代綱利公 妙應院様
京町御茶屋ニ被為入候節御茶屋詠次口より野得御慰ニ御出被成候節も右之被堀残置候
訳合委ク被仰上候其後重而被為入候節之ために右三枚之内壱枚ハ道ニ被仰付其所ニ須
戸口を御明被成飾之様ニ出入不支候様被仰付候事
一、寛永十年正月元旦年頭之御規式御座候英貴君豊前已来御禮申上来候面々を被差出候
御家司葛西惣右衛門御鉄炮頭以下斎木菅沼半右衛門・生地久兵衛・長坂五郎兵衛・立川
四郎兵衛・岡部上田形右衛門・武藤十左衛門・中山半右衛門・斎木半助・木部清太夫・門
司喜左衛門 右之面々年始五節句御禮申上候事
一、忠利公御大國御拝領被成候ニ付而英貴君江三千五百石之御加禄を給る都合壱万八千
石又忠利公御意被成候ハ其方家ハ武蔵守已来長岡之称号を授来候へ共於當家ニ有吉
之名字者無隠旧臣なり将軍様ニもよく御存知なり先年内膳を大樹公御尋之節も長岡内膳
と申上候得ハ有吉たるかと上意ニ付有吉なる由を申上候ケ様之事も有之候ニ付時代押移
當家重代之名字なきが如くなるべし同ハ有吉の苗字相續可然候夫共ニ称号致度候ハゝ
いつとても勝手次第ニ可改儀心次第と御意致成候ニ付家筋之名字相續可仕旨御請被仰
上候事
一、寛永十四年八月藤崎八旛宮江忠利公・光利公 後光尚公真源院様と奉申候 御武運御長久の
ため英貴君松井佐渡殿被仰談ニ而神前ニ鉄之燈籠を御寄進被成り永ク神籠を被献依之
御代ニ御懈怠なく被献候又御祭礼ニ社僧等之乗馬かざり馬を被差出又後年鋒三本を御
寄進被成候事

















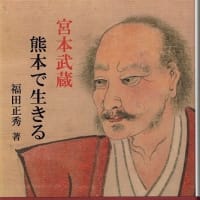







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます