ハンナ・アーレント『暴力について 共和国の危機』(みすず書房、原著1969年)を読む。
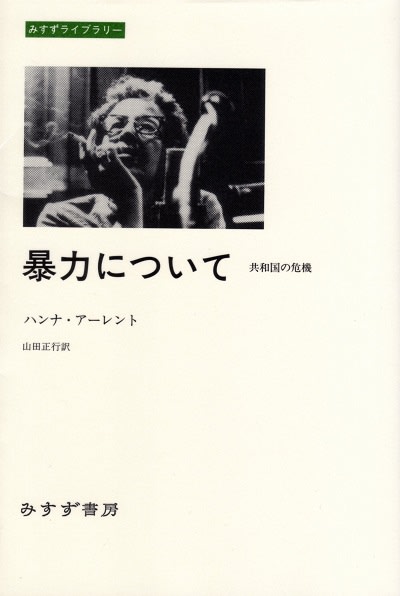
本書には、「政治における嘘」、「市民的不服従」、「暴力について」という3つの論考に加え、アーレントへのインタビューが収められている。書かれた時代には、1968年という全世界的な抵抗のピークがあり、市民は泥沼化したベトナム戦争によって国家に対する疑念を強め、ソ連軍によるプラハ侵攻・アフガン侵攻がイデオロギーの死を宣告していた。
そのような時代に、アーレントは、歪み肥大化した国家権力に対峙するものとして、単に個人の良心に基づく抵抗を位置づけることはしなかった。なぜなら、個人の良心は、人間の作り上げてきた社会の体系や規範に直接的に依存せず、場合によっては独善的で誤った価値判断になりうるからだ。アーレントが高く評価したのは、「アメリカ的」なる自発的・水平的な結社であり(「市民的不服従」)、これは、社会主義による硬直化した組織体系でも、資本主義によるピラミッドの体系でもない。「抵抗権」も、この文脈のなかに位置づけられるのだろう。
そうすると、いまの抵抗のかたちはどうとらえられるのだろう。もちろん有象無象に見えるのだが、少なくとも、インターネットの介在が、自発性・水平性の創出に貢献しているのだと見たいところだ(無邪気な考えだとしても)。
アーレントは、人間の知性による社会体系やルールを信じ、そのために、帝国自身のイメージごときに回帰しようとした非論理性(「政治における嘘」)にも、硬直化した政治参加のシステムにも、熾烈な批判を行った。「暴力」というものに関しては、権力を持たぬ者が行使すれば一瞬の成功やカタルシスはあってもやがて自滅を避けえないこと、また、権力を持つ者が行使するときはその権力を失いつつあるときであることを示した(「暴力について」)。
彼女の思考は丹念でいて、かつ、あちこちへと発散する。したがって、(「凡庸な悪」のようには)キーワード的な手がかりや現代の問題への処方箋は、簡単には得られない。だが、あちこちに手がかりがちりばめられていることも確かである。
まずは、次の至言をかみしめてみる。
「・・・権力のいかなる減退も暴力への公然の誘いであることは、われわれは知っているし、知っているべきである―――それがたとえ、政府であれ、被治者であれ、権力をもっていてその権力が自分の手から滑り落ちていくのを感じる者は、権力の代わりに暴力を使いたくなる誘惑に負けないのは困難であるのは昔からわかっているという理由だけからだとしても。」
●参照
マルガレーテ・フォン・トロッタ『ハンナ・アーレント』
仲正昌樹『今こそアーレントを読み直す』
高橋哲哉『記憶のエチカ』











