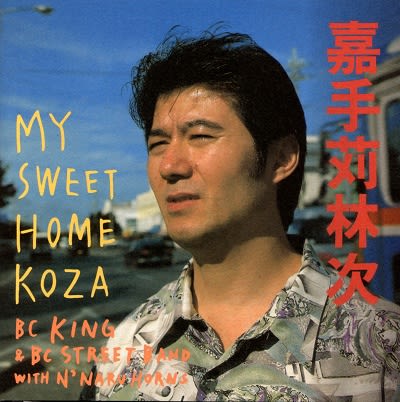何かの飲み会で隣に居合わせたことがきっかけで、坂手洋二さんから新作『8分間』の招待状をいただき、座・高円寺で観劇してきた。

杉並区、おそらく井の頭線のプラットフォーム(隣の駅が見えるとか言っているし)。鈍行の間隔は8分間。登場するのは、女性が車輌との隙間に足を挟まれ困っている。助けようとする人たち、痴漢だいや冤罪だともめる男女、香港民主化の運動家を装う男女、他人が目に入らぬような雰囲気でやってくる若い男、すぐにツイッターにアップする女子高生、ファンタジー小説の作家など。
ひとしきり騒動が終わって次の電車が来ると、また同じ時間に戻っている。そしてまた次も、その次も。8分間で繰り広げられることは、それぞれ微妙に異なっている。
この悪夢のなかから見えてくるものは、「今、ここで」に他ならないのだった。面白かった。なお、音楽は太田恵資さん。
終わってから、同じ回に観た編集者のSさんと古本屋を巡り、沖縄料理の「抱瓶」で飲み食い。

「抱瓶」の揚げにんにく