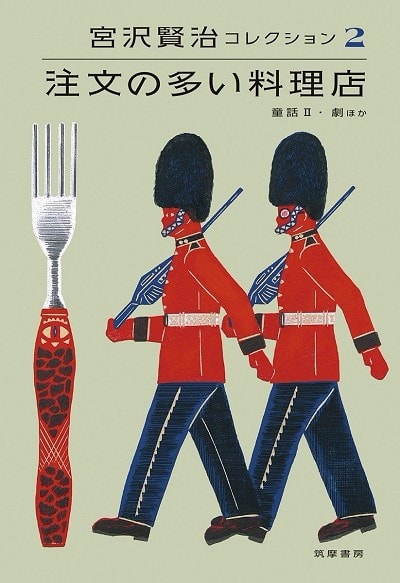寺下誠『Great Harvest』(テイチク、1978年)を聴く。

Makoto Terashita 寺下誠 (p)
Bob Berg (ts)
Errol Walters (b)
Jo Jones Jr. (ds)
Yoshiaki Masuo 増尾好秋 (g)
時代なのか、影響なのか、寺下さんのピアノはマッコイ・タイナーを思わせる。新宿ピットインにおいてエルヴィン・ジョーンズ・ジャズ・マシーンの一員として寺下さんが弾いたのを観たときも、そう思った。独特の和音を次々に重ねながら、熱く前に進むピアノである。
しかし、本盤を聴くと、それに加え、<日本>的なテイストを感じざるを得ない。余裕や懐の深さもあって、ついニッコリ。
わたしが過去に通っていた学校では、よく待合室で愉快な話をされていた(公園でサックスを練習している若者がいて、つい良いねえと声をかけちゃったよ、とか)。また、年に1回の発表会セッションでは、わたしが吹く後ろでピアノを弾いてくださった(自分が吹くのに精一杯でよく覚えていないが)。
ああ、ライヴに行きたくなった。