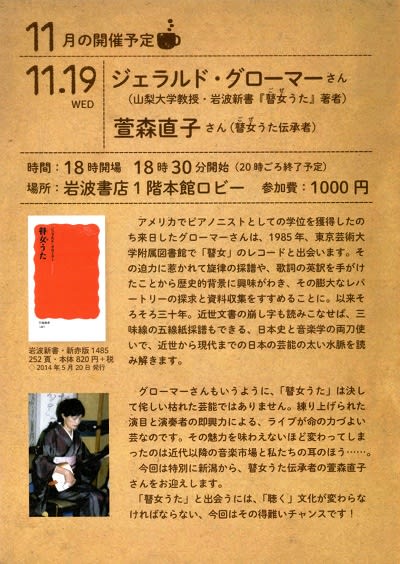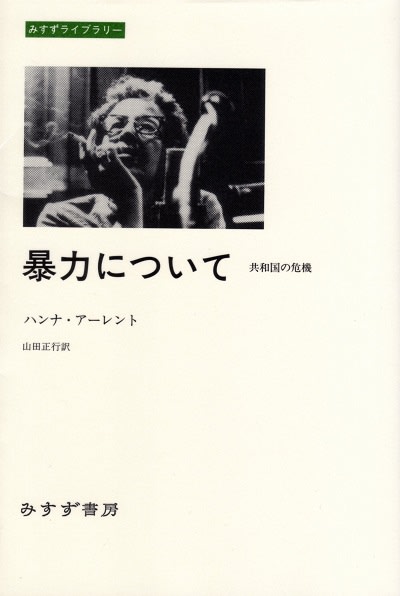ハンプトン・ホーズ『Live at the Jazz Showcase in Chicago Vol. 1』(Enja、1973年)

Hampton Hawes (p)
Cecil McBee (b)
Roy Haynes (ds)
1950年代のハンプトン・ホーズしか知らなかった。というより、興味が向いていなかった。レコード店の棚でこれを目にしたとき、少なからず驚いた。後年のプレイで「St. Thomas」などを弾いていることもあるが、なによりサイドメンである。
とくに、ホーズより結構年下のセシル・マクビー。このとき、まだインディア・ナビゲーションや同じエンヤからリーダー作を出す前だった筈だ。この名ベーシストが存在感を高めてゆく時期なのかな。
聴いてみると、ホーズのピアノは50年代とはずいぶん変わっているようだ。ホーズがこの数年後(1977年)に亡くなったあとに書かれた山下洋輔のエッセイに、「しばらく前にはビル・エバンスに学んだ形跡があった。そしていま、再び何事かをつかもうとしていた時期だったのかもしれない」とある。ただ、確かに抒情的な色もあるものの、分厚い和音、硬質な音、ブルースは50年代と同じとも思える。
マクビーのベースは期待以上に奮起。アタックが硬く、ぐいんぐいんと弦を唸らせながら音楽を駆動する。この人のベースを聴くと、なぜか、気泡がたくさん入っている金属の塊などを想像する。