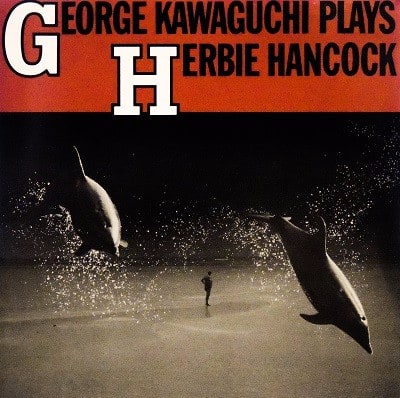早稲田松竹において、「沖縄返還から45年、映画のなかの沖縄」と銘打って、4本の映画を上映している。そのうち、東陽一の2本を観るために、朝から張り切って足を運んだ。なお他の2本は、大島渚『夏の妹』と高嶺剛『ウンタマギルー』。どちらも傑作ゆえ時間があれば再見したいところ。
東監督は、のちの2004年には『風音』を撮り、ふたたび沖縄を舞台としている。いずれも決して先鋭的とは言えないのだが、職人的で熱い想いは伝わってくる。この2本も見どころは少なくなかった。
■ 『沖縄列島』(1969年)

施政権返還前の沖縄をとらえたドキュメンタリーである。敢えてストーリーを意識しないつくりになっている。
コザでは、米兵におカネをもらえず激怒する売春婦。嘉手納空軍基地からは、ベトナムに向けてB52が爆音とともに離陸している。ダイバー3人は、原潜からの放射性物質を含んだ排水を浴びて体調を崩した。西原村(現・西原町)では、自民党の立てた候補をやぶり、革新系の村長が当選。
勝連半島の先にある平安座島には働き口がない。干潮のときに、砂糖黍の搬送のため本島との間でトラックが行き来するが、海水で1年でダメになる。ここと、隣の宮城島に、米国ガルフ・オイル社(のちにシェブロンに合併)が石油備蓄基地(CTS)を作る計画が出てきた。宮城島の人口は4,000人、だがCTSで雇用するという約束は300人、150人、100人とだんだん減ってゆく。関係者は、それでは受け入れられないと話す。(なお、CTS工事は翌年着工された。)
石垣島のパイン工場では、台湾の女工が多く働く。それは台湾よりも沖縄に働き口を求めてのことだが、それでも、給料は沖縄人よりも安い。そして伊江島では、阿波根昌鴻さんが登場する。
もちろん半世紀近く前のことゆえ現象も状況も異なるのだが、根っこの社会構造は変わっていない。驚きはない。
映画が終わった後に、東陽一監督が登壇し、あれこれとこの映画のことを話した。東さんは、基地問題や社会問題を形として描くのではなく、ひとりひとりを個人として見たかった。石垣のパイン工場における台湾女工を撮るとき、ニュース映像と何が違うのかと自問自答し、しゃがんでみた。そこには、女工が疲れて足をくの字にしている姿があった。のちに自主上映したとき、観客から、このシーンについて「もののあはれ」だと指摘され、仰天したのだという。
■ 『やさしいにっぽん人』(1971年)

前作と異なり劇映画である。
主人公(河原崎長一郎)は、記憶にはないものの、幼少時に渡嘉敷島においていわゆる「集団自決」を体験している。そのせいなのか、沖縄出身ゆえの他の理由があるからなのか、あるいは社会運動家にして神戸で狂死した謝花昇と同じ苗字を持つことが影響しているのか、「謝花」ではなく読み間違われがちな「シャカ」と名乗っている。かれは屈折し、警察官に理不尽に殴られようと、はっきりした態度をとることができない。それを見抜くような、恋人(緑魔子)。
ストーリーはあってなきがごとしだが、いわゆる「集団自決」については、その本質が強制集団死であることをしっかりと描いている。沖縄タイムスが『鉄の暴風』を発刊したのが1950年のことであり、その内容はすでに「本土」にも伝わっていたということか。
それにしても緑魔子が魅力的。トークショーでは、東監督は驚くべきことを明かした。女優を決めておらず、新宿の街場で見つけようと思い、ずっと観察していた。そして目の前でまさに相応しい人が通り過ぎたため、後をつけて(あぶない人)、彼女が入っていった劇場の事務所を訪ね、シナリオを渡してきた。それが緑魔子であり、後日、本人が電話をかけてきて「わたし、この映画に出ます」と断言したのだとか。
ところで、河原崎長一郎は、浦山桐郎『太陽の子』(1980年)にも主演している。やはり沖縄を主題にした映画だが、何か本人の中で連続するものはあったのかどうか。