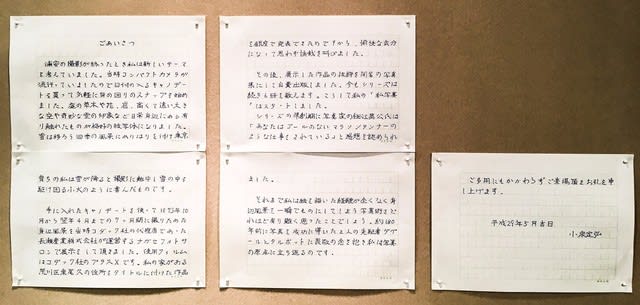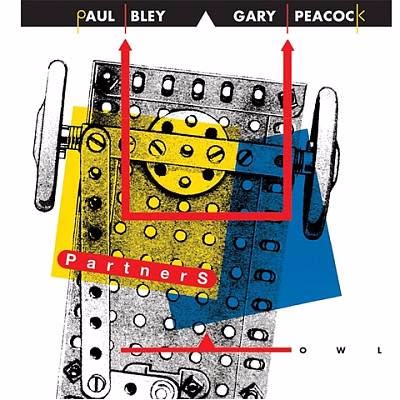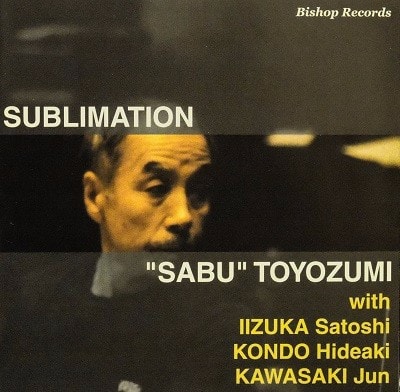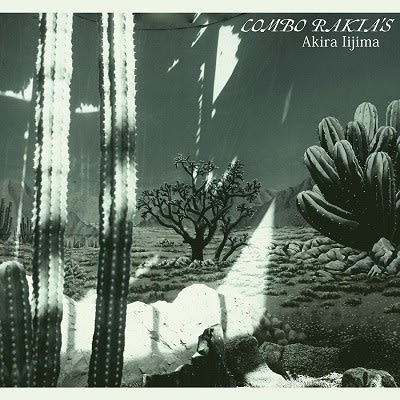ティム・バーン『The Sublime and. Science Fiction Live』(Thirsty Ear、2003年)を聴く。CD 2枚組。

Tom Rainey (ds)
Craig Taborn (rhodes, laptop, vitual org)
Marc Ducret (g)
Tim Berne (as)
もう、何ちゅうアルバムか。痺れるとはこのことだ。私的名盤認定。
アンサンブルはかなり精巧に組み立てられたようなものに思える。いっぷう変わった感じで各々の出番が回ってきて、精巧さというストーリーの中で各メンバーの野性味がいかんなく発揮されている。マルク・デュクレの火花のように炸裂するギターも良いし、職人的でもあるトム・レイニーのドラムスは見せ場が多い。クレイグ・テイボーンは、主役を奪ったときでも脇役のときでもスタイリッシュでカッコいい。
そして、奇妙で精巧な構造に追従したラインに、ティム・バーンのアルトが粘りつき、猛禽類のようにどこまでも飛び続ける。
●ティム・バーン
イングリッド・ラブロック UBATUBA@Cornelia Street Cafe(2015年)
イングリッド・ラブロック『ubatuba』(2014年)
ティム・バーン『You've Been Watching Me』(2014年)
ティム・バーン『Shadow Man』(2013年)
チェス・スミス『International Hoohah』(2012年)
ティム・バーン『Electric and Acoustic Hard Cell Live』(2004年)
ティム・バーン+マルク・デュクレ+トム・レイニー『Big Satan』(1996年)
ジョン・ゾーン『Spy vs. Spy』(1988年)
●トム・レイニー
イングリッド・ラブロック UBATUBA@Cornelia Street Cafe(2015年)
イングリッド・ラブロック『ubatuba』(2014年)
イングリッド・ラブロック+トム・レイニー『Buoyancy』(2014年)
イングリッド・ラブロック、メアリー・ハルヴァーソン、クリス・デイヴィス、マット・マネリ @The Stone(2014年)
イングリッド・ラブロック(Anti-House)『Roulette of the Cradle』(2014年)
トム・レイニー『Hotel Grief』(2013年)
トム・レイニー『Obbligato』(2013年)
イングリッド・ラブロック(Anti-House)『Strong Place』(2012年)
クリス・デイヴィス『Rye Eclipse』、『Capricorn Climber』(2007、2012年)
イングリッド・ラブロック『Zurich Concert』(2011年)
ティム・バーン『Electric and Acoustic Hard Cell Live』(2004年)
ティム・バーン+マルク・デュクレ+トム・レイニー『Big Satan』(1996年)
●マルク・デュクレ
ティム・バーン+マルク・デュクレ+トム・レイニー『Big Satan』(1996年)
クレイグ・テイボーン+イクエ・モリ『Highsmith』(2017年)
クレイグ・テイボーン『Daylight Ghosts』(2016年)
チェス・スミス『The Bell』(2015年)
クレイグ・テイボーン『Chants』(2013年)
クリス・ライトキャップ『Epicenter』(2013年)
クリス・ポッター『Imaginary Cities』(2013年)
『Rocket Science』(2012年)
デイヴ・ホランド『Prism』(2012年)
Farmers by Nature『Love and Ghosts』(2011年)
オッキュン・リーのTzadik盤2枚(2005、11年)
ロブ・ブラウン『Crown Trunk Root Funk』(2007年)
アイヴィン・オプスヴィーク『Overseas II』(2004年)
ティム・バーン『Electric and Acoustic Hard Cell Live』(2004年)
ロッテ・アンカー+クレイグ・テイボーン+ジェラルド・クリーヴァー『Triptych』(2003年)