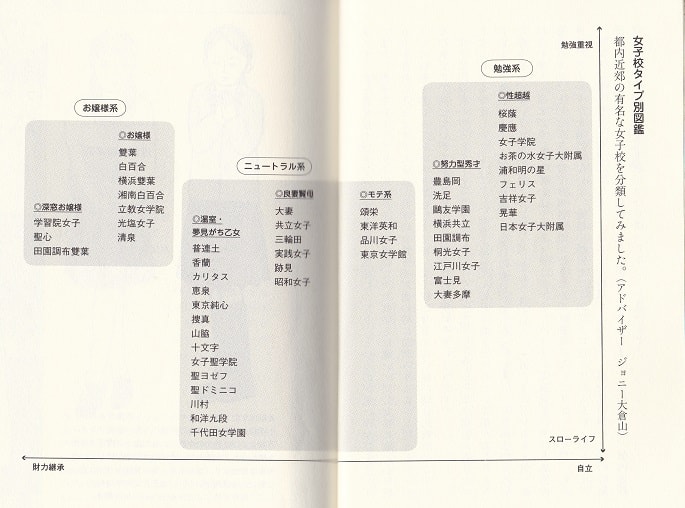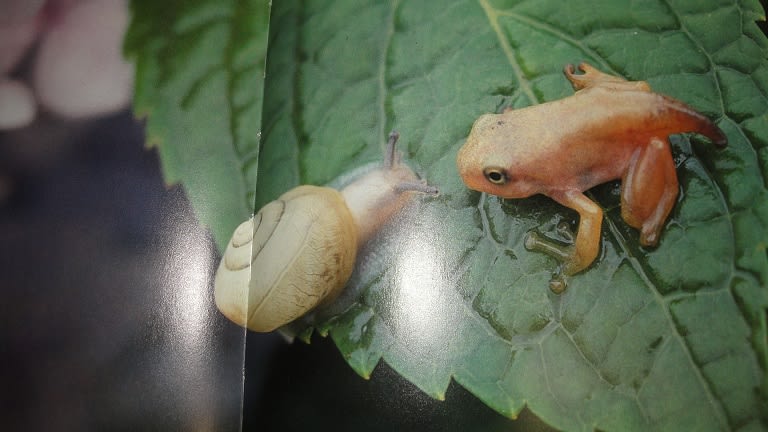「ピュリツァー賞受賞写真全記録」ハル・ビュエル
タイトルどおりの内容。
それぞれの写真に対して、丁寧な紹介文章と時代背景が説明されている。
これらを見ると、20世紀も21世紀も戦争と暴動、暴力の連続であったと思い知らされる。
ショッキングな写真も多数含まれているので、繊細な方はうなされるかもしれない。
なお、本書は日経ナショナルジオグラフィック社発行で、一般の書店では入手しずらいかもしれない。
私は図書館で借りた。

「爆撃からの逃走」 沢田教一 (c) Kyoichi Sawada(UPI)/Corbis 1965年撮影、66年
【参考リンク】
時代を象徴するピュリツァー賞受賞作品 70年の記録を写真集で振り返る
【ネット上の紹介】
アメリカで最も権威ある賞のひとつ、ピュリツァー賞。最初の受賞写真は、自動車工場でのストライキを写したものだった。その後70年間に受賞作が伝えたのは、ベトナム戦争、冷戦、アフリカの紛争、イラク、アフガニスタン、噴火、地震、津波。写真家が全身全霊をかけて切り取った1枚の写真に、時代のすべてが映し出されている。1942年の写真部門創設から、最新2011年の受賞写真までを収録。受賞写真を編年で紹介。撮影時の状況、写真への反響、写真家自身の証言、撮影機材や条件を記した撮影データ、背景を理解する助けに、同時代の出来事を付した。
[目次]
第1期 大判カメラと初期のピュリツァー賞受賞作品(1942年・デトロイトの労働争議(ミルトン・ブルックス);1943年・水を!(フランク・ノエル) ほか);第2期 カメラの小型化、ベトナム戦争と公民権運動(1962年・孤独な2人(ポール・パシス);1963年・革命と罪の赦し(ヘクター・ロンドン) ほか);第3期 新たな賞、特集写真部門の創設(1970年ニュース速報部門・キャンパスの銃(スティーブ・スター、AP通信);1970年特集部門・季節労働者の移動(ダラス・キニー) ほか);第4期 カラー写真、デジタル化、女性写真家、アフリカ(1981年ニュース速報部門・浜辺での処刑(ラリー・プライス);1981年特集部門・ジャクソン刑務所での生活(タロウ・ヤマサキ) ほか);第5期 デジタル革命(2003年ニュース速報部門・コロラドの山火事(ロッキー・マウンテン・ニューズ紙写真部スタッフ);2003年特集部門・エンリケの旅(ドン・バートレッティ) ほか)