都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
日本の古代史に登場する「卑弥呼(ひみこ)」といえば、邪馬台国(やまたいこく)の女王として君臨した日本最初の女帝ということになっています。では何故、女帝の名前に「卑」という文字が使われているのでしょう。
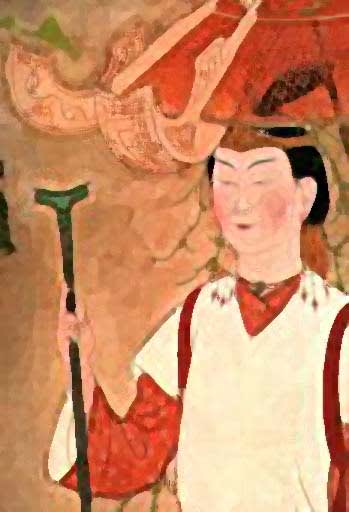 これは、もともと日本では、太陽や燃える火を「ヒ」というように、尊いもの、輝かしいものを表す音が「ヒ」だったからだといわれています。
これは、もともと日本では、太陽や燃える火を「ヒ」というように、尊いもの、輝かしいものを表す音が「ヒ」だったからだといわれています。
また、「卑弥呼」の「弥呼」は、もともと「人」という意味だったそうです。つまり、「卑弥呼」とは、「尊い人」ということなのです。
「卑弥呼」は固有名詞ではなく、「総理大臣」と同じような一般名詞ではなかったのかという説もあるそうです。
いずれにせよ、「卑」は必ずしも卑(いや)しいことではなかったようです。
卑弥呼(ひみこ、170年頃 - 248年頃)は、『魏志倭人伝』等の中国の史書に記されている倭国の王(女王)。邪馬台国に都をおいていたとされる。封号は親魏倭王。後継には親族の壹與が女王に即位したとされる。
本来の表記は「卑(上部の「ノ」が無い)彌呼」だそうです。
「魏志倭人伝」
卑彌呼 事鬼道 能惑衆
年已長大 無夫壻
有男弟佐治國
自爲王以來 少有見者
唯有男子一人給飮食 傳辭出入
居處宮室樓觀 城柵嚴設
卑彌呼死去 卑彌呼以死 大作冢 徑百余歩
狥葬者奴碑百餘人
卑弥呼は鬼道(妖術)で衆を惑わしていた
既に年長大であったが夫を持たず
弟がいて彼女を助けていた
王となってから後は、彼女を見た者は少なく
ただ一人の男子だけが飲食を給仕し、彼女のもとに出入りをしていた
宮室は楼観や城柵を厳しく設けていた
卑弥呼が死亡したときには、倭人は直径百余歩もある大きな塚を作り、
百余人を殉葬した
このような記述から、卑弥呼は邪馬台国の象徴としての存在で あり、日の巫女として神託を啓示するシャーマンとしての強大な存在であったとする説もあります。
「天照大神」は卑弥呼がモデルであるという説もあります。
したっけ。




















