都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
「食パン」といわれれば、誰でも想像できます。それはふつう4枚切りとか6枚切りとか8枚切りに最初からスライスされている、 四角い形のパンです。
当然、食べるものです。では何故、わざわざ『食』という字がついているのでしょうか。その理由は、諸説あるようです。
① 「菓子パン」と区別する説
 1874年、製パン会社の老舗の文英堂(現在の東京・銀座の木村屋総本店の前身)が、日本で初めてのアンパンを発売しました。饅頭をヒントに作ったそうですが、これが当時では爆発的な人気商品となり、パンといえば「菓子パン」というイメージが定着したそうです。
1874年、製パン会社の老舗の文英堂(現在の東京・銀座の木村屋総本店の前身)が、日本で初めてのアンパンを発売しました。饅頭をヒントに作ったそうですが、これが当時では爆発的な人気商品となり、パンといえば「菓子パン」というイメージが定着したそうです。
その後、パンの製造過程で使われる酵母の研究が盛んになり、1915年に国内で最初の乾燥酵母が開発されました。
更に発酵時間が速い酵母もアメリカから輸入されるようになり、米のご飯に代わる主食として、現在の食パンに近いパンが急速に広がっていったそうです。
そこでこうした食事用のパンを菓子パンと区別する為、「食パン」と呼ぶようになったそうです。
② 本食パン説
もともと「本食パン」と呼ばれていたため。
 第二次世界大戦より前のパン職人は食パンのことを、西洋料理の『もと』となる食べ物という意味で「本食」と呼び、イギリス系の白パン(山型食パン)のことをさしていました。
第二次世界大戦より前のパン職人は食パンのことを、西洋料理の『もと』となる食べ物という意味で「本食」と呼び、イギリス系の白パン(山型食パン)のことをさしていました。
③ 消しパンと区別する説
昔々、食パンはデッサンなどで消しゴムの代用品として使用されていた(ねり消し)。
その「消しパン」と食用のパンを区別するため。
④ 酵母説
酵母が食べて、パンが膨らむので「食パン」という。
⑤ フライパンと区別する説
台所に相存在するフライパンと食用のパンを区別するため。
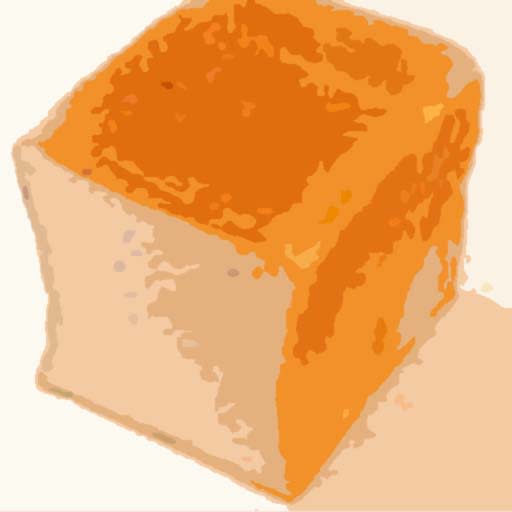 北海道では、一般的な「食パン」を全て「角食(かくしょく)」と呼んでいました。元々この呼称は、製パン業者間で使用される業界用語だそうです。断面が四角形の食パンを「角型食パン」といい、それを簡略化したものだそうです。因みに、断面の一辺が丸い山型を「山型食パン」、「山食(やましょく)」といいました。しかし、今では「角食」と呼ぶ人は殆どいません。
北海道では、一般的な「食パン」を全て「角食(かくしょく)」と呼んでいました。元々この呼称は、製パン業者間で使用される業界用語だそうです。断面が四角形の食パンを「角型食パン」といい、それを簡略化したものだそうです。因みに、断面の一辺が丸い山型を「山型食パン」、「山食(やましょく)」といいました。しかし、今では「角食」と呼ぶ人は殆どいません。
※「アンパン」については下記を参照ください。
したっけ。



















