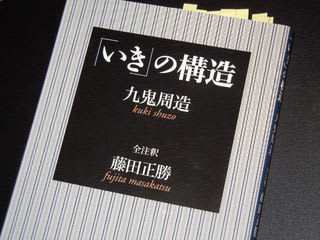198 塩尻市大門(塩尻駅の近く)の火の見櫓 111002
■ 櫓は上方に向かって直線的に絞り込まれている。櫓の部材はリベット接合されている。見張り台と比べて屋根が小さい。地味な姿を見て「どの形態も構造から生まれ、次第に芸術になった」という、以前建築関係の本で読んだ言葉を思い出した。避雷針には曲線状の飾り(頂華)がつけられている。

ブレースのリング式ターンバックルは肉厚で剛性が高そう。脚部は柱材相互を2本の横架材で繋いでいる。めずらしいデザイン。寄付をした人たちの名前を記したプレートが取り付けられている。
追記(160606):撤去されて今は無い。