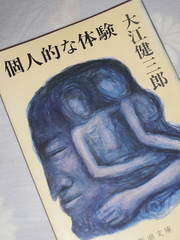

■ 『死者の奢り』『芽むしり仔撃ち』『見るまえに跳べ』『われらの時代』『遅れてきた青年』『性的人間』『個人的な体験』・・・。
ぼくが大江健三郎の初期の作品を読んだのは高校生の時だった。そう、あの頃は、ぼくのまわりの同期生の間で、安部公房と大江健三郎、このふたりの作家は人気があって、みんなよく読んでいた。読まなければならない作家のような感じだったようにも思う。上に挙げた初期の作品では、大江さんが描いた世界にすんなり入り込むことができた。『個人的な体験』を再読した時は子育て中だったこともあり、いや逆かな、子育て中だから再読したのかもしれない、縁遠い世界のことではないことで、共感したことを覚えている。
『万延元年のフットボール』も高校生の時に読んだ(随分昔のことだ 箱入の本で定価が490円)。大江健三郎の作品だから読まなきゃ、と義務感のように感じて読んだのではなかったか、と思う。
だが、この小説で描かれている世界に入りこむことができなくて、もちろん難しくて理解できなかったということが前提としてあるけれど、大江健三郎の世界に共感できないというか、全く自分にはかかわりのないことと感じて、それこそ義務感だけで字面を追ったということを覚えている。

大学生になってからも、大江作品は読み続けてはいた。『万延元年のフットボール』と同様に字面だけを追った作品もあったが。2020年の5月、もう大江作品を再読することはないだろうと、単行本だけ残して(写真)、何冊もあった文庫本はすべて古書店に引き取ってもらった。
なぜ、『万延元年のフットボール』はだめだったんだろう・・・。

『大江健三郎 江藤 淳 全対話』(中央公論新社2024年 図書館本)をえんぱーく内の塩尻市立図書館で借りて読んだ。この本には以下の通り、4つの対話、というか、対談が収録されている。
安保改定 われら若者は何をすべきか(1960年)
現代の文学者と社会(1965年)
現代をどう生きるか(1968年)
『漱石とその時代』をめぐって(1970年)
この中で興味深く読んだのは 「現代をどう生きるか」だ。この対談で『万延元年のフットボール』が取り上げられている。ここで、江藤さんが語っていたことによって、ぼくがこの作品に入り込めなかった理由(わけ)が分かった。
江藤さんはこの作品を徹底的に批判する。発言の一部だけ切り取るのはどうかと思うが、敢えてそうして載せる。以下、引用するのはどれも発言の一部。
**『個人的な体験』と今度の作品とを比べると、複雑なことをうまく重ね合わせてまとめているという点では技術的に今度のほうがすぐれているかもしれない。だけれど文学的には大江さんが以前『個人的な体験』で提出された主題が一歩も前進させられていないという印象を持った。**(71頁)
この発言を江藤さんは**技術的な進歩と文学的な足踏みというところに大江さんの現在の問題が集約されているように思う。**(72頁)と括っている。この発言に対し、当然大江さんは反論する。フェアではないが、その反論はここには載せない。このふたりに関心のある方には、この本をお薦めしたい。
**ぼくは、正直にいって何度もページを閉じながらある義務感からやっと読み通した。**(75頁)そうか、江藤さんもぼくと同じだったのか。江藤さんはこの発言に続けて**だからはっきりいえば、ぼくにとってあれは存在しなくてもいいような作品です。**(75頁)とまで言う。本人に向かってなんとも辛辣なことばだ。この対談で、ふたりは実に激しい論戦を繰り広げている。とにかく興味深く、そしておもしろい。ふたりとも決して逃げることなく、キッチリ論戦している。
**あなたの小説では呉鷹男とか蜜三郎とかいう奇妙な名前の人物が出てくるでしょう。この名前を認めるか認めないかがいわば読者に対する踏み絵になっているのです。**(80頁) ぼくは踏み絵とまでは思わないけれど、このような名前(鷹四、蜜三郎)に違和感というか、抵抗感をを覚えるというのは確かだ。
名前を認めた人間は大江さんの主観的な世界にコミットすることを強要されてしまう、と江藤さん。続けて**これは主観的・恣意的な世界をそれが本当に共用され得るかどうかという問題を回避して読者におしつけようとする一種の詐術です。**(80頁)
強要されるとまでは思わないけれど・・・、でもまあ、そういうことかもしれない。ぼくの理解力の無さを棚に上げていえば、難解な文章でがっちりガードして、それでも入り込んでくる読者に向けて書かれた小説ということではないのかな。これはぼくにとって都合の良い解釈か?
江藤さんの指摘に対して大江さんは**この小説を最後まで読んでこれを受けいれた人がいるということだと受けとっています。そしてそれは客観的に江藤さんが受けいれられないといわれる証言と少なくとも同じ重みを持つ証言じゃないでしょうか?**(82頁)と返す。
また、大江さんは次のようにも語る。**たしかにぼくは太郎や次郎から出発したわけじゃない、蜜三郎や鷹四から出発した。そうしてでき上った作品において、そういう名をもつ人物たちが普遍性を、いくらかなりとコミュニケートする力を読者に対して持てば、それは小説家として自分の作業が社会化したと考えることなんです。**(85頁)
**『万延元年』の最初の章であなたは非常に難解なイメージを出した。胡瓜を尻に突っこんで死んだ人を出したでしょう。あれは非常にわかりにくい鬼面人をおどろかす仕掛けです。いろいろな魂胆からあの小説を支持する人でも最後まで分からないといっているイメージ。**(115頁) (単行本を確認すると29頁にこのことが書かれていた。)江藤さんが指摘することをぼくも感じてしまう。
「現代をどう生きるか」で分かるのはふたりの文学観、文学の社会性についての考え方の相違だ。
江藤さんのことばを引用したい。**いまになって十年をふり返ってみると、あなたの客観世界との乖離というか外界の喪失という形でそれらをとらえるよりぼくにはとらえられない。**(83、4頁) この指摘がポイントだろう。
江藤さんは対談の成り行きもあって、大江さんに何のために小説を書くのかとまで問う。大江さんは**自分自身がどのように現実とかかわって生きているかということを小説に書くことによって確かめるために書いています。**(96頁)と答えている。正直なことばだと思うし、小説家として、当然の態度だと思う。読者に阿るようなことはするべきではない。
この対談を読んで、ぼくは思った。大江健三郎の内的世界、江藤 淳が指摘した外界を喪失した世界にぼくはついていけなかった、ということだろうな、と。どんどん難易度が上がる世界について行くことができないで、早々と脱落してしまったということだろう。



















