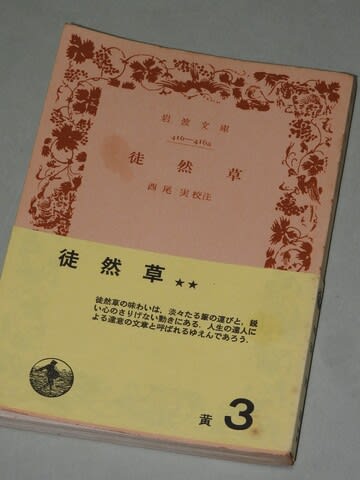
■ ぼくが持っている『徒然草』(岩波文庫)の奥付を見ると、昭和44年(1969年)6月10日 第52刷発行 となっている。読んだのは随分昔、55,6年も前のことだ。今も忘れずに覚えているのは第109段の高名の木のぼりの「かばかりになりては、飛び降るとも降りなん。如何にかく言ふぞ」ということば(表記はこの文庫87頁による)。油断大敵という教訓だと理解している。それから、仁和寺にある法師の教訓も内容は覚えている(過去ログ)。
『徒然草』に狛犬が出てくることも、いつごろからか知っていた(第236段)。
ある年の秋、聖海上人が大勢の人を誘って丹波の出雲神社を参拝した。**御前なる獅子・狛犬、背きて、後さまに立ちたりければ、上人いみじく感じて、「あなめでたや。この獅子のたちやう、いとめづらし。ふかき故あらん」と涙ぐみて(後略)** (168頁)
獅子・狛犬がお互い背を向けて据えられている様を見た上人は、「大変珍しい。これには深いわけがあるのだろう」と感激して涙ぐむ。同行者たちにそのことを伝えると、「これは都へのみやげ話にしよう」などと言っている。で、上人がものをよく知っていそうな神官に、このような据え方には由緒があるのでしょう。そのことについて、お聞かせ願えませんか、とお願いしたところ、「いたずらっ子たちが向きを変えてしまったんですよ」と言って、元のように据え直して行ってしまった、という話し。
ねずてつやさんが『狛犬学事始』(ナカニシヤ出版1994年初版1刷、2012年初版7刷)でこの狛犬を取り上げていた。塩見一仁さんの『狛犬誕生』(澪標2014年)でも取り上げられている。
ねずさんはこの段を描いた学習マンガを2冊、江渡大輔・園田光慶著『古典まんが徒然草』と『赤塚不二夫のまんが古典入門⑦徒然草』を取り上げ、どちらも参道狛犬の扱いで、描かれているのは台座に据えた石造の狛犬であることを紹介している。ぼくも図書館でマンガ日本の古典17の『徒然草』バロン吉本(中央公論新社)を見たけれど、やはり石造の参道狛犬が描かれていた。
神殿狛犬 京都の河合神社の境内社・貴布禰神社社殿 2015.12
『徒然草』の獅子・狛犬は上の写真のように神殿の縁に据えられた神殿狛犬と解さないといけない。
聖海上人たちが見た時は、いたずらっ子たちが右の獅子を右を向いた状態に、左の狛犬を左を向いた状態に据え替えてしまっていたというわけ。この据え方に由緒があるわけでもなんでもなく、単なる子どものいたずら。あちゃー、このことが分かったとき、上人はどうしただろう。
3冊のマンガには参道狛犬が描かれているが、石造の狛犬は(簡単には)動かせない。参道狛犬は江戸時代になってから普及し始めているようだ。『徒然草』が書かれたのは鎌倉時代末期ころとされている。その頃はまだ、参道狛犬は無かった、ということではないか。
「御前なる獅子・狛犬」と文中にある。御前は社殿の直前であって、仮に参道に設置されていたとすれば、御前ではなく別の表現をするだろう。また、神殿内に設置されているのなら、子どもたちのいたずらの対象にはならないだろう。神殿狛犬は木で作られたものが多い。大きさにもよるが、軽くて子どもたちにも動かせるし、神官が持ち上げてくるっと向きを変えることもできる。
漫画家も編集者も狛犬と聞いて、参道に設置された石造の狛犬しか浮かばなかったのだろう。確かに神社に詣でても、参道狛犬しか気がつかない、ということが普通だろうから・・。『徒然草』でも聖海上人に言われるまで、同行者は狛犬に気づいていなかったように。
赤塚不二夫が学習マンガに描いた狛犬の画像がありますが、掲載は控えます。ネット検索すればすぐ見つかります。
さて、本を読まなきゃ。



















