
『空海の風景 上下』司馬遼太郎(中公文庫2006年改版24刷(上)、2005年改版21刷(下))
■ 司馬遼太郎の作品は何作か読んだが、大半を処分した。この作品を処分しないで残したことに積極的な意味があるわけではない。ただし空海について書かれた本は今までに何冊か読んできた(過去ログ)。
上下両巻の本書紹介文を引く。**平安の巨人空海の思想と生涯、その時代風景を照射して、日本が生んだ最初の人類普遍の天才の実像に迫る。構想十余年、著者積年のテーマに挑む司馬文学の記念碑的大作。**
**大陸文明と日本文明の結びつきを達成した空海は、哲学宗教文学教育、医療施薬から土木潅漑建築まで、八面六腑の活躍を続ける。その死の謎をもふくめて描く完結篇。**昭和五十年度芸術院恩賜賞受賞
空海の起伏あれど幸運で充実した生涯について書かれたものは何作もあるが、司馬遼太郎の文体が好きな人はこの作品によって、空海について知ることも良いかもしれない。
ぼくも再読したい、って、この先、そんなにあれこれ読めるかなぁ(と常々思っている)。










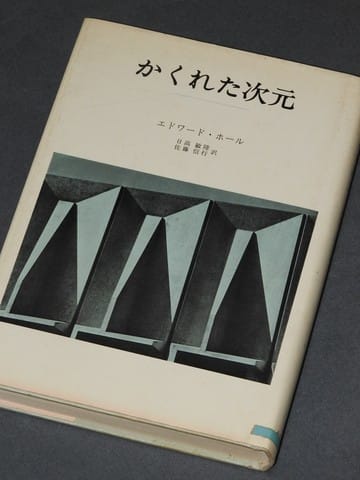 320
320