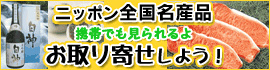【まくら】
貝原益軒は、女性に「七去(しっきょ)」というものがある、と言っている。このなかの一つでもあてはまれば、夫に追い出されてもしかたない、というのである。その一つが悋気つまり嫉妬であった。悋気すると夫を怨み妾を怒り、家の中が乱れて収まらないし、子孫繁栄の妨げになるからだ。『女大学宝箱』という本には、夫が浮気をしているなら静かにいさめるべきであって、恐ろしくすさまじく怒ったりしたらかえって夫にうとまれる、とある。『近世女大学』という本では、夫の気持ちを失わずに長く愛を保ちたいと思うなら絶対に嫉妬するな、書いている。江戸時代、悋気は「してはいけない」ものなのである。しかし、狂言の『身代座禅』や歌舞伎や落語や戯作では、女性の嫉妬が笑いのネタだった。そのすさまじさがかえって面白い、というわけだ。こちらのほうが健康である。
出典:TBS落語研究会
【あらすじ】
花川戸に橘屋さんという鼻緒問屋があった。ご主人が堅い人で女遊びをしたことが無いという。ある時、 寄合の後無理に誘われ吉原で遊んだ。こんな楽しいことが有ったのかと、今度は自分から通い始めた。でも、そこは商人、何か金がかからなくて遊べる工夫はないかと考え、親許身請けして根岸の里に妾宅を構える。
旦那様は最初本宅に20日、妾宅に10日お休みになった。本妻にこの事が分かり冷たくされ、何を言っても「フン!」と邪険にされるので、本宅に10日妾宅に20日と、逆になってしまう。そのうち帰らない月まで出てきた。
本妻は悋気に耐えきれず、あの女が居るからだと、藁人形に5寸釘で”カチーン”と杉の木に打ち付けた。それを聞いた根岸のお妾さんは「5寸釘で私を呪い殺すだと、それならこちらは6寸釘で」と、藁人形をカチ~ンと打ち付けた。それを聞いた本宅では許さない、「生意気だね!7寸釘を買っておいで」。7寸釘でカチ~ンと呪った。それを聞いたご妾宅では「悔しいね!」と8寸釘でカチ~ン。それを聞いた本宅では・・・。きりのないことで、 「人を祈らば穴二つ」の例え通り、ご本妻の一心が通じたものか、お妾さんがころっと亡くなった。同じ日にお妾さんの祈りが通じたものか本妻さんも亡くなった。こうなるとつまらないのは旦那さんで、葬儀を二つ出した。
初七日も済んだ頃、橘屋さんの蔵の脇から陰火が根岸に向かって飛んでいった。と、根岸から陰火がふあふあ~と飛んで、大音寺前で火の玉どうしが「カチーン」とぶつかる大騒動になった。
この一件がご主人の耳に入り、ご住持にお願いしたがお経ぐらいでは受け付けず、ご主人が一緒に行くことになる。「二人の火の玉に優しく語り聞かせ、心落ち着いたところで、有り難いお経を上げれば静まるだろう」と、大音寺前へ。
夜も更けると、根岸のご妾宅から陰火がふあふあ~と二人の前に飛んできた。話を語り聞かせて居ると、ご主人、たばこが飲みたくなるが火が無いので、お妾さんの火の玉を近くに呼んで、 たばこを付けて一服味わう。その内、本宅から上がった陰火が唸りを上げてものすごく、飛んできた。呼び止めるとぴたりと止まった。話し始めたが、また火が欲しくなり「こちらにおいで」とキセルを出すと、火の玉が”ツー”っとそれて、「私のじゃ、美味くないでしょ、フン!」。
出典:落語の舞台を歩く
【オチ・サゲ】
仕込落ち(落語のオチの醍醐味を最も味わえる、オチ。前半で、オチに対する伏線を含ませながら、噺を進め、後半に前半で仕込んだ複線を踏まえつつ、オチに向かう)
【噺の中の川柳・譬(たとえ)】
『悋気は女の慎むところ、疝気は男の苦しむところ』
『膝枕さして辺りを見ながらそっと水を含んで口移し』
『痣の付くほど抓っておくれそれを惚気の種にする』
『痣の付くほど抓ってみたが色が黒くてわからない』
『四十男の浮気と 七つ下がりの雨はやまぬ』(中年になってから覚えた放蕩は、若いときの放蕩と違ってなかなかやめられないということ。「七つ下がりの雨」とは午後四時過ぎに降り出した雨のことで、夕方降り出した雨は長く続きなかなか止まない。つまり、四十過ぎての道楽と七つ下がって降る雨は止みそうで止まぬということ)
『人を呪わば穴二つ』
【語句豆辞典】
【七去(しちきょ)】妻を離縁してよいとされた七つの理由。父母に従順でないこと、淫乱なこと、嫉妬すること、悪病のあること(悪疾)、子のないこと(無子)、おしゃべりなこと(多言)、盗みをすること(窃盗)。礼記の「大戴礼」にあらわれ、日本では江戸時代に女大学などの書物によって一般化した。離婚の際には三行半とも称される離別状が書かれた。
【親許(おやもと)身請(みう)け】身請けは遊女や芸妓を年の途中で金を払って足を洗わせることで、普通は馴染みがスポンサーになって金を出す。この場合の身請けは親がすること。または親に成り代わって身請けすること。
【根岸の里(台東区根岸)】江戸の別荘地として有名で、ご隠居さんやこの噺の様なお妾さんが小粋な造りの家に生んでいた。吉原の大店の主人達もここに住まいや別荘を持っていて、看板娘が病気で倒れるとここで療養させたりした。そのぐらい閑静で自然の景観が良かった。今、JR「鶯谷」駅が有る。その駅名からも当時の雰囲気が伝わってくる。
【この噺を得意とした落語家】
・八代目 桂 文楽
・五代目 三遊亭圓楽
【落語豆知識】
【明かり直し】高座の照明を徐々に落とすこと。



貝原益軒は、女性に「七去(しっきょ)」というものがある、と言っている。このなかの一つでもあてはまれば、夫に追い出されてもしかたない、というのである。その一つが悋気つまり嫉妬であった。悋気すると夫を怨み妾を怒り、家の中が乱れて収まらないし、子孫繁栄の妨げになるからだ。『女大学宝箱』という本には、夫が浮気をしているなら静かにいさめるべきであって、恐ろしくすさまじく怒ったりしたらかえって夫にうとまれる、とある。『近世女大学』という本では、夫の気持ちを失わずに長く愛を保ちたいと思うなら絶対に嫉妬するな、書いている。江戸時代、悋気は「してはいけない」ものなのである。しかし、狂言の『身代座禅』や歌舞伎や落語や戯作では、女性の嫉妬が笑いのネタだった。そのすさまじさがかえって面白い、というわけだ。こちらのほうが健康である。
出典:TBS落語研究会
【あらすじ】
花川戸に橘屋さんという鼻緒問屋があった。ご主人が堅い人で女遊びをしたことが無いという。ある時、 寄合の後無理に誘われ吉原で遊んだ。こんな楽しいことが有ったのかと、今度は自分から通い始めた。でも、そこは商人、何か金がかからなくて遊べる工夫はないかと考え、親許身請けして根岸の里に妾宅を構える。
旦那様は最初本宅に20日、妾宅に10日お休みになった。本妻にこの事が分かり冷たくされ、何を言っても「フン!」と邪険にされるので、本宅に10日妾宅に20日と、逆になってしまう。そのうち帰らない月まで出てきた。
本妻は悋気に耐えきれず、あの女が居るからだと、藁人形に5寸釘で”カチーン”と杉の木に打ち付けた。それを聞いた根岸のお妾さんは「5寸釘で私を呪い殺すだと、それならこちらは6寸釘で」と、藁人形をカチ~ンと打ち付けた。それを聞いた本宅では許さない、「生意気だね!7寸釘を買っておいで」。7寸釘でカチ~ンと呪った。それを聞いたご妾宅では「悔しいね!」と8寸釘でカチ~ン。それを聞いた本宅では・・・。きりのないことで、 「人を祈らば穴二つ」の例え通り、ご本妻の一心が通じたものか、お妾さんがころっと亡くなった。同じ日にお妾さんの祈りが通じたものか本妻さんも亡くなった。こうなるとつまらないのは旦那さんで、葬儀を二つ出した。
初七日も済んだ頃、橘屋さんの蔵の脇から陰火が根岸に向かって飛んでいった。と、根岸から陰火がふあふあ~と飛んで、大音寺前で火の玉どうしが「カチーン」とぶつかる大騒動になった。
この一件がご主人の耳に入り、ご住持にお願いしたがお経ぐらいでは受け付けず、ご主人が一緒に行くことになる。「二人の火の玉に優しく語り聞かせ、心落ち着いたところで、有り難いお経を上げれば静まるだろう」と、大音寺前へ。
夜も更けると、根岸のご妾宅から陰火がふあふあ~と二人の前に飛んできた。話を語り聞かせて居ると、ご主人、たばこが飲みたくなるが火が無いので、お妾さんの火の玉を近くに呼んで、 たばこを付けて一服味わう。その内、本宅から上がった陰火が唸りを上げてものすごく、飛んできた。呼び止めるとぴたりと止まった。話し始めたが、また火が欲しくなり「こちらにおいで」とキセルを出すと、火の玉が”ツー”っとそれて、「私のじゃ、美味くないでしょ、フン!」。
出典:落語の舞台を歩く
【オチ・サゲ】
仕込落ち(落語のオチの醍醐味を最も味わえる、オチ。前半で、オチに対する伏線を含ませながら、噺を進め、後半に前半で仕込んだ複線を踏まえつつ、オチに向かう)
【噺の中の川柳・譬(たとえ)】
『悋気は女の慎むところ、疝気は男の苦しむところ』
『膝枕さして辺りを見ながらそっと水を含んで口移し』
『痣の付くほど抓っておくれそれを惚気の種にする』
『痣の付くほど抓ってみたが色が黒くてわからない』
『四十男の浮気と 七つ下がりの雨はやまぬ』(中年になってから覚えた放蕩は、若いときの放蕩と違ってなかなかやめられないということ。「七つ下がりの雨」とは午後四時過ぎに降り出した雨のことで、夕方降り出した雨は長く続きなかなか止まない。つまり、四十過ぎての道楽と七つ下がって降る雨は止みそうで止まぬということ)
『人を呪わば穴二つ』
【語句豆辞典】
【七去(しちきょ)】妻を離縁してよいとされた七つの理由。父母に従順でないこと、淫乱なこと、嫉妬すること、悪病のあること(悪疾)、子のないこと(無子)、おしゃべりなこと(多言)、盗みをすること(窃盗)。礼記の「大戴礼」にあらわれ、日本では江戸時代に女大学などの書物によって一般化した。離婚の際には三行半とも称される離別状が書かれた。
【親許(おやもと)身請(みう)け】身請けは遊女や芸妓を年の途中で金を払って足を洗わせることで、普通は馴染みがスポンサーになって金を出す。この場合の身請けは親がすること。または親に成り代わって身請けすること。
【根岸の里(台東区根岸)】江戸の別荘地として有名で、ご隠居さんやこの噺の様なお妾さんが小粋な造りの家に生んでいた。吉原の大店の主人達もここに住まいや別荘を持っていて、看板娘が病気で倒れるとここで療養させたりした。そのぐらい閑静で自然の景観が良かった。今、JR「鶯谷」駅が有る。その駅名からも当時の雰囲気が伝わってくる。
【この噺を得意とした落語家】
・八代目 桂 文楽
・五代目 三遊亭圓楽
【落語豆知識】
【明かり直し】高座の照明を徐々に落とすこと。