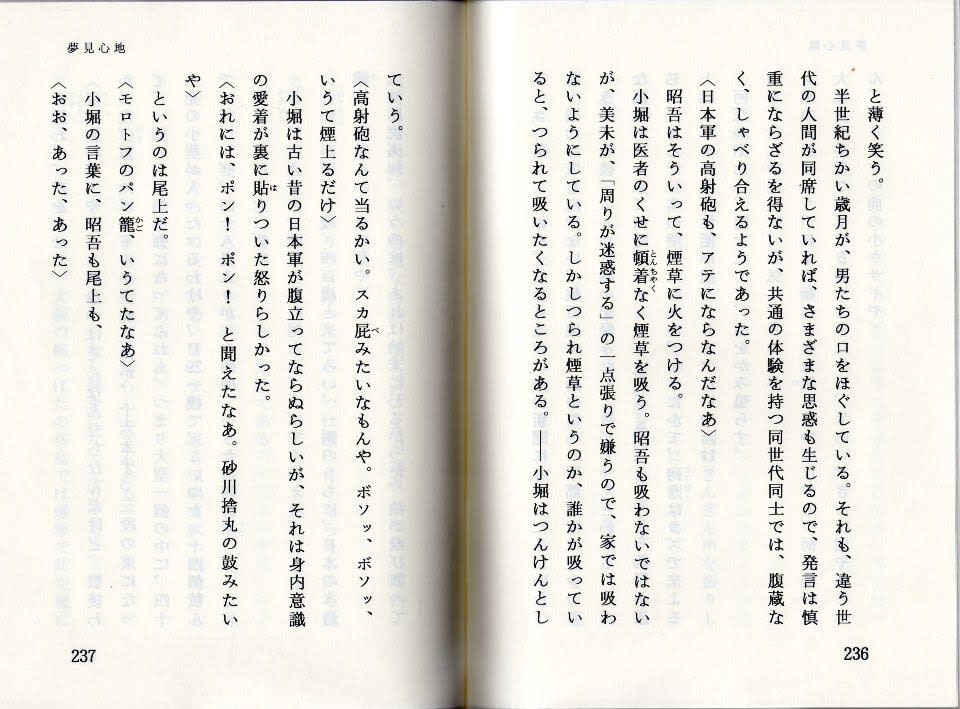本の概要 サイトから引用
ラヴ・ロマンスの作家、妻の美未は、海外義援の会に出かけ、生意気ざかりの娘は、自室へ引き上げた。昭吾は一人水割りを手に、思いに浸る。あのとき、日本も戦場だった。―昭和二十年八月、B29の大編隊が大阪を襲い、昭吾は、爆弾と火炎の地獄の中を、あぐりを守って逃げまどった。清い少年と少女の日々。
第二次世界大戦中にB29の爆撃の中逃げた昭吾と、当時まだ2歳だった美未。夫の昭吾には、売れっ子のラブ・ロマンス作家となった妻の美未には口にしない、戦時中の熱い恋の思い出があった。一緒に爆撃から逃げ、結婚まで望みながらもそれが叶わなかっ たその相手――あぐりへの思いが、戦時中の景色と共に蘇る。
以下の4ページはそれぞれ本文中の別々のシーンから引用
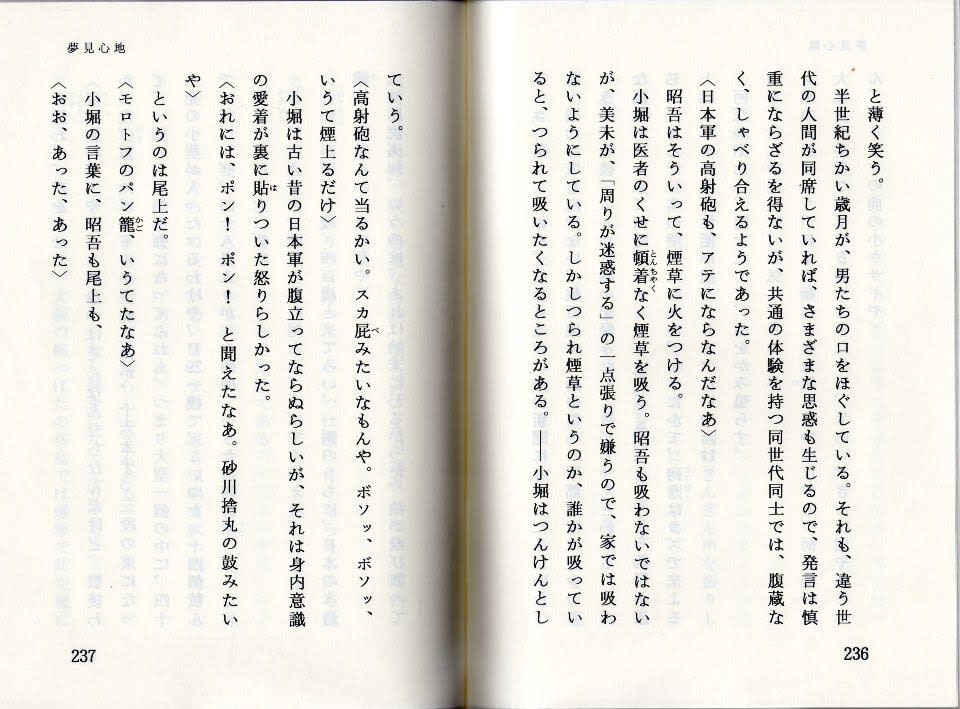



私が心の支えにしている、ある女性の言葉がある。
彼女の名前は倉本あぐり。田辺聖子の『おかあさん疲れたよ』で出会った、魅力的な女性だ。田辺作品では必ず魅力的な女性が登場するが、あぐりは私の中でちょっと特別。
この作品は『言い寄る』三部作に代表される軽やかで鋭い恋愛小説とも、『ひねくれ一茶』『花衣ぬぐやまつわる…』のような評伝小説とも異なる。田辺聖子の戦後史であり、昭和史であり、王朝ロマンまで巻き込んだ大河恋愛小説でもある。それを一気に読ませてしまうのだから、その筆力たるや、ため息をついてしまう。
作品の主人公は、第二次世界大戦中に中学生だった昭吾と、2歳だった美未という夫婦。夫婦それぞれのラブロマンスが描かれる。あぐりは昭吾と同年で、共に戦火から逃げたこともある。終戦後、昭吾は結婚を望んだが、あぐりは大黒柱として母と弟一家を支えるため、自らの幸せをあきらめ、別れることを選んだ。そして40代になって二人は再会。あぐりは独身のまま家族を支えていた。逢瀬を楽しむ二人。が、あぐりは昭吾にとって妻と娘も大切だと知っているから、多くを求めない。一人で死ぬときの準備すら、密かにしている。そして昭吾に言うのだ。
「感嘆符が付かな、あかんねんわ。あたし、『運がよかった!』と思ってるわ、あたしの人生――」
「!!!!!」
感嘆符がつかなあかんかったのは、私の方だった。ちょっと、そこの私! 私大変とか思ってる場合じゃない! なにかのせいにしている場合じゃない!!! 被害妄想のまったくない、でも自虐的でもないこの言葉は、以降、大きな落ち込み(大失敗したとか)の時も小さな落ち込み(バスを乗り過ごしたとか)の時も私の中で蘇る。そして様々な意味で「運がいい」と思い直して前に歩かせてもらっている。
「戦時中にちょうど娘ざかりだった若い女性たちは、戦後、過酷な運命に待たれていた。(中略)同世代の私は、可憐な彼女たちから目を離すことができなかった。彼女たちへの応援歌をうたいたかった――そしてまた空襲で逝った同世代の少年少女らへの鎮魂歌も――」
田辺さんはあとがきでこう書いている。
いま、私たちは未曾有の出来事に直面している。私自身、とっても不安にもなる。そんなとき、あぐりの生き方とこの言葉は、私をやさしく励まし、なぐさめてくれる。だから「いま」選ぶ「このイチ」に本作を選んだ。これは、極上のラブロマンスでありながら、すべての女性に「いま」も捧げる応援歌なのだ。
ちなみに田辺さんの小説は、17年くらい前、デザート編集部の緑川良子さんに渡されて読み始めた(もちろん、彼女が「このイチ!」に書いている『苺をつぶしながら』含めた『言い寄る』三部作)。素晴らしくて驚いた。そんな私がいつの間にか文庫出版部に異動し、田辺さんを担当させていただけたのだから、言葉通り「運がいい」と心から思っている。
(2011.06.15)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この本は図書館の「大活字本」シリーズで借りた。
田辺聖子さんと同世代の女性たちは義母の世代で、戦時中にちょうど娘ざかりだった若い女性たちは、戦後、過酷な運命に待たれていたとあるように
詩人の茨木のり子さんなどもそうだが 数年の生まれ年の差で送った人生の曲折がかなり違う。
田辺聖子さんは惜しくも昨年6月に亡くなられたが おそらく 日本の文学史に 太平洋戦争の一面を描いた作家としても残るだろう。