2019年7月28日任期満了実施参院選で
安倍自民党を大敗に追いつめれば
政権運営が行き詰まり
2019年10月1日の消費税10%への増税を
断念させる可能性が生じる
|
2001年から日本オリンピック委員会(JOC)会長に就任している竹田恒和が3月9日(2019年)午後、都内で行われたJOC理事会で今年6月の任期一杯で会長と理事を退任することを表明した。
理由はマスコミがこれまで伝えてきたように東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会(役目を果たして2014年1月解散)理事長時代の2013年7月と10月にこの招致委員会がシンガポールのコンサルタント会社に二度に亘って送金した約2億を超えるカネは東京五輪招致のコンサルタント契約を装った、実際は集票依頼の賄賂ではないかとの疑惑を持たれて、2016年1月にフランス検察当局が捜査を開始、本人も2018年12月に予審判事の事情聴取(自身は「ヒアリング」と言っている)受けるなどしていたが、フランスの裁判所は昨年12月に裁判を開くかどうかを審査する「予審手続き」に入り、さらに今年1月になって、仏検察当局は贈賄容疑で竹田恒和に対する正式捜査を開始したと伝えていることによる。
竹田恒和は昨年12月の予審手続き入りを受けて2019年1月15日に記者会見を開き、身の潔白を表明した。安倍晋三の森友学園疑惑・加計学園疑惑に関わる国会答弁と同様、竹田恒和にしても本人が自分の口で身の潔白を言っているに過ぎない。事実無根の証明とはならない。記者会見にしても、本人の釈明のみで、記者の質問を断って、7分で終了している。事実、潔白であるなら、どのような質問も恐れないはずである。この質問を断ったことが、フランスの捜査とは別に本人に対する疑惑を深めることになった。
2019年1月15日付の「NHK NEWS WEB」記事が記者会見の全文を伝えていた。
竹田恒和「おはようございます。竹田恒和でございます。皆様には、日頃からわが国のスポーツの振興、特にオリンピックムーブメントに多大なご理解とご協力を賜っておりますことを厚く御礼申し上げたいと思います。
またこのたびは、東京オリンピックパラリンピック競技大会に向けてご支援いただいている国民の皆様、スポーツ関係者の皆様、大会準備に携わっておられる組織委員会の皆様に大変ご心配おかけしており、申し訳なく思っております。
本日は、2014年までにすでに解散してしまった、東京2020オリンピックパラリンピック招致委員会、元理事長として会見をさせていただきます。改めまして、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。
本件は招致委員会とシンガポールのコンサルティング会社 ブラックタイディングス社と取り交わされた2つのコンサルタント業務に関するものであります。これら2つのコンサルタント契約は、通常の承認手続きに従い締結されたものであります。2つの契約に関する稟議書は通常の承認手続きを経て最後に回覧され、私が押印いたしました。私の前には既に数名が押印しておりました。
これらの契約内容はロビー活動および関連する情報を収集するコンサルタント業務の委託になります。これらの契約につき、私は国会の衆参両院の予算委員会をはじめとする各委員会に呼ばれ、私は招致委員会元理事長の立場で参考人として説明をいたしました。質疑に対応するため、私は実務の詳細につき国および都から派遣された招致委員会当時の職員などに実態を確認し、報告をさせていただきました。
招致委員会事務局は主として国と都から多くの人材を派遣いただいて、オールジャパン体制で業務を行っておりました。国会においてはその後、本件に対してさらなる追及はありません。さらにJOCは第三者により、外部の弁護士、公認会計士による調査チームを設置し、延べ37名の関係者を対象に私が署名に至った経緯につき綿密なヒアリング調査を行いました。調査報告書はブラックタイディングス社とのコンサルタント契約は適正な承認手続きを経て締結されたものと確認しております。
承認手続きにおいて担当者が取り引きの概要説明を記載した書面の稟議書を起案し、この上司が順次承認したうえで、理事長であった私に承認を求めるものであります。私自身はブラックタイディングス社との契約に関し、いかなる意思決定プロセスにも関与しておりません。私には本件に関与していた人々や本件の承認手続きを疑うべき理由はありませんでした。
調査報告書は招致委員会からブラックタイディングス社への支払いはコンサルタント業務に対する適切な対価であったと結論づけております。また付け加えますと、調査報告書では私がブラックタイディングス社と国際陸上競技連盟会長、およびその息子がいかなる関係があったことも知らなかったことを確認いたしました。また調査報告書は、ブラックタイディングス社との契約締結に日本法において違法性はないと結論づけました。
この調査報告書は2016年9月に発表され、それ以降さらなる調査は行われておりません。2017年初旬にはフランスの要請を受けた東京地検にも協力し、すべての質問に対し回答をいたしました。東京地検では何らの手続きも行われていません。そ
の後、フランス当局の要請により、(2018年)12月10日にパリでヒアリングを受けてまいりました。
そこですべての質疑に応答し、みずからの潔白を説明いたしました。現時点、私の心境といたしましては、この騒動により2020年東京オリンピックパラリンピック開催に向け、着実で順調な準備に尽力されている皆様、組織委員会、オリンピックムーブメントに対し影響を与えかねない状況となってしまったことにつき、大変申し訳なく思っております。
また、信頼するスタッフたちが一丸となって熱い思いを持って取り組んでいたのは紛れもない事実であり、その支えがあったからこそ、この東京招致が実現できたものと確信しております。この場をお借りして改めて当時のスタッフを誇りに思うとともに、皆様に感謝を申し上げたいと思います。
今後、私は現在調査中の本件について、フランス当局と全面的に協力することを通じて、みずから潔白を証明すべく全力を尽くしてまいります。以上であります。
|
カネを使って東京都に投票をお願いする行為はあくまでも裏取引に所属する不正であって、係の者が案を作成、関係者に回して承認を求める会議開催手間省略の稟議書に不正を正直に書くはずもなく、にも関わらず、「承認手続きにおいて担当者が取り引きの概要説明を記載した書面の稟議書を起案し、この上司が順次承認したうえで、理事長であった私に承認を求めるもので」あることを以って不正がなかったことの証明にしようとする。
例え不正に関わった人間が作成した稟議書であったとしても、そこに裏取引の経緯や成果を記すはずもない。証明にならない事務手続きを持ち出さざるを得ないこと自体が限りなく状況証拠をクロに近づけている。JOC設置の外部第三者調査チームが「コンサルタント契約は適正な承認手続きを経て締結されたものと確認した」と、この「確認」をも事実無根・シロの根拠にしているが、この根拠にしても、仏検察当局が贈賄容疑で竹田恒和に対する正式捜査を開始したことに対しては何ら役に立ってはいなかったことになる。
当然、2018年12月10日にパリでフランス当局から事情聴取を受けた際の自らの身の潔白の訴えにしても、相手に聞く耳を持たせることはできなかった。そのような訴えとは裏腹にシロであることの証明とはならないことを証明としている矛盾の追及を恐れて、記者に対する質疑の時間を設けることはせず、言いっ放しで記者会見を打ち切ることにしたのだろう。繰返しになるが、事実、潔白であるなら、どのような質問も恐れることはない。
竹田恒和は「これらの契約につき、私は国会の衆参両院の予算委員会をはじめとする各委員会に呼ばれ、私は招致委員会元理事長の立場で参考人として説明をいたしました」と言っているが、参考人招致をされた国会での質疑を取り上げてみる。安倍晋三と同じで必要ないことを長々と喋って、無実の証明に必要となる発言やあるはずの契約書等の物的証拠は一切示さなかった。ムダな発言が多いから、読み飛ばしたとしても、無実の証明とならない理由は短い言葉で片付くゆえに、その理由さえ目を通して貰えば、片付くはずだ。
2016年5月16日衆院予算委員会
玉木雄一郎「2020年東京オリンピックの招致をめぐる買収疑惑であります。
私も2020年東京オリンピック・パラリンピックの成功を祈る一人でありますが、このオリンピックに関しては、新国立競技場の建設計画の見直し問題、またエンブレムの見直し問題、また、新しい国立競技場には聖火台がない、こういった問題、さまざまな問題がこれまでも取り上げられてきましたが、今回の問題は極めて私は深刻であると思っています。
資料1をごらんください。
そもそも、これは一部の報道ではなくて、フランスの検察当局が公式にこの件に関して捜査を行っている旨を5月12日に発表しております。また、ガーディアンというイギリスの新聞を初め、海外の各紙メディアもこれを報道しております。まさに日本の名誉にかかわる問題だと思っています。
資料2をごらんください。事案の概要、これはそのガーディアン紙の報道の表をそのまま持ってきましたけれども、少し複雑なので順を追って説明します。
この一番上にあるラミン・ディアクさんという国際陸連の会長さんがいます。彼はあわせて、IOC、国際オリンピック委員会の投票権を持つ委員でもありました。今回報じられている疑惑は、この国際陸連の前会長であるラミン・ディアクさんの息子さん、パパマッサタ・ディアクさん、英語ではクロースフレンドと書いていますが、親友とされるイアン・タン・トン・ハン氏、このタン氏の経営する会社の口座、これはブラック・タイディングス社といってシンガポールにあると言われていますが、この口座に日本の招致委員会から多額のお金が送金をされ、そしてそのお金が招致にかかわるIOCの委員の買収と、そしてまた成功報酬として使われたのではないか、こういう疑惑であります。
そこで、まず総理にお伺いします。
先週の本会議で、同僚議員の福島議員からの質問に対して、本件に関して、早急に東京都及びJOC、日本オリンピック委員会、ここに確認をし、調査するなど事実関係の把握に努めると総理は明言されましたけれども、その後の調査結果はどうなっていますか」
安倍晋三「詳細については文科大臣から答弁をさせたいと思いますが、御指摘の件については、招致委員会の理事長であったJOC竹田会長が先週ステートメントを私の答弁の後発表し、正式な業務契約に基づく対価として支払いを行ったとの見解を示したと承知をしています。
当時の招致活動の具体的な内容については、招致委員会の主体となっていたJOCと東京都が説明責任を果たしていくべきものであり、政府としても、スポーツ庁を中心に、引き続き事実関係の把握に努めてまいりたいと思います」
玉木雄一郎「資料1をごらんください。
総理、これは危機感と緊張感が少し少ないのかなと思うので、改めてこれを見ていただきたいんです。
フランス検察当局も文書の中に書いていますが、これはなぜ問題かということは、フランス当局が、短いステートメントですけれども、その中に幾つかの要素を書いています。一番大事なポイントは何かというと、金銭の送金、授受が、皆さんも、全国の皆さんも大変感動したと思いますが、2013年9月のあの感動的な、東京に開催地が決まった9月、この9月を挟んで前後に2回、合計2億円を超えるお金が、先ほど申し上げたシンガポールのブラック・タイディングス社に送金されているということです。
この時期的な近接、つまり、開催決定の2カ月前に約1億円がまず振り込まれ、そして開催が決定した次の月に残りの1・3億円が振り込まれている。この決定にかかわる極めて近接した時期に多額の資金が移動していることについて、フランス当局は、それを捜査を始める一つの理由と掲げて、このステートメントを発表しているわけであります。
改めてお伺いします。この送金については、フランス当局やあるいは外国のメディアが報道しているような疑惑は一切ないと、これは自信を持ってお答えになりますか。総理、改めて」
文科相馳浩「報道がありましてから私も大変びっくりいたしまして、事実関係については、招致委員会、しかしながら当時の招致委員会はもう解散しておりますので、そこの理事長であった竹田さん、JOCの今は会長でございますけれども、その方々、また、スポーツ庁としては、何か大変重大な事案ではないかということで、当時の担当しておられた水野さんと、また招致委員会事務局の樋口さん、この方々に直接お会いをして確認をし、そして、当面いただいている情報について今からお伝えしたいと思いますし、きょうは参考人としても竹田さんをお呼びでありますので、ぜひ事実関係をお聞きしていただきたいと思います。
実は、私も、当時8月に招致の最終段階に入りまして、一番最終的な票読み、またそのための情報収集、どのような方にどのように働きかけをした方が最終的に票を獲得できるかということで、モスクワの世界陸上選手権、ここの方に私も参りました。
と同時に招致委員会においても、ここが大きな山場だと。このときの時点において、御記憶にあると思いますが、大変日本は厳しい状況にありました。理由は、汚染水の問題であります。私も、7月、8月とこの問題について官邸ともかけ合いながら走り回ったことを記憶しておりますが、そのときに、最終的に、コンサル会社と調整をした上で、適切な情報を踏まえて対処しなければいけないという判断をされたようですが、その際に、自薦、他薦、あまたのコンサル会社がどうですかと言ってくる中で、十分に対応するためにも、招致委員会のメンバーはコンサル業務に関してはプロではありませんので、電通に確認をしたそうであります。そうしたら、電通の方から、こういう実績のある会社としてはこの会社はいかがでしょうかということの薦めもあって、しかしながら、最終的には、招致委員会の方において判断をされて、この会社と契約をされたということがまず一点目であります。
ただ、その契約のときに、契約交渉の中で、コンサル料を払わなければいけませんが、残念ながら、向こうから指定された金額を、当時、招致委員会は財政的に厳しい状況で、持っていなかったそうです。したがって、まず払うべき金額を払い、また、この後、最終的に招致を成功させなければいけませんから、成功までの間のことも含めてその後また払いますというふうな状況で、契約を2回に分けた、こういうふうに報告を聞いております。
最終的には招致をかち取ることができて今日に至っているわけでありますが、8月の段階のモスクワでの世界陸上選手権、これに向けて、より強い、情報を収集し、対策を練る、そのための戦略を持つに当たって、必要なコンサル、そのコンサルが今回御指摘されている会社であった。
ただ、そのコンサルがラミン・ディアクさんと関係する会社であったということは、残念ながら、当時の招致委員会においては知る由もなかった、こういうふうな報告を受けております」
玉木雄一郎「電通からの推薦でお願いすることになったコンサルティング会社だということは分かりましたけれども、今大臣からもありました、きょうは、竹田会長、招致委員会の前理事長にもお越しをいただいておりますので、お伺いしたいと思います。
最初の振り込みが7月です。招致決定が9月です。2カ月間、実質働いたのは2カ月間だと思いますが、そこで2億円を超えるお金。具体的に、どういう情報収集をいただいて、どういう報告をもらって、どういう業務活動書のレポートを受けているのか。具体的に、どのような活動をして、どのような成果があったのかという、その報告はどのようなものを受けておられるのか、御説明をください」
竹田恒和「ただいま御指名いただきました日本オリンピック委員会、JOCの竹田でございます。
先生方には、日頃から我が国のスポーツ振興に多大な御支援、御協力を賜り、また、この8月に開催されますリオデジャネイロ・オリンピック大会、2020年の東京オリンピック大会に向けて多大な御支援をいただいていることを心から感謝申し上げたいと思います。また、大会の招致活動につきましても、皆様方には多大な御支援そして御協力をいただいたことを改めて御礼を申し上げたいと思います。
本日は、日本オリンピック委員会の会長の竹田でございますが、2020年東京大会の招致活動にかかわる問題でございますので、特定非営利活動法人東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会の元理事長として説明をさせて頂きたいと思います。
2020年の招致委員会は、2011年9月にJOCと東京都で立ち上げ、そして招致活動をスタートいたしました。同年12月には衆参両議院の招致決議、そして閣議了解をいただき、本格的活動となりました。
その活動に当たっては、民間資金の調達として、各界各層からの寄附、そして協賛金をベースとして、税金を一切使わないでこの活動を行ったということをまずお伝えしたいと思います。
また、オリンピック招致活動で海外コンサルの契約を結ぶことは、国際的に見ても極めて一般的でありまして、むしろ海外コンサル契約なしでは招致は成功しないとまで言われているほどであり、これは事実であると思っております。
今回、どのような契約が行われたかということを御説明申し上げたいと思います。
まず、経緯でありますが、先ほど馳大臣からもお話がございました。この各種大会イベントを行うに当たって、代理店あるいはコンサルというのは自薦、他薦、多くありますが、今回は本人から売り込みがありました。そして、株式会社電通さんにその実績を確認いたしましたところ、十分その業務ができる、そして実績があるということを伺い、事務局で判断したということを報告を受けております。特に、アジア、中東地域において活動実績が強いこと、この地域を中心とした活動に期待したところであります。
敗れた2016年の東京招致の際には今回の倍近い多数のコンサルを雇っておりましたが、残念ながら余り機能させることができなかったため、2020年には絞り込んで活動をいたしました。
招致活動最終段階においては、特に実績のあるコンサルタントを探しており、契約するに至ったと報告を受けております。特に陸上関係については影響力があると各方面からも聞き、PRすべき重点競技として考えていたところでございます。世界陸上協会の会長の親族が関係しているということは全く認識していなかったということを申し添えます。
このIAAF、世界陸上競技連盟とブラック・タイディングス社は業務の実績はあるということは伺っておりますが、ラミン・ディアク氏そしてその息子さんたちとこの会社が関係があるということは、全く我々は知る由もなかったということをお伝え申し上げます。
ただし、いずれにいたしましても、いずれのIOC委員あるいはその親族がブラック・タイディングス社との資本関係や役員として関係していないということを認識しております。IOC委員として、そしてその親族が、経営者ではなく、あくまで知人の範囲であれば問題はないということも認識しているところであります。
この会社の実績はいろいろございまして、決してペーパーカンパニーではございません。2015年の世界陸上北京大会の招致コンサルタント、マーケティング、2008年北京オリンピックのホスピタリティーサポート、博鰲アジアフォーラムの協力、そして二〇一二年イスタンブール世界室内陸上競技の大会等が挙げられます。
また、この契約の内容でありますが、先ほども御質問ありました。ブラック・タイディングス社との契約は、異なる業務内容で二つの契約を行い、それぞれの業務対価として二回にわたって支払ったものでございます。これは、招致委員会の正式な手続に基づき、そして契約を交わし、行ったものでございます。
この契約支払い行為につきましては、国際会計基準により、招致委員会にて適切な会計処理をし、新日本有限責任監査法人等により正式に監査を受けたものであり、そして、IOCにも決算報告をし、承認を受けたところでございます。
内容といたしましては、一回目は、最終段階に入った国際ロビー活動を効果的に、そして効率的に行うため、ロビー活動コミュニケーション戦略の確立、IOC委員の動向、周辺情報の収集、大会関係の情報収集などを業務といたしました。
国際関係のプロモーションは2013年の1月から解禁でありまして、ですから、一月から、実際この契約は7月でありますが、7月から9月までの最後の一番大事なときに契約をしたわけでございます。
二回目の、招致決定後のIOC総会や東京招致の要因についての情報収集、分析を委託し、招致に関する報告や今後の活動などのために基礎資料とすべく業務をしたものでございます。
ここで、よろしいですか。(玉木委員「簡潔にお願いします。時間がないので」と呼ぶ)はい、分かりました。
まず、業務内容ですけれども、そして、成果物のことについてお話し申し上げます。
当該業務の成果物はロビー活動そのものであり、アポイントメントの実施や業務報告、情報分析などの有形無形の各種報告が成果であります。これらの成果は、最終段階までの情報収集と効果的なロビー活動の詰めに大いに役立ったものであり、まさに最後の票読みと票獲得には欠かせないものであったというふうに確信をいたしております。
招致活動の特殊性とその契約の実態について少し御説明をさせていただきたいと思います。
招致決定の1カ月前、2013年8月10日から18日まで開催されましたIAAF世界陸上選手権ですが、同時にIOCの理事会が行われました。30名以上のIOC委員が来ることが分かっておりました。
2016年のオリンピック・パラリンピック招致のときにも、2009年ベルリンで行われました同選手権が招致の決定1カ月前に開催されました。その決戦の場であり、そこでの活動が十分でなかったということが敗因の一つとなっておりました。
2020年の招致では同じ失敗は許されず、モスクワの世界陸上の選手権で、活動は決戦の場であり、そのための招致戦術を策定すべく、2013年4月から6月にかけて全力で取り組んでおりました。しかし、世界陸上の関係者へのアプローチの点での人脈が脆弱であるとの結論に至ったわけであります。
そこで、事前アプローチを受けていた数名のコンサルタントのうち、国際競技連盟大会に……」(玉木委員「質問ができないです」と呼ぶ)
委員長竹下亘「竹田会長、申しわけございません、時間が迫っておりますので、手短にお願いをいたします」
竹田恒和「はい、わかりました。
まず、招致決定した際の収入の確保状況も踏まえて、そして成功報酬的な意味合いもある、新たな追加業務委託もあるということを話し合ったということも聞いておりました。
そして、結果として、2013年9月7日、ブエノスアイレスのIOC総会で東京決定を受け、日本国内で盛り上がりも大きく、日本国民の全体に活気をもたらすことができたと思っております」
玉木雄一郎「いろいろ今説明いただきましたけれども、私の質問には答えて頂いておりません。
どういう結果が成果物、有形無形のというふうに言いましたけれども、では、文書として、この二億円を超えるものに対する対価として何らかの報告書はあるんですかないんですか、この点についてはもう一度お答えいただきたいのと、ちょっと資料3を見てください。
実績の大変あるブラック・タイディングス社ということで、例えば2015年の北京国際陸上などを招致した実績があるというふうにありましたけれども、これは一部欧米のメディア、日本のメディアも報じていますし、私もグーグルアース等で住所を確認すると同じところが出てきますけれども、アパートの一室で、しかも、今は会社がもうないということです。
このもとになる、世界反ドーピング機構の独立委員会の報告書の中に一番最初にこの東京招致についての疑惑が出てくるんですが、実はそこにもこのブラック・タイディングス社の口座というのが出てくるんですね。ロシアのマラソンランナーのドーピングのもみ消しに失敗したので、そのお金をリファンド、うまくいかなかったので、戻すときの口座にここが使われているんです。
そこの報告書の中の注書きにおもしろい記述を見つけました。このブラック・タイディングスというのは、英語をそのまま訳すと黒い文書とか情報とか通知ということだと思いますが、そのヒンディー語は、黒い金を洗浄するという意味だそうです。
これはペーパーカンパニーではないと今お話がありましたし、そういう認識はなかったということであれば、証拠を出してもらいたいんです。招致委員会は既に解散しておりますけれども、残余財産は組織委員会にも引き継がれていますし、ましてや竹田前理事長、今JOC会長は、ある意味、同じ人物で当事者でありますから、先ほど話があった、こういう2億3千万円に対する対価としての活動報告書及び財務諸表は、今、誰が、どこで管理をされていますか。
そして、もう一つ伺います。
こういう問題が発覚した後に、ブラック・タイディングス社あるいはタン氏に接触をとって、渡したお金をおかしなことに使われていませんねという確認はとりましたか」
竹田恒和「まず、関係書類についてでありますが、これは、法人清算人であります招致委員会元専務理事水野正人氏が責任を持って管理をしております。この契約書につきましては、その存在と内容は、昨日、5月15日に現物を確認いたしました。そして、条約事項には守秘義務事項があることを御理解いただきたいと思います。守秘義務事項によりまして、契約相手側の確認など、法的な論点の検討を経ずに、直ちに開示をできるものではないと認識いたしております。
また、これが、先ほども御質問がございましたが、ペーパーカンパニーではないかということでございますが、契約時は、実績もあり、そしてペーパーカンパニーではないということを確実に認識しております。しかし、現在はどうなっているか、正直、把握しておりません。
そもそも、この世界でのコンサルタントは、個人事業も非常に多く、個人経営ですね、そして、海外を回って活動することも多いため、自宅を会社として登記している例も珍しくなく、多くのコンサルタントもそのようにしております。我々としては、あくまでも、ブラック・タイディングス社の実績を踏まえて今般の契約に至ったということをお伝え申し上げたいと思います」
玉木雄一郎「二番目の質問は、この事案が、事前にはわかりました、信頼あるところと信じてやったということなんですが、こういうことが取り上げられて、大きな世界的な疑惑になっておりますから、そういうことが出た後、改めてブラック・タイディングス社あるいはタン氏そのもの、こんなにたくさんのお金を払っているわけですから、連絡先は当然わかっていると思いますが、確認はされましたか」
竹田恒和「確認はいたしておりません」
玉木雄一郎「では、正しいということはどのように、妥当性について、今、確かに払ったことは払ったとお認めになっていますが、それが今、不正なものに使われたのではないのかということが、国際的な疑惑が生じているわけですから、その使途について確認は、では、それが適正なものであったかというのはどういうふうに確信をお持ちなんですか」
馳浩「今回の事案は、フランスの捜査当局が指摘をしたことから始まったというふうに認識しておりますから、私も大臣の立場で、ある意味では、そういう指摘を受けた以上は、きちんとフランスの捜査当局に協力をしなさいというふうな指示はもう出しておりますので、それを踏まえて、どのようにそのお金が使われたのかといったことも、フランス捜査当局との、関係捜査機関との調査によって明らかにされるべきものだと考えております」
玉木雄一郎「大臣、それは違うと思います。
この前、ロンドンで腐敗サミットが行われて、そこで、伊勢志摩サミットでは日本が主導してスポーツにおける腐敗対策の文書を取りまとめるということをもう言っているわけですね。しかし、ホスト国自身がオリンピックの招致にかかわって大きな疑惑を抱えたままでは、そんな文書を取りまとめるなんてできないと思いますよ。それこそブラックジョークですよ、これは。
だから、私がお願いしたいのは、まず委員長、サミット前までにもう一度、この件に関する集中審議を求めたいと思います。そして、先ほど大変重要な答弁があったのは、これは水野氏が報告書等を全て管理しているということでありますから、この水野氏と、そして前事務局長の樋口氏の参考人招致を求めたいと思います。
あわせて、最後、総理にお願いしたいんですが、これはやはりサミット前までにきちんとした、我が国独自にしっかり調査をして潔白だということを明らかにすべきだと思うんです。その意味でお願い申し上げたいのは、本件に係る契約書、活動報告書、そしてブラック・タイディングス社が本当に実績があるのかというその実績を記した文書、また財務諸表を、これは例えば党首討論がまた行われますから、その日の正午までに公表するようにぜひ促していただきたいのと、それと、第三者委員会、独立の調査委員会を立ち上げて、サミットまでに徹底した真相究明をすべきだと思いますけれども、総理、いかがでしょうか」
安倍晋三「先ほど馳大臣から答弁したとおりでありまして、フランス当局がまさに今捜査をしているわけでございますから、我々としては、このJOC側に対しては、旧招致委員会側に対しましてもしっかりと協力するように馳大臣から申し上げているところでございます」(玉木委員「いや、総理、最後に」と呼ぶ)
竹下亘「玉木さん、ちょっと待ってください。先ほど要求がありました集中審議の件、それから参考人質疑、それから財務諸表の提出、後刻、理事会で検討をさせていただきます」
玉木雄一郎「はい。よろしくお願いします。もう終わりますが、もともとこれが、国際的に取り上げたのは、一月に発表された世界反ドーピング機関の報告書です。その報告書の中にこういう記述があります。マーケティングコンサルタント業とは何を意味するのかについて、捜査当局間の共通認識として、それは不正な賄賂を隠す便利な言葉だというふうにされています。
ですから、コンサルタント契約の対価として公式に払ったといっても、まさにそれが不正を隠す一つの隠れみのになっていて、その使途が本当に適正だったかどうかについては、これは日本の名誉をしっかりと保つためにも徹底的に日本独自で自主的に調査すべきだと考えますので、このことを強くお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました」
|
玉木雄一郎が「この二億円を超えるものに対する対価として何らかの報告書はあるんですかないんですか」とコンサルティング会社に2億円以上の対価を支払うについての何らかの報告書はないのかと問い質したのに対して竹田恒和は「この契約書につきましては、その存在と内容は、昨日、5月15日に現物を確認いたしました。そして、条約事項には守秘義務事項があることを御理解いただきたいと思います。守秘義務事項によりまして、契約相手側の確認など、法的な論点の検討を経ずに、直ちに開示をできるものではないと認識いたしております」と答弁しているが、裏取引ならば、正規の契約書を装っているだろうから、そこからは何も見えてこない。
但しそのコンサルタント会社は本人からの売り込みであったために株式会社電通にその実績を確認したところ、調査の末、実績を請け合ったとしている。当然、どういった事柄の確認を電通に依頼したのか、その事項を書き連ねた書類の写しは残っていなければならない。調査にはカネが掛かるはずだから、のちのちの支払い・経費として計上する証拠として入出金表に残さなければならないからだ。電通にしても収入・経費・利益を計上する関係から、調査依頼を文書で受け取り、調査結果を文書で報告しなければならない。調査に関わるカネが組織間で動く以上、口頭で依頼して、口頭で依頼を受け、口頭で報告し、口頭で報告を受けたとすることは決してできない。
コンサルティング会社がペパーカンパニーの疑いがある以上、電通への依頼書、電通からの報告書がペパーカンパニーの疑いを払拭するより確かな証拠となる。玉木一郎はこの点を突破口とすべきだった。
だが、竹田恒和は自身の身の潔白を証明するより重要な証拠となる電通への依頼書、電通からの報告書を持参もせず、当然、見せることもしなかった。贈賄の疑いをかけられて国会に参考人招致された人物がそのような文書を持参しないということはあるだろうか。
また、コンサルティング会社はIOC委員やその関係者への働き掛けを依頼されていただろうから、報告書に「守秘義務」をかけるのは止むを得ないとしても、玉木雄一郎が「開催決定の2カ月前に約1億円がまず振り込まれ、そして開催が決定した次の月に残りの1・3億円が振り込まれている」と明かしている2013年10月に支払ったカネに関する前以っての契約について竹田恒和は「二回目の、招致決定後のIOC総会や東京招致の要因についての情報収集、分析を委託し、招致に関する報告や今後の活動などのために基礎資料とすべく業務をしたものでございます」と答えている、その手の「委託」にまで守秘義務をかける正当な理由は見い出し難い。
この点を突くべきだったし、逆に竹田恒和はなぜ存在するはずの業務依頼書と業務報告書を示して、「これこれこのとおり疚しいところはありません」と身の潔白証明の一つとしなかったのだろうという疑問が残る。
さらに「IOC総会や東京招致の要因についての情報収集、分析」の「委託」に「1・3億円」もの対価を必要とする理由にしても、その正当性は見い出し難い。成功報酬と捉えた方が素直に納得できる。どう贔屓目に見ても、状況証拠は限りなくクロを示している。黒いカネが功を奏した2020年東京五輪決定と見るべきだろう。「青、黄、黒、緑、赤」5色の五輪マークが全部黒色に見えてくる。

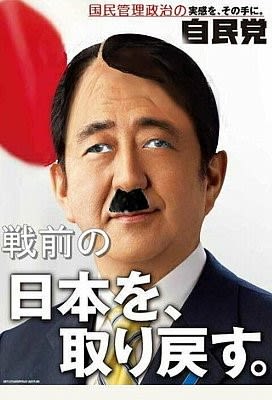 2019年7月28日任期満了実施参院選で
2019年7月28日任期満了実施参院選で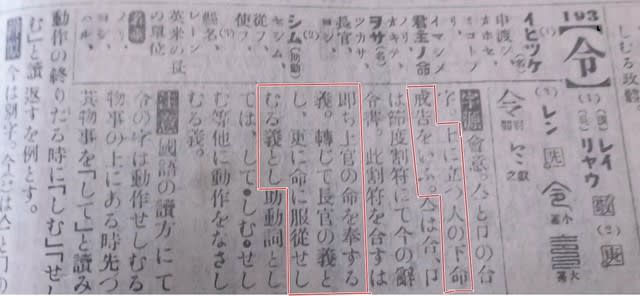 最初に書いたように菅義偉の新元号発表時の「令和」の「令」の字に上からの命令系の意味解釈を感じ取ったから、大正6年初版発行という時代物の『大字典』(啓成社)で調べてみた。「令」の字が載っているページの画像を載せておくが、かなりボロボロになっている上に撮影技術が未熟なために写りが悪いが、勘弁してもらうことにする。
最初に書いたように菅義偉の新元号発表時の「令和」の「令」の字に上からの命令系の意味解釈を感じ取ったから、大正6年初版発行という時代物の『大字典』(啓成社)で調べてみた。「令」の字が載っているページの画像を載せておくが、かなりボロボロになっている上に撮影技術が未熟なために写りが悪いが、勘弁してもらうことにする。















