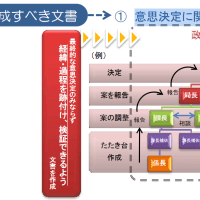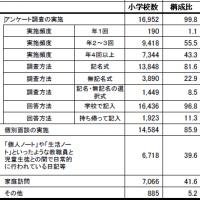| Kindle出版電子書籍「イジメ未然防止の抽象論ではない具体策4題」(手代木恕之著/2024年5月18日発行:500円) |
では、日本の歴代天皇は現人神としてこの世に現れた神の子孫であり、日本の神としての絶対的な存在性を纏うことができていたのだろうか。ネットから見つけ出した情報を頼りにこれまでにブログで書いてきたことと混ぜ合わせて自分なりに取り上げてみる。
先ず大日本帝国憲法「第1章 天皇」の主要部分を抜き出してみる。
第1條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第3條 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第4條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
第11條 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第13條 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
帝国憲法が天皇に規定しているこれらの権限のみを見た場合、天皇は絶対的権力を有する存在と看做すことができ、天皇独裁制を採用した国家体制と言える。何しろ神聖にして侵してはならないと絶対的地位を与えられているのである。
この神聖にして侵してはならないという絶対的地位は国民のみからではなく、政府の誰からも、帝国陸海軍の誰からも、保障を得ていなければ、天皇独裁制とは言えないし、大日本帝国憲法第1章天皇の各規定は単なる作文、見せかけとなる。
天皇のこの絶対的権力は他の条項をも保証している。
第4章 國務大臣及樞密顧問
第55條 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス
第56條 樞密顧問ハ樞密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ國務ヲ審議ス
輔弼(ほひつ):明治憲法下で、国務大臣・宮内大臣・内大臣が天皇の権能行使に対して助言す
ること。
諮詢(しじゅん):参考として他の機関などに意見を問い求めること
国務大臣は天皇に助言し、その助言に対して責任を負う。国務大臣は天皇の意見の求めに応じて国務を行う。このことも助言行為に相当し、責任を負う。天皇は一切責任を負わない。
この天皇の無答責は大日本帝国憲法「第1章 天皇」第3條の「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」に対応させた措置とされている。
但し天皇の側に主体性を置いた総理大臣や現役武官制を採用していた陸海軍大臣等の上級軍人 を含めた国務大臣側からの助言なのか、総理大臣や上級軍人を含めた国務大臣側に主体性を置いた天皇に対する助言なのかによって天皇無答責はイコール総理大臣や上級軍人を含めた国務大臣側の無答責となりうるし、そうなった場合は天皇の絶対性は形式的な性格を帯びることになり、天皇の無答責は総理大臣や上級軍人を含めた国務大臣側の有答責の隠れ蓑となるし、隠れ蓑とすることも可能となる。
もし隠れ蓑として利用していたのなら、天皇の絶対的存在性、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」の帝国憲法の規定を総理大臣や上級軍人を含めた国務大臣側自身が侵し無視していたことになる。
どのような経緯を取ったかを見ていくことにする。
既に触れているが、1941年(昭和16年)9月6日の第6回御前会議で帝国は自存自衛を全うするために対米(英蘭)戦争を辞せざる決意の下に概ね10月下旬を目途とし戦争準備を完整すことを決定した。その会議の内情を以下の記事とNHKの記事を参考に見ていくことにする。
『よもの海みなはらからと思ふ世になど波風のたちさわぐらむ』(日々のクオリア 砂子書房一首鑑賞 一ノ関忠人/投稿日:2014年9月6日)
この記事は当時陸軍軍務科高級課員だった石井秋穂(あきほ)大佐が事務方として会議に参加していて、その様子を書き記している「石井秋穂大佐回顧録」を参考に解説している。
〈「最後に天皇陛下は御親(みずか)ら御発言遊ばされ、先ず『枢相〔原嘉道枢密院議長〕の質問に対して統帥部が答えないのは甚だ遺憾である』と仰せられポケットから紙を御出しになり『四方の海皆はらからと思う世に/など波風の立ちさわぐらむ』との明治天皇の御製を二度朗読あらせられ『自分は常に明治天皇の平和愛好の精神を具現したいと思っておる』とお述べ遊ばされた。」〉――
第6回御前会議で原嘉道枢密院議長が統帥部に発した質問がどのような内容のものか、ネットを調べたが分からなかったから、MicrosoftのAI、Copilot(コパイロット)に尋ねたところ、〈
第6回御前会議で、原嘉道枢密院議長が統帥部に発した質問の内容は、具体的には「統帥部の戦争計画についてどのようなものか」というものでした。この質問は、戦争計画の詳細や具体的な戦略についての情報を求めるものでした。〉
ところが、統帥に関して天皇を直接補佐する役目にある陸軍参謀総長なのか、海軍軍令部長なのか、統帥部は答えなかった。和歌の内容以前の問題として、大日本帝国憲法「第1章 天皇」第1条で日本帝国の統治者と位置づけられ、第3条で神聖で侵してはならない存在とされ、第11条で陸海軍の最高統帥者である大元帥とされ、第13条で宣戦布告と戦争終結の発令の任を負う帝国国家に於ける最高権威者である天皇が臨席する場で国家の命運を左右するかもしれない戦争計画を枢密院議長から尋ねられて、統帥部は答えなかった。
ここで戦争の前準備作業の経緯を振り返ってみる。
・1941年1月18日、秋丸機関が行った、短期戦(2年以内)且つ対ソ戦回避の場合は対南方武力行使は概ね可能、但し対米英長期戦遂行は危険大を内容とする「対米英国力調査」の報告が為される。
・1941年8月27・28日両日、総理大臣直轄総力戦研究所の日米戦想定の机上演習報告「日本必敗」が告げられる。
・1941年(昭和16年)9月6日に第6回御前会議開催。帝国は自存自衛を全うするために対米(英蘭)戦争を辞せざる決意の下に概ね10月下旬を目途とし戦争準備を完整することを決定。
多分、自存自衛の旗印をいくら勇ましく掲げようが、対米英開戦に持っていった場合、十分に勝機はありますと簡単には答えることができなかったから、無視せざるを得なかったといったところなのかもしれない。
だが、天皇自身が「枢相〔原嘉道枢密院議長〕の質問に対して統帥部が答えないのは甚だ遺憾である」と注意し、件の和歌を読んだということは、既に報告が為されていた秋丸機関の「対米英国力調査」も、総力戦研究所の日米戦想定の机上演習も、統帥部は天皇には知らせていなかった疑いが出てくる。天皇に知らせていたなら、例えば、「我が陸海軍は対米英開戦したならば、必勝に向けた作戦を鋭意構築中です」といったことを原嘉道枢密院議長に伝えることもできたはずだし、あるいは昭和天皇自身、開戦の確率を承知することができていて、反戦和歌を詠む必要も生じなかったかもしれないからである。
なぜ天皇自身、陸海軍の最高統帥者であり、大元帥という地位にある役目上、「戦争する場合の勝機ありやなしや」、「戦争を避ける道はありやなしや」と直接統帥部に尋ねなかったのだろう。尋ねずに明治天皇が作った和歌を用いて、世界のみんなは兄弟姉妹みたいなものなのになぜ戦争の波風を立てるのかと遠回しな表現で戦争回避意思を伝えただけだった。
その程度のことしかできなかったということは大日本帝国憲法「第1章 天皇」の各条項に規定された天皇自身の巨大な権限を、本人の側からすると、ウソにする態度となり、統帥部側からすると、裏切る態度となる。
この両面性は大日本帝国憲法「第1章 天皇」の各条項が実体を備えていなかったことを意味することになり、天皇という存在は、備えていると看做されていた権限も権威も、何もかもを含めて、飾りに過ぎなかったことの証明としかならない。
当然、帝国憲法「第4章 国務大臣及枢密顧問」の「第55条 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任ず」の「輔弼」(天皇の権能行使に対して助言すること)にしても、どちらに主体性を置いた助言なのか、前のところで問い掛けたが、答は天皇の側に主体性を置いた国務大臣側からの助言ではなく、国務大臣側に主体性を置いた彼らからの助言ということであって、そうである以上、助言という形を装って、きっとこの上なく丁寧な言葉遣いを用いた、最初は遠回しな、最終的には自分たちの意思・要求を飲ませる性格の"助言"といった可能性が強い。
この第6回御前会議での天皇の発言は異例だということを次のネット記事で知った。テレビ放送の要約案内である。
「運命の御前会議 昭和天皇 戦争回避への苦闘」(NHK/放送日2019年07月31日)
〈番組より、1941年9月6日に開かれた御前会議。それまで、御前会議で天皇は発言することはないとされていたが、この日、ある行動をとる。昭和天皇の異例の意思表示と日本のリーダーたちが、それをどのようにとらえたのかの部分。
番組内容
日米開戦の危機迫る1941年(昭和16年)9月6日、昭和天皇は、政府と軍部の指導者たちが出席した御前会議で驚きの行動に出た。天皇は発言しないという慣例を破り、「歌」を披露したのだ。「よもの海みなはらからと思ふ世になと波風のたちさわくらむ」。
戦争回避を願う異例の意思表示は、緊迫した状況を平和へと引き戻すはずだった。しかし3か月後、日本は勝ち目なき戦争へ突入する。戦争か否か、天皇の知られざる苦闘と決断を描く。(著作権上の理由等で、一部放送とは異なる部分があります)〉――
天皇は発言しないという慣例があったが、それを破って、異例の意思表示を行った。理由の説明がないから、ネットを調べてみると、天皇の発言が天皇自身の責任に関係するのを避ける目的からといったことが紹介されているが、これは二つの点から疑わしい。
先ず一つは国家の重要な政策を方向づける会議の場で天皇は発言しないのが慣例となると、何のための大日本帝国国家の統治者なのか、意味を失うことになる。
第二に天皇の責任を言うんだったら、大日本帝国憲法第4章 國務大臣及樞密顧問「第55條」で、「國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」と規定している以上、総理大臣以下の、現役武官の陸軍大臣、海軍大臣を含めて、天皇は我々の助言に従っただけだから、天皇には責任はない、責任は我々にあるとすれば、済むことである。
だが、責任回避を目的に天皇が発言を控え、それを慣例としているならば、国家の統治者であり、陸海軍の最高統帥者である天皇を排除した形で国の政策は決定されていることになる。
この天皇臨席が形式に過ぎないという事実は大日本帝國憲法第1章「天皇」で規定している天皇の各権限自体が形式に過ぎないことを物語ることになる。既に触れているように天皇はお飾りに過ぎなかった。そして天皇の臨席が形式であることに対応して発言権を満足に与えられていなかったという事実を見ないわけにはいかないことになる。
大日本帝國憲法第1章「天皇」の条文に反するこの二重性は、勿論、存在理由があって成り立っていることだが、先ずは何のために天皇は存在したのか見ていく。
天皇はその時々の内閣や軍部首脳にとってお飾りに過ぎなかったが、1890年(明治23年)10月30日の明治天皇公布の「教育勅語」で国民一丸となっての天皇への奉仕を求め、昭和12年(1937年)発行の「国体の本義」で、万世一系の天皇が皇祖の神勅を奉じて大日本帝国を永遠に統治する在り方が我が国の万古不易の国体であり、その天皇とは神の子孫であると同時に皇祖及び代々の天皇と御一体で我が国を統治する現人神であって、永久に臣民・国土の生成発展の本源として存在し続けると天皇の権威を神格化の高みにまで持っていき、そのような天皇の本質を国民の目に具体的に示す在り方が帝国憲法第1条の「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」であり、第3条の「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」だと、天皇という存在の絶対性を国民意識に植え付ける目論みが為されていた。
だが、既に触れたように最重要な国策決定の場である御前会議では天皇が日本帝国の統治者としての、あるいは陸海軍の最高統帥者としての、さらには現人神としての意思表明を行うのではなく、逆にその意思表明を控えることを慣例としていた事実は政府首脳や陸海軍首脳が天皇のこれらの権限を、あるいは帝国憲法が表現している天皇の存在性自体を認めていないことの何よりの証明であって、天皇を除いた支配層側の憲法上は絶対的としている天皇という存在を虚構とする絶対性と国民向けに宣伝している絶対性の二つの絶対性――この二重性も天皇は負っていることになる。
天皇の絶対性に対する天皇を除いた支配層側のこのような無視は何も御前会議ばかりのことではない。『小倉庫次侍従日記・昭和天皇戦時下の肉声』(文藝春秋・2007年4月特別号)の昭和14年5月9日の日記には次のような記述がある。
〈御乗馬、御すすみあらざりしも、天気好かりしを以って遊ばしいただきたり。防共協定の問題に付、御軫念(ごしんねん・心配の意)と拝す。〉――
解説を受け持っている昭和史研究家・作家の半藤一利氏は次のように説明している。
〈このころ、昭和11年11月広田弘毅内閣のときに締結した日独防共協定を、軍事同盟にまで強化する問題をめぐって、平沼騏一郎内閣は大揉めに揉めていた。陸軍の強い賛成にたいして、海軍が頑強に反対していたのである。このため平沼首相、有田八郎外相、石渡荘太郎蔵相、板垣征四郎陸相、米内光政海相による五相会議が連日のように開かれていたが、常に物別れとなり、先行きはまったく見えなかった。〉
3日後の「小倉庫次侍従日記」の記述。
〈5月12日 秩父宮殿下10時参内。(以下略)〉――
半藤一利氏解説「『昭和天皇独白録』(文春文庫)にはこう書かれている。
『それから之はこの場限りにし度いが、三国同盟に付て私は秩父宮と喧嘩をしてしまった。秩父宮はあの頃一週三回くらい私の処に来て同盟の締結を進めた。終には私はこの問題については、直接宮には答へぬと云って、突放ねて仕舞った』」――
昭和天皇は日独伊三国同盟締結には反対していた。秩父宮は締結に賛成で、天皇を説得しようと皇居を頻繁に訪れた。対して昭和天皇は「私はこの問題については、直接宮には答へぬ」と突っぱねた。要するに反対の意思を賛成の意思を示している秩父宮に個人的に表明していた。
なぜこのような個人的な対応を取っていたかと言うと、五相会議に答がある。「五相会議」(Wikipedia)
〈「五相会議」とは、昭和時代前期の日本において、内閣総理大臣・陸軍大臣・海軍大臣・大蔵大臣・外務大臣の5閣僚によって開催された会議。 主に陸軍・海軍の軍事行動について協議され、これを実現する財政・外交政策のために蔵相、外相も出席した。 議案の必要に応じて企画院総裁なども出席したことがある。〉――
外国と軍事同盟を締結することの是非を議論する重要な国策決定の場でもある五相会議から日本帝国の統治者であり、陸海軍の最高統帥者たる天皇の出席は排除されていた。しかも天皇自身は三国同盟の締結に反対していながら、結局のところ締結されたという事実は政府や陸海軍が賛成の立場を取った場合、天皇の賛成の承認のみが必要であって、反対の意思は無視されることを示すことになり、天皇が大帝国憲法上担うその絶対性は政治や軍事の場では虚構に過ぎないことになって、やはり政府や陸海軍にとってお飾りそのものであることを暴露することになる。
いわば政治・軍事の実権は憲法の規定どおりに昭和天皇ではなく、政府・軍部が握っていた。この権力の二重性は昭和天皇に限ったお仕着せではないし、その時代に限られた権力構造ではないことは昭和天皇が第6回御前会議で詠んだ「四方の海皆はらからと思う世になど波風の立ちさわぐらむ」が祖父明治天皇の作で、日露戦争開戦前に詠んだものの、この意思表示に反して日露戦争に突入した事実によって、明治天皇までもが同じ実体、虚構の絶対性を纏っていたことを証明することになる。
言葉を変えて言うと、明治天皇は和歌を読むことでしか日露戦争に反対の意思を示すことができなかった。そして昭和天皇は日露戦争開戦阻止に何の役も立たなかった明治天皇作の和歌を対米英開戦反対の意思表示として詠むことしかできなかった。
明治天皇は父親の孝明天皇の満35歳での崩御(1867年1月30日-慶応2年12月25日)に伴い、大政奉還(慶応3年10月14日-1867年11月9日)の約9月前に皇位を継承した。年齢16歳。この明治天皇の父親の孝明天皇の崩御については、『大宅壮一全集第二十三巻』(蒼洋社)に、「当時公武合体思想を抱いていた孝明天皇を生かしておいたのでは倒幕が実現しないというので、これを毒殺したのは岩倉具視だという説もあるが、これには疑問の余地もあるとしても、数え年16歳の明治天皇をロボットにして新政権を樹立しようとしたことは争えない」と書いている。
大宅壮一は孝明天皇暗殺説を全面否定しているわけではない。岩倉具視以外の誰かが行った可能性を残している。例え暗殺でなかったとしても、薩長一部公家の討幕勢力が天皇を頂点に据えたのは徳川幕府約265年間の歴史とその権威のスケールに対抗するに薩摩藩主や長州藩主、単なる公家では見劣りがして、徳川に遥かに優る皇紀2500余年の歴史を当時抱えていた皇室という存在を旗印として必要としたからだろう。
そして自らを官軍と位置づけ、徳川幕府方を皇室から政権を簒奪した賊軍と位置づけて、自らの勢力の正当性を打ち立てることで士気の点でも優位を狙い、徳川幕府を倒すことができ、明治政府の発足となったが、薩長連合一部公家政権が明治天皇をロボット、いわば単なるお飾りにし、権力の二重構造としたのは本人が政治・軍事について右も左も分からない数え年16歳という若さだけが原因を成したわけではない。
歴史的に朝廷に代わって世俗勢力の台頭以降、いつの時代も朝廷という存在に対して権力を実質的に掌握していたのは世俗勢力自身であって、世俗勢力は日本国を統一した豪族連合の頂点に立っていたという朝廷の権威だけを必要とし、その権威を利用して天皇を頭に置きながら、政治を恣にした。当然、歴代天皇自身が自らの力で126代の地位の全てを紡いできたわけではない。大和朝廷成立以降から世俗権力者である豪族たちが自分の娘を天皇の后(きさき)に据えて生まれた子をのちに天皇の地位に就け、自身は外祖父や外戚として世俗上の実権を握り、天皇を名ばかりとする権力の二重構造は豪族たちの権力掌握と権力操作の歴史的に伝統的な常套手段となっていった。
例えば古墳時代の豪族、蘇我馬子らの父親である蘇我稲目が娘を天皇の妃とし、その子が用明天皇や推古天皇として即位していて、権力を恣にしている例は日本史の早い時期から権力の二重構造が確立してことを示す例となる。
さらに蘇我馬子が自分の娘を聖徳太子に嫁がせて山背大兄王(やましろのおおえのおう)を産ませているが、聖徳太子没後約20年の643年に専横を極めていた蘇我入鹿の軍が自らの権力の確立のために古人大兄皇子(=ふるひとのおおえのおうじ、舒明天皇の皇子、母は蘇我馬子の娘の蘇我法提郎女=ほてのいらつめ)を天皇に立てるべく、斑鳩宮を襲わせ、聖徳太子の子である山背大兄王(やましろのおおえのおう)らを妻子と共に自害に追い込んでいる例にしても外戚として天皇の権力を我が物にしようとする権力の二重構造を企む典型例であり、飛鳥時代にも引き継がれていたことを示すことになる。
平安時代中期の公卿の藤原道長にしても同じ常套手段を利用した。一条天皇に長女の彰子を入内させ皇后とし、次の三条天皇には次女の妍子(けんし)を入れて中宮とするが、三条天皇とは深刻な対立が生じると、天皇の眼病を理由に退位に追い込んで、長女彰子の生んだ後一条天皇を9歳で即位させ、自らは後見人として摂政となり、政治を動かすことになった。
一年ほどで摂政を嫡子の頼通に譲り、後継体制を固める。後一条天皇には四女の威子(たけこ)を入れて中宮となし、「一家立三后」(=「いっかりつさんこう」、天皇3代の皇后を全て自分の娘にしたこと)と驚嘆されたという。そして藤原氏の次に権力を握ることになった平清盛も娘を天皇に嫁がせて、外戚(がいせき・母方の親戚)となって権勢を誇ることになった。
要するに世俗権力者である豪族たちが自分の娘を天皇の后(きさき)に据えて生まれた子をのちに天皇の地位に就け、自身は外祖父か外戚として世俗上の実権を握り、天皇を名ばかりとする権力の二重構造は豪族たちの権力掌握と権力操作の常套的手段として忠実に受け継いで行く伝統となった。
時代が下って自分の娘を天皇に嫁がせて、その子を天皇に据える傀儡化――血族の立場から天皇家を支配する権力の二重構造は廃れ、源頼朝以降、距離を置いた支配が主流となっていくが、自身の武力で天下統一を果たしていながら、天下統一による国家支配の正当性は朝廷に付与させた征夷大将軍の役職に置き、国家支配そのものは自らが行う権力の二重構造の形式は維持された。
一方で明治に入って薩長一部公家とそこから派生した軍部が憲法で天皇を国家統治者とし、陸海軍の最高統帥者等、国家の最高位に位置づけるが、天皇としては表向き敬うものの名目的存在にとどめて、国民に対しては「教育勅語」や「国体の本義」で著した思想や精神の教化を通して天皇を敬い、従うべき絶対的存在に仕立てて、名目的と絶対的の使い分けで国家と国民を天皇の名のもとに統治する権力の二重構造へと姿を変える。
本質部分では変わらない、この歴史的に伝統的な権力の二重構造をより強固に維持する要件として考え出され、実行に移された権威が万世一系であり、男系、あるいは2千何年という長い歴史であり、現人神であるといった天皇家を飾り立てる数々の壮大な仕掛けであり、仕掛けが大きい程にその権威を利用する側は大きな効果を見込むことができる。その手の利便性から結果的に126代も延々と続いたということであろう。
このことが同時に国民統治の優れた装置として大きな力を発揮したということになる。
でなければ、天皇が歴史的に名目的な存在とされてきたことに反するこれらの壮大な権威付けの説明がつかない。
「国体の本義」その他を通してこのような天皇の権威付けに迫られたのは明治以降、西洋の文化・文物が入ってきて、国民がその影響を受けやすくなった国情(開戦の前年は都市部ではアメリカブームに沸き、ハリウッド映画やジャズが流行していたとNHKの日本の戦争を取り上げた放送が伝えていた)、さらに昭和に向かう過程で列強との対立と競争が激しくなってきた国情を受けて、天皇の権威を利用して国家権力を恣にする世俗勢力が国論の統一、いわば政府にとって望ましい形の国民統治を確保しつつ、国家統治の実権を守り続ける権力の二重構造維持の利便性を担保するためには、当然のこと、天皇の権威は壮大であることが望ましいからだ。
米英戦争の過程で天皇の権威はより強調されることになり、政府の天皇の名前を利用した呼びかけに応じて、兵士は戦場に赴き、一般国民は銃後の支えとなり、それが自国国力を過大評価した杜撰な戦争計画だとは知らないままに多くの兵士が戦場に散り、多くの一般国民が激しい空襲や艦砲射撃で命を落とすことになった。
このように天皇が権力の二重構造維持のために利用される存在だったことを考えると、安倍晋三が2006年7月20日発刊の自著『美しい国へ』の中で、「日本では、天皇を縦糸にして歴史という長大なタペストリーが織られてきたのは事実だ」と書き、2012年9月2日の日本テレビ「たかじんのそこまで言って委員会」に出演して、「むしろ皇室の存在は日本の伝統と文化、そのものなんですよ。まあ、これは壮大な、ま、つづれ織、タペストリーだとするとですね、真ん中の糸は皇室だと思うんですね。この糸が抜かれてしまったら、日本という国はバラバラになる」と言っていることは、権力の二重構造からしてバラバラになるのを防いでいたのは天皇の権威を利用して国を治めてきた世俗勢力なのだから、安倍晋三の歴史認識は軽薄なフィクションに過ぎないことが分かる。
明治以前の歴代天皇は、例外はあるが、殆が皇室という世界でのみ生息してきた。明治に入って世界政治の表舞台に立つことになったが、その権威を必要とされるだけで、政治的決定権は世俗勢力に従う受け身の存在であることに変わりはなかった。
天皇と世俗勢力の権力の二重構造からすると、安倍晋三の皇室の存在と日本の伝統及び文化をイコールさせる歴史認識、日本の伝統と文化は皇室と共にあったと見る歴史認識、日本の歴史そのものを一連続きのつづれ織、タペストリーに喩えて、真ん中の糸を皇室と見る歴史認識は明治以降から終戦までの政府や軍部がいたずらに天皇を権威付けてきたきたことの踏襲に過ぎない。安倍晋三が戦前型の国家主義者であることの所以である。
そもそもからして多くの歴史学者が神話上の人物としか見ていない神武天皇を初代天皇として、その即位年から日本建国の年数を数える日本式の紀年法である"皇紀"なる名称は4世紀末頃から5世紀頃の大和朝廷成立当時からあったものではなく、1872年(明治5年)に「太政官布告第342号」を以ってして制定したものであって、政府は1940年(昭和15年)が皇紀2600年に当たるとしてその年に大々的に奉祝行事を行うことになったが、明治に入ってから使い始めたという経緯からすると、皇紀元年を西暦紀元前660年に当てていることから、天皇家の歴史が西洋の歴史と遜色ない長さを持っていることを材料に日本の歴史及び大日本帝国と天皇を権威付ける仕掛けであったことがミエミエとなる。
天皇に付与したあれこれの権威が国民を統治するための仕掛けに過ぎなかったからこそ、対米英戦争で日本が不利な状況に立たされると、天皇の権威が崩れ去るのを恐れて、大本営は天皇直属の最高戦争指導機関でありながら、国民に対してだけではなく、天皇に対してもウソの戦況報告をするに至った。この点からも軍部は実質的には天皇の下に位置していたのではなく、天皇の上に位置し、天皇を名目的存在として扱っていたことが露見する。だから、対米戦争反対の天皇の意向を無視して、対米戦争に突入することができた。
天皇をより良き国民統治装置とするために神の子孫とし、且つ現人神だと敬わせ、日本は神国だと日本民族の他民族と比較した優越性を謳い、天皇の神格化とその優越性を国民の精神に植え付けて国民を鼓舞し、戦争に駆り立てるのは天皇の利用で済むが、冷徹で合理的な計算が求められる戦争の場にまで日本人の優越性用いて鼓舞する精神主義を持ち込んだのは天皇の権威を利用して国民を支配し、統治する計算を裏切って、政府や軍部までが日本民族の優越性に取り憑かれていた証明となり、その合理精神の欠如が自国国力過大評価と米国国力過小評価を生み、杜撰な戦争計画へと発展していったと見るほかない。
当然、戦死者はその犠牲となったのであり、政調会長だった当時の高市早苗が2021年10月18日の秋季例大祭に靖国を参拝した際、「国策に殉じられた方に、尊崇の念を持って感謝の誠をささげてきた。日本人として感謝を捧げるのは当たり前だ」と語った言葉は、当の国策が自国国力過大評価と米国国力過小評価を内容とし、そのような杜撰な国力評価に基づいた杜撰な戦争計画となっていたのだから、思いどおりの力で戦った類いの"殉じた"とするのは戦死の実相を奇麗事に見せる企みそのもので、思いどおりに戦えずに戦死を強いられたといったところが大方の戦死の実際の姿であったはずだ。
戦闘に於いて日本民族の優越性に基づいた精神主義が罷り通っていた例を敗戦まで用いられていた大日本帝国陸軍の「歩兵操典」から簡単に見てみる。注釈等は当方。
「歩兵操典(全)」(豆辯- Douban)
| 〈第2 戦捷(戦勝)の要は有形無形の各種戦闘要素を総合して、敵に優る威力を要点に集中発揮せしむるに在り 訓練精到(詳しくて、よく行き届いていること)にして、必勝の信念堅く、軍紀至厳(極めて厳しいこと)にして、攻撃精神充溢せる軍隊は、能く物質的威力を凌駕して戦捷(戦勝)完うし得るものとす 〈第3 必勝の信念は主として軍の光輝ある歴史に根源し、周到なる訓練を以って之を培養し、卓越なる指揮統帥を以って之を充実す 赫々たる伝統を有する国軍は、愈々(いよいよ)忠君愛国の精神を砥礪(しれい:努め励むこと)益々訓練の精熟を重ね、戦闘惨烈の極所に至るも上下相信倚(しんい:信頼する)し、毅然として必勝の信念を持せざるべからず 第6 軍隊は常に攻撃精神充溢し、志気旺盛ならざるべからず 攻撃精神は忠君愛国の至誠より発する軍人精神の精華にして、強固なる軍隊志気の表徴なり。武技之に依りて精を致し、教練之に依りて光を放ち、戦闘之に依りて勝を奏す。蓋し勝敗の数は必ずしも兵力の多寡に依らず。精練にして、且つ攻撃精神に富める軍隊は、克(よ)く寡を以って衆を破ることを得るものなればなり 第68 突撃は兵の動作中特に緊要なり 兵は、我が白兵の優越を信じ勇奮身を挺して突入し敵を圧倒殲滅すべし。苟も(いやしくも)、指揮官若しくは戦友に後れて突入するが如きは深く戒めざるべからず 兵は敵に近接し突撃の機近づくに至れば、自ら着剣す〉 |
「第2」、作戦は地理や天候、地勢、地の利の不利・有利、そして敵軍と味方軍の兵力の差等、各戦場の状況を計算した戦術の具体性の良し悪しによって決まるはずだが、「敵に優る威力を要点に集中発揮せしむる」の「敵に優る威力」は兵力(兵員数や兵器の種類とその数量、その性能などの総合力に基づいた戦闘能力)が必須要素となるが、そのことを考えない精神論で成り立たせた戦術の具体性もない抽象論そのもので成り立たせている。
緻密な訓練(=訓練精到)が、「必勝の信念」を育み、厳しい軍紀(=軍紀至厳)が「攻撃精神」を充溢させ、そういった優れた要素に満たされた軍隊は、相手の物理的戦闘規模(=物質的威力)を上回って戦勝をもたらすとしていることは、そういった信念や精神をしっかりと身につけさえすれば、三八式歩兵銃でアメリカ軍の機関銃群に立ち向かったとしても、戦いに勝利できると言っているようなもので、戦術・戦略を全く抜きにした精神論そのものでしかない。
「第3」、「軍の光輝ある歴史」が「必勝の信念」を生み出して、その信念のもと、「忠君愛国の精神」に努めて、訓練技術の向上に励み、将兵が相信頼し合えば、どのように激しい戦闘に遭遇しようとも、必ず勝利するだという自信を持たせなければならないとしているが、ここでは必ず勝利するという自信を持つことができると確信を与えるのではなく、自信を持たせるよう義務としている点は少なからず自信がなかったのかもしれない。
だが、戦術を抜きにした精神論を語っていることに変わりはない。忠君愛国の精神と日本軍人としての誇り・自信が勝利をもたらすという精神主義が日米陸軍武器の量及び性能を含めた戦力差にしても、陸海含めた兵員数の差にしても約10倍以上とされた状況下で戦局にどう影響するかという合理的判断を排除している。
「第6」、「勝敗の数は必ずしも兵力の多寡に依らず」が事実であったとしても、「忠君愛国の至誠」に発する「軍人精神の精華」、それが生み出す「強固なる軍隊志気」が「攻撃精神」をもたらしたとしても、様々に想定した数多くの実地訓練を通して獲得する戦闘行動を体と頭に記憶させ、記憶させた戦闘行動を実際の戦闘で状況に応じて臨機応変に再現することのできる身体的スキルを身につけることの方が実際的で、それでもなお兵力差の影響を受けることを頭に置いておかなければならない必須要件であり、「忠君愛国の至誠」に基づく「軍人精神の精華」だ、「強固なる軍隊志気」だ、「攻撃精神」だだけでは片付かないことを認識させる注意が必要だが、精神論だけで終えている。
「第68」、敵陣地に近接できた場合の集団の突撃は一定程度の犠牲を計算に入れた上で効果は見込めるが、近接とは言えない距離からの集団の突撃は敵の火力の餌食に曝されるのが精々で、それを、〈我が白兵の優越を信じ・・・敵を圧倒殲滅すべし。〉と、戦場で敵味方が抱えることになる様々な状況・条件の違いを考慮せずに精神主義をベースに無条件の勝利を可能としている。
1942年8月7日から1943年2月7日までの約7ヶ月間のガダルカナル島の戦いでは、NHKのテレビ放送が伝えるところでは、島を占領したアメリカ軍に対して奪還を目指した約900人の日本陸軍がアメリカ兵力1万人に対して2000人程度と誤認、さらに睡眠中と誤認したのだろう、小銃の先に剣を装着し、夜間の白兵突撃を敢行、対してアメリカ軍は飛行場の周辺に集音マイクを設置、日本軍の動きを察知、待ち構えていて、2方面から機関銃などを浴びせる十字砲火で応戦、日本軍900人のうち777人が命を落とすことになったと伝えていた。
アメリカ軍が万が一待ち構えていたなら、どう戦術転換をするかという危機管理を頭に置かない勢いに任せた突撃で勝利を計算できるのは精神主義頼りだからであって、精神主義を単純画一的な戦術としていたからだろう。
日本側が米英の7倍余の310万もの戦死者を出した事実は突撃は個々の戦場での個々の戦いに限定された精神主義を纏わせた戦術ではなく、戦争全体が精神主義に裏打ちされた突撃の性格を帯びていたことの証明とすることができる。
このような精神主義だけを頼りとした戦争はあまりにも合理性を欠いている。杜撰な日米国力評価に基づいた杜撰な戦争計画を結果として招いたことはある意味当然だったと言える。
戦闘の場面では勝敗を左右する重要な要件は兵力や地勢に基づいた戦術の如何にあるのであって、忠君愛国や、軍の光輝ある歴史によって叩き込まれた帝国軍人魂ではないことを教えられないままにそれらを戦いの主たる要件とした場合、合理的精神は抑えられて忠君愛国だ、帝国軍人魂だといった精神主義だけが顔を利かすことになり、いとも簡単に戦争のリアリズムの生贄になるのは目に見えている。
ところが、合理的思考力が必要とされる戦後になっても、国民統治装置として万世一系だ、男系だ、現人神だと様々に権威付けてきた歴史から目を逸らして、そのような天皇の存在を根拠に日本民族の優越性を謳う少なくない日本人が存在する。
例えば国家主義的心理性で安倍晋三とベッドを共にしている高市早苗は2021年9月29日投開票の自民党総裁選に向けて自身の思想と政策を纏めた『美しく、強く、成長する国へ』(Kindle電子書籍)云々の著作の中で、「大自然への畏敬の念を抱きながら勤勉に働き、懸命に学び、美しく生き、国家繁栄の礎を築いて下さった多くの祖先の歩みに、感謝の念とともに喜びと誇らしさを感じずにはいられない。現在においても、126代も続いてきた世界一の御皇室を戴き、優れた祖先のDNAを受け継ぐ日本人の素晴らしさは、本質的に変わっていないと感じている」と謳い上げているが、この主張を成り立たせている根本思想は天皇主義に基づいた全体主義である。
祖先のDNAを全て優れていると見ていて、当然、その子孫である現日本人を全て優れていると見ていることになるが、"優れている"とした場合、日本民族優越意識があからさまになるからだろう、"素晴らしい"と一段と和らげた表現となっているが、その評価を日本人全体に置いている以上、日本民族の全体的優越性を謳い上げていることになる。
また、高市早苗がこの日本民族優越意識の根拠を皇室の存在や戦前の歴史から見ていることは自身のサイト、『高市早苗ブログ』2002年08月27日)に、〈欧米列強の植民地支配が罷り通っていた当時、国際社会において現代的意味での「侵略」の概念は無かったはずだし、国際法も現在とは異なっていた。個別の戦争の性質を捉える時点を「現代」とするか「開戦当時」とするかで私の答え方は違ったものになったとは思うが、私は常に「歴史的事象が起きた時点で、政府が何を大義とし、国民がどう理解していたか」で判断することとしており、現代の常識や法律で過去を裁かないようにしている。〉と述べていることから明らかだが、歴史的事象が起きた戦前の時点の1941年12月8日の時点では未明の米ハワイ島オアフ島真珠湾基地に対する奇襲攻撃の戦果が国内で伝えられ始めると、多くの国民が常に天皇の存在を背景に置いて、知識人を交えて戦果を歓呼で迎え、日本の敗色が濃厚になった以降も大本営の国民の戦意喪失の防止からの偽情報の流布、あるいは不都合な情報の隠蔽工作が功を奏して、国民が戦争を支持し続けていたことは事実と言える。
安倍晋三も2006年7月20日発刊自著『美しい国へ』の中で、「列強がアフリカ、アジアの植民地を既得権化する中、マスコミを含め、民意の多くは軍部を支持していたのではないか」を論拠に、「その時代に生きた国民の視点で歴史を見つめ直す」と書いていて、出来事が起きた時代に生きていた人間の総体的解釈が歴史認識だとしている。
いわば両者共に国民がその当時、何に賛成し、何に反対したのか、そのことによってのみ、歴史は価値づけられる、あるいは歴史は解釈されるとしている。だが、二人のこの考え方自体が論理矛盾に彩られている。なぜなら、日本が米英に宣戦布告した出来事自体は当時はまだ歴史にはなっていない、国家の政策遂行(=国家行為)に過ぎないからである。何らかの国家のその時々の政策遂行(=国家行為)が歴史の形を取るためには時間の経過、時代の経過が必要条件となる。つまり当時の国民ができたことは開戦、あるいは戦争という国家の政策遂行(=国家行為)に対する賛否――是非の解釈のみである。
特に政府・軍部等の国家の支配層の国民に対する天皇絶対崇拝の教育、あるいは洗脳が行われていて、ほぼ無条件に国の政策に従属させられた時代下で自由な意思表示・判断は表沙汰にはできなかった。表沙汰になったり、密告されたりしたら、国賊とか、アメリカのスパイとして取り締まりを受けるか、社会的な制裁を受けることになった。
逆に後世の国民ができることは戦前当時の国家状況及び世界状況や社会状況等を起因とした国家の政策遂行(=国家行為)が時間の経過、時代の経過を経て歴史となった時点で時間・時代の経過と共に蓄積することになった知識・情報を背景とした現在の国民の目を通した是非の解釈である。決して国家の政策遂行(=国家行為)に対する当時の国民の解釈そのままに同調する、しないが歴史解釈ではない。
当然、安倍晋三が、いわば「その時代に生きた国民の視点」を歴史解釈とする、高市早苗が過去の出来事はその時代の常識や法律で裁くと言っていることは当時の日本国民は殆が天皇と国家を支持していたのだから、戦前日本の天皇制に基づいた国家体制、大日本帝国国家を肯定している両者の歴史認識となる。
この肯定を歴史認識としている以上、安倍晋三や高市早苗等の保守政治家が「お国のために命を捧げた」、「国に殉じた」を口実とした靖国参拝を戦前国家肯定儀式と断じているのはこの点にある。
と同時に戦前の大日本帝国国家に歴史認識を肯定的立場から寄り添わせている関係からして、両者共に個人よりも国家に絶対的価値を置く国家主義者の範疇に入れることができる。
自国国力過大評価・米国国力過小評価に基づいた杜撰な戦争計画で戦った戦争であるということと、兵力の差、武器の性能の差、地の利の有利・不利、時間帯等々を計算し尽くした合理性に則った戦術ではなく、合理性も何もない精神主義を拠り所とした戦い方を叩き込んで、闇雲に突撃精神だけで戦わせて多くの兵士を死なせたのだから、愚かな国策の犠牲となったが実際の姿でありながら、靖国神社に祀った戦死者に手を合わせて、国策に殉じたとか、国のために尊い命を捧げたとか、"国策"や、"国"を主体にして顕彰することができるのはやはり個人よりも国家の価値観を大事にする国家主義の姿勢を正体とし、戦前国家を肯定しているからできることである。
《日本国力過大評価と米国力過小評価に基づいた杜撰な対米英戦争計画から見る安倍、高市等の靖国参拝(1)》に戻る