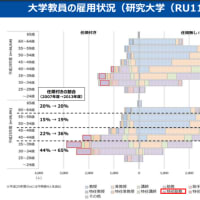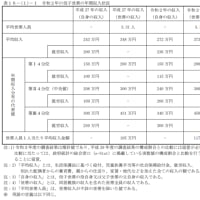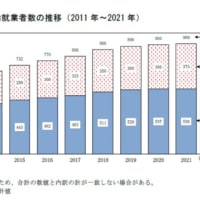毎日新聞のWebサイトに、「まだまだ学ぶべきことがあるのだな~」と、実感する記事があった。
それは、最近話題になっている「NFT」についての記事だった。
毎日新聞:仮想空間でも靴を買う?NFTが生んだ「値段をつける力」
先日、拙ブログでも「NFT」について少し書かせていただいた。
とはいうものの、私自身が「NFT」そのものを十分理解している、というわけではなく、以前「デジタルアートを買う」という方のお話を聞きかじった程度の内容だったため、中途半端な内容になってしまったのでは?という感覚は否めなかった。
そんな中、毎日新聞の記事はわかりやすく解説をされているような気がしている。
とはいうものの、「仮想空間でも靴を買う?」という見出しだけ見れば、電通が仕掛けて失敗に終わった感のある「セカンドライフ」のような「仮想空間の中で生活をしているアバターが、靴を買う」というイメージを持たれる方のほうが多いのでは?という気がしている。
そもそも電通が仕掛けた「セカンドライフ」という仮想空間は、ネットゲームとは違うがネット上でのコミュニケーションを目的としていた(と、記憶している)。
ネット上のコミュニケーションを目的としている為、当然のように「街があり、生活がある」ということになる。
街があれば、「買い物をする」ということも当然含まれる。
そのような「ネット上(=仮想空間上)でアバターというツールを使って、コミュニケーションを育む」というのが、「セカンドライフ」の目的の一つだった(はずだ)。
違う言い方をするなら、大ヒットしたゲーム「あつまれどうぶつの森」のような場所がいくつもあり、その場所を行ったり来たり、買い物をするといった「生活」をするコミュニケーションツールだった。
しかし「NFT」の仮想空間というのは、「セカンドライフ」のような「ネット上の生活」を基盤としたコミュニケーションを目的としているわけではない。
取引として行われる場所が「仮想空間」であり、そこで売買されるのは「所有する権利」なのだ。
「所有する権利」だから、その所有物に対しての価値観が同じような人たちが集まらなくては、その市場は成立しない。
それだけではなく、「所有する権利」を持った人が、コピーをすることはできるが、そのコピーされたモノには「価値はない」ということになる。
重要なポイントは、「コピーされたモノには価値がない」ということなのだ。
「コピー=複製」されやすいというものとして、音楽や美術作品がある。
ネット社会となり、そのコピーのされやすさは、以前とは比べモノにならないほど短期間で大量に作られるようになっている。
ネット上に公開されたモノ・コトは、誰もが気軽にコピーすることができ、美術品の「贋作」とは違い、技術的な知識や技量を必要としない。
そのようなモノに対しても「価値をつけ、保護をする」という機能を持っているのが、「NFT」ということのようだ。
とすると、見出しにあった「靴を買う」というのは、ネット上で公開された「靴のデザインを買う」ということである、ということが理解できる。
その「靴のデザイン」を「NFT」を通して購入すれば、「靴のデザインの権利」は購入者も持つこととなる。
そのように考えると、「アートとNFTは親和性がある」ということになるだろう。
著名なアーティストが作った作品を、一人の人が所有するのではなく、その「価値を決められる人たちが複数で持つ」ことができれば、アートに興味を持つ人たちは増えるかもしれない。
その反面、その「価値を付けられる人」に限られる、ということになる。
それは多くの市井の人たちが、アートを所有することで、その作品を楽しむ人が増える可能性を秘めているが、日本のように「アートは高尚な人たちの趣味」と視野を狭めて楽しめない人たちにとっては、まったく関係のない「投資目的」となってしまう可能性もあると、懸念もしている。
最新の画像[もっと見る]