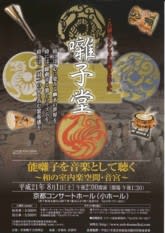
舞と音楽(謡・器楽)によって成り立つ能楽。そのうち器楽(笛・小鼓・大鼓・太鼓)の奏者を囃子方という。常は主役の引き立て役。今日は囃子方が主役の演奏会であった。
波の音や、弦をかき鳴らす音を、笛と小鼓の一対一の真剣勝負の中でイメージするのが聞きどころという「絃上」。
獅子が狂ったように遊び戯れる様を笛、小鼓・大鼓・太鼓だけの素囃子で表現する「内外詣(うちと もうで)」。掛け声の応酬に迫力があった。獅子舞を舞うという格調の高さは、最高の境地、秘儀に近いものだと解説された。みなで13曲。
専門的なことにはうとい。が、今年で7回目、うち4回を楽しんだ素人ファン。多くの亡き方々の縁者と出会うお盆を前に、心の土壌に水やり。単純に、日常を離れた空間に飛び出たかったかのような気もする今年。
 大鼓の音は脳天を突き抜けていく。謡の、まろやかで優雅な節にうっとり。和した調べが琴線に触れる。魂が揺り動かされると言ったらオーバーか。日本人であることを感謝のひと時。
大鼓の音は脳天を突き抜けていく。謡の、まろやかで優雅な節にうっとり。和した調べが琴線に触れる。魂が揺り動かされると言ったらオーバーか。日本人であることを感謝のひと時。ステージ上に奏者は、時に二人、多くて五人が横並びに座る。
指揮者がいない。他の奏者のやり方を互いに聞き合わせながら、各自のパートを演奏し、全体の調和を作り上げる。そして一定の約束に従った掛け声でタイミングを取り合っていくのだという。
「みんな違っていい」と言ってしまう前に、聞き合わす・各自のパートに励む・声かけで調和を作り上げる努力……か。そこに、埋もれることのない個の輝きを見る。初めて、みんなそれぞれの輝きでいいんだと思わされる。ひとそれぞれ勝手でいいのではなさそうだ。
メロディーを奏でない小鼓の柔らかな音にも強烈な存在感がある。















