「日本の伝統色・和色辞典」というサイトがあり、465色の和名のカラー見本が紹介されています。
http://www.colordic.org/w/
桜の季節になりましたが、「薄墨桜」って有名ですね。「岐阜県本巣市(旧・本巣郡根尾村)の淡墨公園にある、樹齢1500年以上のエドヒガンザクラの古木である。花の色が日を追うごとに変わり最後には薄墨色に変わる」(ウィキペディア)という桜だそうですが、一度拝見したいと思いますねー。「薄墨色」ってどんな色なのだろうと思いこのサイトをぐぐって見ると、随分にごった色で随分イメージと違いました。実物はもっと優雅な色合いをしているのでしょう。「桜鼠(さくらねず=pink gray)」なんて色も粋でいいですね。桜を表す色に「一斤染(いっこんぞめ)」が有るようですが、なんだか違う気がします。やはり桜は「桜色」ですね。
・薄墨 http://www.colordic.org/colorsample/2286.html
・桜鼠 http://www.colordic.org/colorsample/2340.html
・一斤染 http://www.colordic.org/colorsample/2251.html
・桜色 http://www.colordic.org/colorsample/2281.html
肥後煤竹(ひごすすたけ)という色があるのをご存知ですか。「肥後」とか「細川」とかをキーワードにいろいろ調べてきたつもりですが、これは知りませんでした。名前の由来を知りたいところです。着物の色としては結構知られているようですね。もしご存知の方が居られましたら、ご示教下さい。
・肥後煤竹 http://www.colordic.org/colorsample/2403.html
今日は史談会の例会に出かけ先程帰りましたが、あちこちに見える桜はほぼ満開の状態です。
残念ながら風が随分強くなり、夕方から雨になりそうで、お花見を予定されている方には残念なお天気になりそうです。
http://www.colordic.org/w/
桜の季節になりましたが、「薄墨桜」って有名ですね。「岐阜県本巣市(旧・本巣郡根尾村)の淡墨公園にある、樹齢1500年以上のエドヒガンザクラの古木である。花の色が日を追うごとに変わり最後には薄墨色に変わる」(ウィキペディア)という桜だそうですが、一度拝見したいと思いますねー。「薄墨色」ってどんな色なのだろうと思いこのサイトをぐぐって見ると、随分にごった色で随分イメージと違いました。実物はもっと優雅な色合いをしているのでしょう。「桜鼠(さくらねず=pink gray)」なんて色も粋でいいですね。桜を表す色に「一斤染(いっこんぞめ)」が有るようですが、なんだか違う気がします。やはり桜は「桜色」ですね。
・薄墨 http://www.colordic.org/colorsample/2286.html
・桜鼠 http://www.colordic.org/colorsample/2340.html
・一斤染 http://www.colordic.org/colorsample/2251.html
・桜色 http://www.colordic.org/colorsample/2281.html
肥後煤竹(ひごすすたけ)という色があるのをご存知ですか。「肥後」とか「細川」とかをキーワードにいろいろ調べてきたつもりですが、これは知りませんでした。名前の由来を知りたいところです。着物の色としては結構知られているようですね。もしご存知の方が居られましたら、ご示教下さい。
・肥後煤竹 http://www.colordic.org/colorsample/2403.html
今日は史談会の例会に出かけ先程帰りましたが、あちこちに見える桜はほぼ満開の状態です。
残念ながら風が随分強くなり、夕方から雨になりそうで、お花見を予定されている方には残念なお天気になりそうです。

















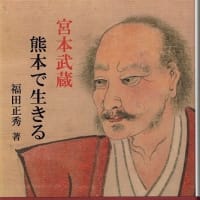







ここ数年で、江戸川橋から明治通りまでの神田川沿いの桜並木が、すっかり桜の名所と化してしまいました。
関口台上の永青文庫から胸突坂(この坂、ブラタモリの早稲田界隈の回で紹介されたようです。)を降りた所に、駒塚橋という橋が架かっていて、神田川を渡った南詰上流側に植わった桜が、何故か毎年、他の桜に2、3日先駆けて開花します。今日はこちらも時折突風が吹いていますが、晴れて気温も高く、昨日は蕾のみだった駒塚橋の先駆け桜が、1日でかなりの花を咲かせました。明後日位には、ほとんどの桜が咲き始める事と思います。
ところで、平川門についてですが、神田川の、神田台開削前の名に由来することもあり、以前から興味を持っていた所、先般詳しく調べるきっかけを作っていただき、今重箱の隅をつついているところです。結構、状況が掴めて来ましたので、もう少しウラをとってからご報告いたします。
ツツミ
幽斎公が慶長12年2月15日に室町家式三巻を進上した事にも永井直勝と共に関わるとされる方です 慶長6年に秀忠公に奉仕し「常に御夜詰に候す 尚祐かってより足の疾あるがゆえに 営にのぼる毎に乗輿して平川口より御臺所のほとりに至ることをゆるさる」と…
尚祐は慶長五年仕官で采地千石を賜る 嫡男古祐(母は瀧川雄利女)は三千石を知行するが末弟の包助の母は継室酒井忠次養女(山岡景友の兄 景佐が実父)であり幕府実力者の後ろ盾か 分家して五千石を知行することになる 「曾我流」の書礼は奥祐筆の必携として伝授されて行く事になる たまたま平川門の事で 曾我兄弟にゆかりの曾我氏が思い浮びました…