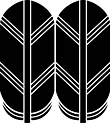去年の大河ドラマを観て「刀伊の来寇」で活躍した藤原隆家の事が気にかかっている。
隆家というよりも、その子孫だという菊池氏の事だと言い換えた方が良いかもしれぬが・・・
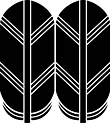
熊本史談会では2022年3月、菊池市在住の歴史家・堤克彦氏をお招きしてー新資料で「菊池氏初代則隆の出自」を探るーという、お話を聞いたが、「土豪説」と「藤原氏後胤説」のいわば合体説とでもいうべき御説の解説であった。
これは堤先生の古文書解析から導かれたものあり、説得力のある御説として受け止めている。
私は菊池氏の藤原隆家後胤説には組しないが、「菊池一族の興亡」の著者・荒木栄司氏がその著の冒頭に、「菊池一族が藤原姓を称し、自分たちが藤原摂関家という王族の血統を色濃く継承した氏族であるという認識を持ち続けた氏族であった、と述べるに止める。」と書かれているが、非常に卓越した表現である。
「藤原氏後胤説」は、その根拠として弘和四年七月の藤原(菊池)武朝の「武朝申代々家業之事」にある一文をもってそう信じられてきた。
謹んで当家忠貞の案内を検するに中の関白道隆4代の後胤太祖大夫将監則隆、
後三条院の御宇延久年中(1069-1073)始めて菊池郡に下向してより以降
武朝に至るまで17代凶徒にくみせず、朝家に奉仕する者なり。
太祖とする則隆からすると、武朝は15代の孫にあたるが、その間このことを証明する一次資料は存在しない。
武朝もまた、そういう認識を持ち続けた人であったのだろう。
菊池氏よりも古い歴史を持つ阿蘇氏にしても、氏族の滅亡は氏族内での主導権争いが原因している。
菊池家では武朝から5代の孫・22代当主能運が一族の宇土爲光(菊池氏19代当主・持朝の子)と戦い、次第に力を失って行き、能運は自らの子を宮崎の山深い西米良村に落ち延びさせた。
菊池姓を秘め米良氏を名乗り近世になると、人吉相良家の附傭となり、交代寄合となった。
南朝の忠臣・10代当主菊池武時の後胤として認められ明治に至り旧姓に復して叙爵された。米良家17代の則忠氏である。
又菊池氏は東北地方に菊地氏の姓で大いに繫栄している。菊地武義という人物の存在が知られているが、肥後菊池氏が「南朝系の後胤やら公家の子息等を守って奥州下向した」ともされるが、未だその関係は明らかではないようだ。
菊池系米良氏の詳細や、東北系菊地氏などの関りなど菊池氏はまだ謎に包まれている。
西米良の米良氏について今年は色々調べてみたいと思っている。










 」という文字が存在するが、私はこちらの文字には一度もであったことがない。
」という文字が存在するが、私はこちらの文字には一度もであったことがない。