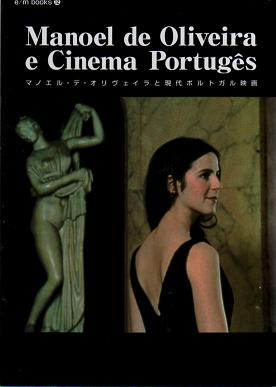先日、『けーし風』読者の集いに出席したら、一坪反戦のYさんにいきなりこの写真集を頂いた。『中電さん、さようなら―山口県祝島 原発とたたかう島人の記録』(那須圭子、創史社、2007年)である。(いつもいろいろとありがとうございます。)
上関町はわりと郷里に近いこともあって、原子力誘致をめぐって様々な軋轢があったことは知っていた。しかし、それ以上に見ようと思わなければ、見えないものだ。その眼を向けると、この写真集はこれまで積極的に知ろうとしない態度をとっつかまえようと待ち構えているようだ。那須氏の先達である写真家・福島菊次郎は、「あのねえ、那須さん。無知であることは罪なの。僕がそうだったからよくわかる。」と語っている。
上関町の事情については、鎌田慧『原発列島を行く』(集英社新書、2001年)に良く整理されている。半島の先っぽに原発予定地の長島がある。しかし、そこは長島に住む人たちの眼に触れることは少なく、むしろその先に浮かぶ祝島と眼と鼻の先という関係になっている。そして、これまで繰り広げられてきた世界は、接待攻撃、カネ=麻薬による患者の増加、それによる地域社会における人間関係の崩壊、不十分な環境影響評価、地方行政の日和り、醜い脅し、強制的な事業着工。どこかで聴いたようなプロセスがここでも行われている。(ところで、『原発列島を行く』には、現厚労大臣がこれまでに行ってきた行動も書かれており興味深い。)
そのようななかで、自分たちの生活権を守るために抵抗し続けている方々の姿が、写真にうつし出されている。取材を通じて得られた「生の声」も、なるほどと思わせることが多い。町長選や町議会選挙では、ずっと賛成6:反対4程度の集票のようだ。しかし、それは個人の声を反映したものではない、と主張している。小さい町なので、賛成とする地域では、反対するとばれてしまい、住んでいけなくなるのだ。それどころか、反対する議員や候補と話をするところを見られただけで、「反対派」と見なされてしまうという。これも、間接民主制の欠陥だろうか。
「するとお婆さんは私の腕を引き寄せて耳打ちした。「わたしら心から賛成しとるわけじゃないんよ。下の者は上の者に何も言えんでしょ。じゃけえ仕方なしにね。」「じゃ、本当は私たちといっしょ?」そう聞くと、お婆さんは黙って大きくうなずいた。そのうえ1年分もあろうかと思える大量の干しワカメまで持たせてくれたのだった。
これは第4章で触れた、あの推進派の元町長のお膝元の白井田での話だ。」