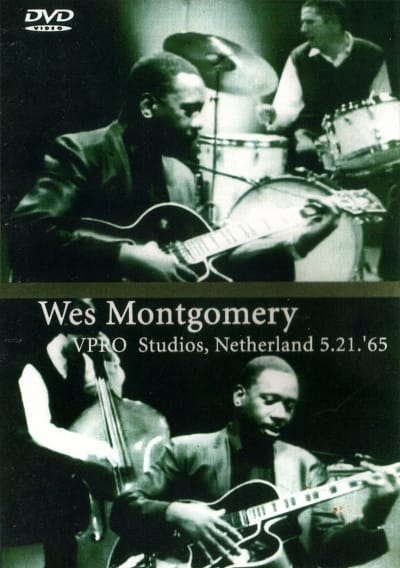伊藤千尋『新版・観光コースでないベトナム』(高文研、2011年)を読む。

ベトナムの近現代史が実体験やルポとともに、よくまとめられている。伊藤千尋氏、さすがである。
日本人にとって、ベトナムとは、食べ物が口に合う国、親近感のある国、それからしばらく置いて、ベトナム戦争があった国。しかし、日本の侵略により、軍隊用の麻袋を作らせられ、食糧生産を圧迫して多くの餓死者が出たことや、ベトナム戦争による景気で潤ったこと、米国のベトナム人虐殺に間接的に加担し続けたこと、沖縄にはベトナム戦争を意識した米軍のジャングル訓練センターがあることなど、どれだけの人が知っているだろう。わたしは断言するが、ベトナムを訪れる現役のビジネスマンの1割もまともな知識を持ってはいない。
ベトナム戦争の終結から40年近くが過ぎようとしているいま、これはもはや過去の歴史なのである。しかし、米国が、屁理屈を付けて(トンキン湾事件など)、自国の利益だけのために(軍事産業や石油利権など)、民間人を無差別に虐殺するという構造、それに日本が追随する構造は、現在の姿そのものだ。また、枯葉剤の被害は現在も止まっていない。
要は、知らなければならない歴史ということである。
●参照
○伊藤千尋『反米大陸』
○ハノイの文廟と美術館
○ハノイの街
○ハノイのレーニン像とあの世の紙幣
○2012年6月、ハノイ
○2012年6月、サパ
○2012年6月、ラオカイ
○『ヴェトナム新時代』、ゾルキー2C
○石川文洋『ベトナム 戦争と平和』
○『米軍は沖縄で枯れ葉剤を使用した!?』
○枯葉剤の現在 『花はどこへ行った』