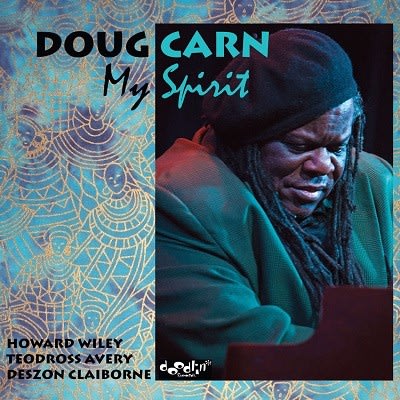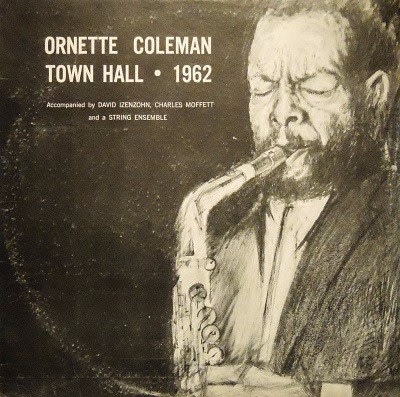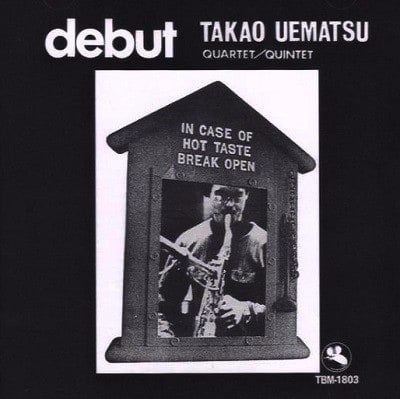上尾のバーバー富士に初めて行った(2017/4/10)。齋藤徹さんのコントラバスソロを観るためである。
テツさんはこのあとヨーロッパに旅立ってしまい、また7月にはミシェル・ドネダ、レ・クアン・ニンの来日、その間はテツさんは加療を控えて空けているのだという。次にソロを観ることができるのはずっと先かもしれないのだ。遠いなんて言っていられないのだ。(それでも東京から1時間でたどり着くことができる。)

齋藤徹 (b)
ファースト・セット、インプロから。静かな弓弾きはまるで環境音であり、やがて、弓と指で弦を撫でさすり、指でコントラバスの胴を撫でさすり、微かな音が層をなして重ねられていく。弓を弾きながらも左手は掌を広げてやはり撫でさすっている。旋律が曲へと移行しても、左手はつねに震え、風にそよぐ叢の音を立てている。
演奏は視覚的なイメージを持つようになっていく。まるで懐かしさのような、遠くからお祭りの音を聴くような、あるいは惜別の感覚のような。テオ・アンゲロプロスの映画に捧げられた曲の断片が聴こえた。足踏みも見せた。
セカンド・セット。いきなり「Django」(ジョン・ルイス)、そして「Lonely Woman」(オーネット・コールマン)。横濱エアジンでの「齋藤徹 plays JAZZ」ではやらなかったジャズナンバーをここで演るのかと驚いた。前者では和声のいろいろな響きを、後者では曲のイメージに負けないよう渾身の力で弦をはじいていた。
次の曲では息遣いと弓弾き・指弾きとが並列に提示された。ノイズを発する棒を使い、弦をはじくのではなく、弦にはじき返される演奏がとても印象的だった。それは高い音、低い音、ノイズを、それぞれ別々の相にあることがわかるままに同時に発した。最後の一音の響きは、菊地雅章のピアノを想起させるほど、多くのものがその和音と不協和の中に含まれていた。
最後に、ふたたびテオ・アンゲロプロスの映画『霧の中の風景』に捧げられた同名の曲。旋律を大事になぞる演奏だった。




Fuji X-E2、Xf35mmF1.4、XF60mm2.4
●齋藤徹
齋藤徹+今井和雄@稲毛Candy(2017年)
齋藤徹 plays JAZZ@横濱エアジン(JazzTokyo)(2017年)
齋藤徹ワークショップ「寄港」第ゼロ回@いずるば(2017年)
りら@七針(2017年)
広瀬淳二+今井和雄+齋藤徹+ジャック・ディミエール@Ftarri(2016年)
齋藤徹『TRAVESSIA』(2016年)
齋藤徹の世界・還暦記念コントラバスリサイタル@永福町ソノリウム(2016年)
かみむら泰一+齋藤徹@キッド・アイラック・アート・ホール(2016年)
齋藤徹+かみむら泰一、+喜多直毅、+矢萩竜太郎(JazzTokyo)(2015-16年)
齋藤徹・バッハ無伴奏チェロ組曲@横濱エアジン(2016年)
うたをさがして@ギャラリー悠玄(2015年)
齋藤徹+類家心平@sound cafe dzumi(2015年)
齋藤徹+喜多直毅+黒田京子@横濱エアジン(2015年)
映像『ユーラシアンエコーズII』(2013年)
ユーラシアンエコーズ第2章(2013年)
バール・フィリップス+Bass Ensemble GEN311『Live at Space Who』(2012年)
ミッシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹@ポレポレ坐(2011年)
齋藤徹による「bass ensemble "弦" gamma/ut」(2011年)
『うたをさがして live at Pole Pole za』(2011年)
齋藤徹『Contrabass Solo at ORT』(2010年)
齋藤徹+今井和雄『ORBIT ZERO』(2009年)
齋藤徹、2009年5月、東中野(2009年)
ミッシェル・ドネダと齋藤徹、ペンタックス43mm(2007年)
往来トリオの2作品、『往来』と『雲は行く』(1999、2000年)
齋藤徹+ミシェル・ドネダ+チョン・チュルギ+坪井紀子+ザイ・クーニン『ペイガン・ヒム』(1999年)
齋藤徹+ミシェル・ドネダ『交感』(1999年)
久高島で記録された嘉手苅林昌『沖縄の魂の行方』、池澤夏樹『眠る女』、齋藤徹『パナリ』(1996年)
ミシェル・ドネダ+アラン・ジュール+齋藤徹『M'UOAZ』(1995年)
ユーラシアン・エコーズ、金石出(1993、1994年)
ジョゼフ・ジャーマン