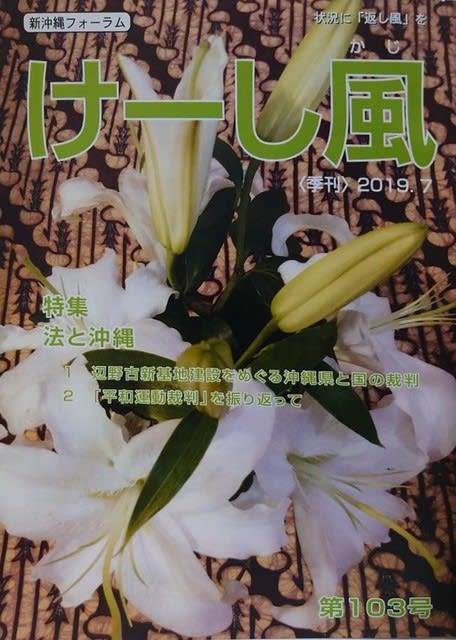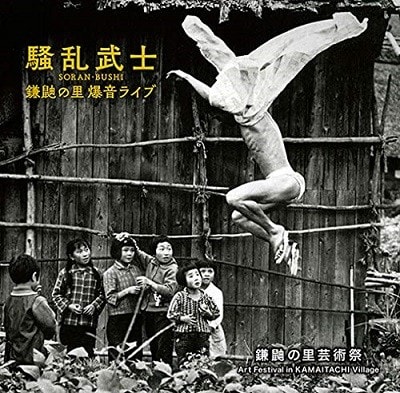昨2018年のマタナ・ロバーツのソロパフォーマンスには痺れた。その後で約束をいただき、インタビューを行った。

(photo by Evan Hunter McKnight)
●マタナ・ロバーツ
2018年ベスト(JazzTokyo)
マタナ・ロバーツ@スーパーデラックス(2018年)
マタナ・ロバーツ「breathe...」@Roulette(2017年)
マタナ・ロバーツ『Coin Coin Chapter Three: River Run Thee』(2015年)
マタナ・ロバーツ『Always.』(2014年)
マタナ・ロバーツ+サム・シャラビ+ニコラス・カロイア『Feldspar』(2011年)
マタナ・ロバーツ『The Chicago Project』(-2007年)
アイレット・ローズ・ゴットリーブ『Internal - External』(2004年)
Sticks and Stonesの2枚、マタナ・ロバーツ『Live in London』(2002、03、11年)