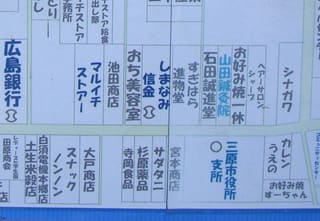数あるワラビ料理の中で一番好きなのがお浸しだ。保存性を高めた佃煮の美味しさを否定するわけではないが、山菜本来の持ち味を楽しむにはこれがいい。
重曹でアクを抜いたワラビを茹でこぼし食べやすい大きさ(5cm程度)に切る。このまま器に盛って削り鰹を振って醤油をかけて食べるのが普通だが、私はもうひと手間かけて出汁醤油にワラビを1時間浸けておく。
淡い旨みを吸ったワラビはシャキシャキの食感で少しヌメリがある。ほのかな苦みが残るワラビをアテにして日本酒を飲むことができるのはあと1ヶ月ほどだ。

重曹でアクを抜いたワラビを茹でこぼし食べやすい大きさ(5cm程度)に切る。このまま器に盛って削り鰹を振って醤油をかけて食べるのが普通だが、私はもうひと手間かけて出汁醤油にワラビを1時間浸けておく。
淡い旨みを吸ったワラビはシャキシャキの食感で少しヌメリがある。ほのかな苦みが残るワラビをアテにして日本酒を飲むことができるのはあと1ヶ月ほどだ。