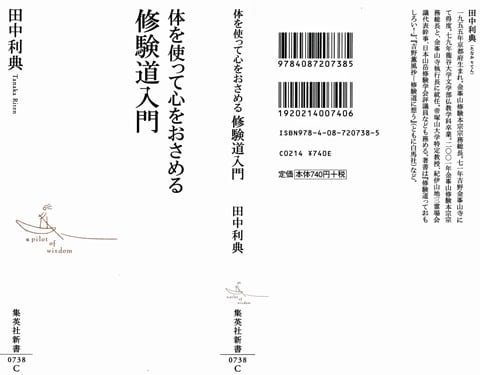金峯山寺長臈(ちょうろう)で、種智院大学客員教授の田中利典(りてん)師が、ご自身のFacebookとブログ「山人のあるがままに」に、こんな文章を載せられた。
「ほんまに朝(5/28)、起きて、勤行をしながら、ふいに思ったことをざーと書いたので、推敲も、原典確認もできていない乱暴なものです。ま、神が降りてきて書いたものということで…」ということだが、これだけの文章を「ふいに思ったことをざーと」書けるということ自体が、すごい。長文なので、まずは抜粋版を紹介し、最後に全文を紹介させていただく。
Ⅰ.仏教の普遍性について(tetsudaによる抜粋版)
仏教とは仏の教えである。仏(釈尊=お釈迦さま)が説いた教えである。そして私が仏となる教えである…という範疇を出ない。で、そこを根底に2500年間、さまざまな先人が出て、仏教を継承・発展させてきた。その継承発展こそが、仏教を世界三大宗教になさしめたのである。釈尊本来の仏教というなら、インドではとうの昔に死滅しているのだ。
釈尊が開いた仏教が各地につたわり、それぞれの風土や民族、歴史の違いの中で、なお、仏教として信仰され、根付いて来たことこそが、仏教なのだと私は思っている。
日本に伝わる仏教は、伝来当時にすでに日本古来の信仰である神道とある種の融合がうまれ、その後には神仏習合、本地垂迹説などが興って、神と仏は共存してきたのである。
現代の日本仏教界最高峰の碩学といえる高野山真言宗の松長有慶師とダライラマ法王との象徴的な面白いやりとりがある(2016年紀伊山地三霊場会議フォーラム)。
(以下「」内は松長有慶師の話)「仏教では一切衆生と言います。日本人は石ころでも命あるものとする。山や川も全て命があり、尊崇する。それがまさに自然観だろうと思うのです。しかし、そういう話をすると、いろいろな点で話が合うところと合わないところがあるのです。その点をダライ・ラマは非常に嫌っているのですね」。
「日本仏教、特に平安仏教は、天台でも真言でも、そういう意味では一切のものの中に命が含まれている。そして、天地万物が自然環境に根付き、全てのものがそれぞれ命を持っていて、自分の命と同じなのだという考え方がある。この話をすると、ダライ・ラマは『違う』と言うのです。やはり命があるのは人間であり、動物までだということです」。
「そういう議論をしてその後物別れになったのですが、それから1年ほど経ってまた日本に来られ、一緒にお昼を食べながら話しました。この前あなたが言っていた石ころにも命があるという考え方は、神道の考え方だなと言った。勉強してきたのですね」。
キリスト教、イスラム教という世界宗教は自分たちの持った普遍性を全世界に広めようとする教えである。であるから、その土地や国が持ってきた歴史や風土を破壊して、自分たちの宗教だけを広めてきたきらいがある。
仏教は同じ世界宗教と言うが、それぞれの土地や国や風土を打ち壊して打ち立てるのではなく、うまく融合して、その土地土地に根ざした信仰を育んできたといってもよいだろう。
現状の葬式仏教には、糾弾されるべき点はごまんとある。寺族(じぞく=住職の家族)による寺院の私物化をはじめ、僧侶の質の低下、葬式自体の形骸化と信仰心の希薄化などなど、数え上げればきりがない。だからといって、あんなものは仏教ではないというなら、釈迦滅後、本来の仏教などというものはこの世にそんなものは存在していないことになる、と私は思う。
しかし仏教は厳然と今も存在し、多くの人々の生きる支えとなっている。また日本でも葬儀という厳粛なる場を通じて、やはり仏教の持つ大きな力が人々の生きる支えを担う部分もゼロなどでは決してないわけだ。私は仏教が2500年にわたって持ち得た歴史自体が人類の叡智なのだと考えていて、そういう叡智が世界宗教としての仏教を仏教ならしめてきたといってもよいだろうと思っている。
いかがだろう? 今まで「山川草木悉有仏性」はおシャカさまの教えだと固く信じ込んでいたが、これが神道と結びついた日本独特の思想だったとは!
「葬式仏教」と言って仏教界全体をおとしめるような人がいるが、ではその人は、お葬式を挙げてもらわなくて良いというのだろうか。
私は日本人の信仰心の根底にあるのは「祖霊信仰」(祖先崇拝、先祖祭祀とも)だと思っている。仏教は「祖霊信仰」と親和的な宗教なので、神道的な考えを取り入れながら約1,500年の長きにわた、信仰され続けてきたのだろう。
いろんなことを考えるヒントをいただいたのが「仏教の普遍性について」だった。利典師、有り難うございました。皆さん、以下の「記事全文」も、ぜひお読みください!
Ⅱ.仏教の普遍性について(利典師の書かれた全文)
仏教はいまから2500年ほど前にインドのゴータマ・シッダッタ(釈迦族から出た聖者という意味で「釈尊」と尊称される)が覚者(悟りを開く)となって開かれた宗教である。そのひろがりはキリスト教・イスラム教とならんで、世界三大宗教という。
仏教はインドでは早い段階で死滅する。今もわずかである。ないとは言えないが、インド全土では仏教とは1%にも満たない。しかし釈尊が説いた法は、その金口説(こくんじきせつ=お釈迦さまご自身の説法)に近い原型を伝えるテーラワーダ(上座部仏教=小乗仏教)系が南伝して、スリランカやタイ、ミヤンマーなどに根付いて、今も国教に近い形で多くの人々の信仰を得ている。
ダライ・ラマ法王をいただくチベット仏教も、中期後期密教の教義を包含しつつもインド純粋のテーラワーダの思想を根底にしている部分も大きいと思われる(ここはちょっと怪しいかも…)。
かたや、釈尊が入滅して500年ほど経った頃から起こったいわば宗教革命的要素で、大乗仏教系の経典が次々と編纂され、般若思想や浄土教や密教などの新しい仏教運動を生みつつ北伝して、中国、韓国、そして日本へと伝えられてきた。おおまかな流れなので、齟齬がたくさんあるが、まあ、一般的にはこんな仏教の変遷といってもよいだろう。
さて最近、日本の仏教の現状を捉えて「釈迦本来の仏教とは似ても似つかぬ非なるもので、葬式仏教など噴飯ものだ」という論がまさに正論のように語られる風潮がある。たしかに江戸時代に寺請け制度の下、日本の大方の寺院は檀家制度に組み入れられて、葬式仏教を育んできた。いま、その葬儀の現状が音と立てて変容を遂げるその論理を支える正論が、一つはそういう「本来の仏教ではない」という論調だろう。
では本来の仏教とはなんだ。仏教とは仏の教えである。仏(釈尊)が説いた教えである。そして私が仏となる教えである…という範疇を出ない。で、そこを根底に2500年間、さまざまな先人が出て、仏教を継承・発展させてきた。その継承発展こそが、仏教を世界三大宗教になさしめたのである。釈尊本来の仏教というなら、インドではとうの昔に死滅しているのだ。
釈尊が開いた仏教が各地につたわり、それぞれの風土や民族、歴史の違いの中で、なお、仏教として信仰され、根付いて来たことこそが、仏教なのだと私は思っている。
そういう意味では、6世紀半ばに公式に日本に伝わる仏教は、伝来当時にすでに日本古来の信仰である神道とある種の融合がうまれ、その後には神仏習合、本地垂迹説などが興って、神と仏は共存してきたのである。仏教本来からいうなら、日本の仏教は釈尊が説いた仏教からは遠く離れて、神道教といってもよいかもしれない。ちょっと言い過ぎた、神道と融合した仏教っていうくらいにしておこう。
現代の日本仏教界最高峰の碩学といえる高野山真言宗の松長有慶師とダライラマ法王との象徴的な面白いやりとりがある。以下、引用をする。
… ダライ・ラマ法王とは集まりの時に環境問題についての話をしました。日本人は、ものの中にも命を認める考え方を持っている。人間の道具としてものを使うのではなく、ものを命あるものとする、お互いの命の連関の中で環境問題を考えないといけない、という話です。
仏教では一切衆生と言います。日本人は石ころでも命あるものとする。山や川も全て命があり、尊崇する。それがまさに自然観だろうと思うのです。しかし、そういう話をすると、いろいろな点で話が合うところと合わないところがあるのです。その点をダライ・ラマは非常に嫌っているのですね。
あの方は、自分がインド仏教のナーランダの伝統を継いでいるのだというプライドを持っておられます。だから、インドのものの考え方をする。よく考えてみると、仏教が中国に来て、動物と植物を衆生に含めるかどうか、一切衆生悉有仏性について、中国人は盛んに議論しているのです。
インド人は、動物、植物は命を持たないものだと考えます。しかし中国では、動物までは認めるけれども植物は認めない、あるいは動物も植物も認めるのか、そういう議論があるのです。
しかし、それが一番盛んに論じられたのは日本仏教です。ですから、日本仏教、特に平安仏教は、天台でも真言でも、そういう意味では一切のものの中に命が含まれている。そして、天地万物が自然環境に根付き、全てのものがそれぞれ命を持っていて、自分の命と同じなのだという考え方がある。この話をすると、ダライ・ラマは「違う」と言うのです。やはり命があるのは人間であり、動物までだということです。
そういう議論をしてその後物別れになったのですが、それから1年ほど経ってまた日本に来られ、一緒にお昼を食べながら話しました。この前あなたが言っていた石ころにも命があるという考え方は、神道の考え方だなと言った。勉強してきたのですね。日本の仏教をそれなりに勉強してきたのです。ですから結局、仏教もそういう考えを持っていた。山や川といった命がないと思われるような全ての存在が命を持つという考えは、やはり日本に来て一番盛んになってきた。(2016年紀伊山地三霊場会議フォーラムより)
本稿では仏教の普遍性について話をしている。キリスト教、イスラム教という世界宗教は自分たちの持った普遍性を全世界に広めようとする教えである。であるから、その土地や国が持ってきた歴史や風土を破壊して、自分たちの宗教だけを広めてきたきらいがある。
いま世界を席巻しているグローバルリズムやISのイスラム原理主義っていうのは、そういうキリスト教、イスラム教が持っている価値観を基盤としているところがあるのではないだろうか。
その点、仏教は同じ世界宗教と言うが、それぞれの土地や国や風土を打ち壊して打ち立てるのではなく、うまく融合して、その土地土地に根ざした信仰を育んできたといってもよいだろう。どちらに本当の普遍性があるのか?そこのところを考えないとこれからの世界はますます困ったことになるように私は思っている。
現状の葬式仏教には、糾弾されるべき点はごまんとある。寺族(じぞく=住職の家族)による寺院の私物化をはじめ、僧侶の質の低下、葬式自体の形骸化と信仰心の希薄化などなど、数え上げればきりがない。
だからといって、あんなものは仏教ではないというなら、釈迦滅後、本来の仏教などというものはこの世にそんなものは存在していないことになる、と私は思う。ダライラマ法王の説く仏教だって、釈迦が聞いたらひっくり返るかもしれない。「わしゃ、そんなこと言うとらん」とのたまうかも知れないのである。
しかし仏教は厳然と今も存在し、多くの人々の生きる支えとなっている。また日本でも葬儀という厳粛なる場を通じて、やはり仏教の持つ大きな力が人々の生きる支えを担う部分もゼロなどでは決してないわけだ。
私は仏教が2500年にわたって持ち得た歴史自体が人類の叡智なのだと考えていて、そういう叡智が世界宗教としての仏教を仏教ならしめてきたといってもよいだろうと思っている。
あっちこっちに話が行って、味噌も糞もごった煮の話になってしまったが、ふと、朝からそんなことを思いついて、筆を走らせてみた。つっこみどころ満載である。それは私の不徳でしかない。多くの叱責が予想されるので、前もってお詫びをしておく。
「ほんまに朝(5/28)、起きて、勤行をしながら、ふいに思ったことをざーと書いたので、推敲も、原典確認もできていない乱暴なものです。ま、神が降りてきて書いたものということで…」ということだが、これだけの文章を「ふいに思ったことをざーと」書けるということ自体が、すごい。長文なので、まずは抜粋版を紹介し、最後に全文を紹介させていただく。
Ⅰ.仏教の普遍性について(tetsudaによる抜粋版)
仏教とは仏の教えである。仏(釈尊=お釈迦さま)が説いた教えである。そして私が仏となる教えである…という範疇を出ない。で、そこを根底に2500年間、さまざまな先人が出て、仏教を継承・発展させてきた。その継承発展こそが、仏教を世界三大宗教になさしめたのである。釈尊本来の仏教というなら、インドではとうの昔に死滅しているのだ。
釈尊が開いた仏教が各地につたわり、それぞれの風土や民族、歴史の違いの中で、なお、仏教として信仰され、根付いて来たことこそが、仏教なのだと私は思っている。
日本に伝わる仏教は、伝来当時にすでに日本古来の信仰である神道とある種の融合がうまれ、その後には神仏習合、本地垂迹説などが興って、神と仏は共存してきたのである。
現代の日本仏教界最高峰の碩学といえる高野山真言宗の松長有慶師とダライラマ法王との象徴的な面白いやりとりがある(2016年紀伊山地三霊場会議フォーラム)。
(以下「」内は松長有慶師の話)「仏教では一切衆生と言います。日本人は石ころでも命あるものとする。山や川も全て命があり、尊崇する。それがまさに自然観だろうと思うのです。しかし、そういう話をすると、いろいろな点で話が合うところと合わないところがあるのです。その点をダライ・ラマは非常に嫌っているのですね」。
「日本仏教、特に平安仏教は、天台でも真言でも、そういう意味では一切のものの中に命が含まれている。そして、天地万物が自然環境に根付き、全てのものがそれぞれ命を持っていて、自分の命と同じなのだという考え方がある。この話をすると、ダライ・ラマは『違う』と言うのです。やはり命があるのは人間であり、動物までだということです」。
「そういう議論をしてその後物別れになったのですが、それから1年ほど経ってまた日本に来られ、一緒にお昼を食べながら話しました。この前あなたが言っていた石ころにも命があるという考え方は、神道の考え方だなと言った。勉強してきたのですね」。
キリスト教、イスラム教という世界宗教は自分たちの持った普遍性を全世界に広めようとする教えである。であるから、その土地や国が持ってきた歴史や風土を破壊して、自分たちの宗教だけを広めてきたきらいがある。
仏教は同じ世界宗教と言うが、それぞれの土地や国や風土を打ち壊して打ち立てるのではなく、うまく融合して、その土地土地に根ざした信仰を育んできたといってもよいだろう。
現状の葬式仏教には、糾弾されるべき点はごまんとある。寺族(じぞく=住職の家族)による寺院の私物化をはじめ、僧侶の質の低下、葬式自体の形骸化と信仰心の希薄化などなど、数え上げればきりがない。だからといって、あんなものは仏教ではないというなら、釈迦滅後、本来の仏教などというものはこの世にそんなものは存在していないことになる、と私は思う。
しかし仏教は厳然と今も存在し、多くの人々の生きる支えとなっている。また日本でも葬儀という厳粛なる場を通じて、やはり仏教の持つ大きな力が人々の生きる支えを担う部分もゼロなどでは決してないわけだ。私は仏教が2500年にわたって持ち得た歴史自体が人類の叡智なのだと考えていて、そういう叡智が世界宗教としての仏教を仏教ならしめてきたといってもよいだろうと思っている。
 | 体を使って心をおさめる 修験道入門 |
| 田中利典 | |
| 集英社新書 |
いかがだろう? 今まで「山川草木悉有仏性」はおシャカさまの教えだと固く信じ込んでいたが、これが神道と結びついた日本独特の思想だったとは!
「葬式仏教」と言って仏教界全体をおとしめるような人がいるが、ではその人は、お葬式を挙げてもらわなくて良いというのだろうか。
私は日本人の信仰心の根底にあるのは「祖霊信仰」(祖先崇拝、先祖祭祀とも)だと思っている。仏教は「祖霊信仰」と親和的な宗教なので、神道的な考えを取り入れながら約1,500年の長きにわた、信仰され続けてきたのだろう。
いろんなことを考えるヒントをいただいたのが「仏教の普遍性について」だった。利典師、有り難うございました。皆さん、以下の「記事全文」も、ぜひお読みください!
Ⅱ.仏教の普遍性について(利典師の書かれた全文)
仏教はいまから2500年ほど前にインドのゴータマ・シッダッタ(釈迦族から出た聖者という意味で「釈尊」と尊称される)が覚者(悟りを開く)となって開かれた宗教である。そのひろがりはキリスト教・イスラム教とならんで、世界三大宗教という。
仏教はインドでは早い段階で死滅する。今もわずかである。ないとは言えないが、インド全土では仏教とは1%にも満たない。しかし釈尊が説いた法は、その金口説(こくんじきせつ=お釈迦さまご自身の説法)に近い原型を伝えるテーラワーダ(上座部仏教=小乗仏教)系が南伝して、スリランカやタイ、ミヤンマーなどに根付いて、今も国教に近い形で多くの人々の信仰を得ている。
ダライ・ラマ法王をいただくチベット仏教も、中期後期密教の教義を包含しつつもインド純粋のテーラワーダの思想を根底にしている部分も大きいと思われる(ここはちょっと怪しいかも…)。
かたや、釈尊が入滅して500年ほど経った頃から起こったいわば宗教革命的要素で、大乗仏教系の経典が次々と編纂され、般若思想や浄土教や密教などの新しい仏教運動を生みつつ北伝して、中国、韓国、そして日本へと伝えられてきた。おおまかな流れなので、齟齬がたくさんあるが、まあ、一般的にはこんな仏教の変遷といってもよいだろう。
さて最近、日本の仏教の現状を捉えて「釈迦本来の仏教とは似ても似つかぬ非なるもので、葬式仏教など噴飯ものだ」という論がまさに正論のように語られる風潮がある。たしかに江戸時代に寺請け制度の下、日本の大方の寺院は檀家制度に組み入れられて、葬式仏教を育んできた。いま、その葬儀の現状が音と立てて変容を遂げるその論理を支える正論が、一つはそういう「本来の仏教ではない」という論調だろう。
では本来の仏教とはなんだ。仏教とは仏の教えである。仏(釈尊)が説いた教えである。そして私が仏となる教えである…という範疇を出ない。で、そこを根底に2500年間、さまざまな先人が出て、仏教を継承・発展させてきた。その継承発展こそが、仏教を世界三大宗教になさしめたのである。釈尊本来の仏教というなら、インドではとうの昔に死滅しているのだ。
釈尊が開いた仏教が各地につたわり、それぞれの風土や民族、歴史の違いの中で、なお、仏教として信仰され、根付いて来たことこそが、仏教なのだと私は思っている。
そういう意味では、6世紀半ばに公式に日本に伝わる仏教は、伝来当時にすでに日本古来の信仰である神道とある種の融合がうまれ、その後には神仏習合、本地垂迹説などが興って、神と仏は共存してきたのである。仏教本来からいうなら、日本の仏教は釈尊が説いた仏教からは遠く離れて、神道教といってもよいかもしれない。ちょっと言い過ぎた、神道と融合した仏教っていうくらいにしておこう。
現代の日本仏教界最高峰の碩学といえる高野山真言宗の松長有慶師とダライラマ法王との象徴的な面白いやりとりがある。以下、引用をする。
… ダライ・ラマ法王とは集まりの時に環境問題についての話をしました。日本人は、ものの中にも命を認める考え方を持っている。人間の道具としてものを使うのではなく、ものを命あるものとする、お互いの命の連関の中で環境問題を考えないといけない、という話です。
仏教では一切衆生と言います。日本人は石ころでも命あるものとする。山や川も全て命があり、尊崇する。それがまさに自然観だろうと思うのです。しかし、そういう話をすると、いろいろな点で話が合うところと合わないところがあるのです。その点をダライ・ラマは非常に嫌っているのですね。
あの方は、自分がインド仏教のナーランダの伝統を継いでいるのだというプライドを持っておられます。だから、インドのものの考え方をする。よく考えてみると、仏教が中国に来て、動物と植物を衆生に含めるかどうか、一切衆生悉有仏性について、中国人は盛んに議論しているのです。
インド人は、動物、植物は命を持たないものだと考えます。しかし中国では、動物までは認めるけれども植物は認めない、あるいは動物も植物も認めるのか、そういう議論があるのです。
しかし、それが一番盛んに論じられたのは日本仏教です。ですから、日本仏教、特に平安仏教は、天台でも真言でも、そういう意味では一切のものの中に命が含まれている。そして、天地万物が自然環境に根付き、全てのものがそれぞれ命を持っていて、自分の命と同じなのだという考え方がある。この話をすると、ダライ・ラマは「違う」と言うのです。やはり命があるのは人間であり、動物までだということです。
そういう議論をしてその後物別れになったのですが、それから1年ほど経ってまた日本に来られ、一緒にお昼を食べながら話しました。この前あなたが言っていた石ころにも命があるという考え方は、神道の考え方だなと言った。勉強してきたのですね。日本の仏教をそれなりに勉強してきたのです。ですから結局、仏教もそういう考えを持っていた。山や川といった命がないと思われるような全ての存在が命を持つという考えは、やはり日本に来て一番盛んになってきた。(2016年紀伊山地三霊場会議フォーラムより)
本稿では仏教の普遍性について話をしている。キリスト教、イスラム教という世界宗教は自分たちの持った普遍性を全世界に広めようとする教えである。であるから、その土地や国が持ってきた歴史や風土を破壊して、自分たちの宗教だけを広めてきたきらいがある。
いま世界を席巻しているグローバルリズムやISのイスラム原理主義っていうのは、そういうキリスト教、イスラム教が持っている価値観を基盤としているところがあるのではないだろうか。
その点、仏教は同じ世界宗教と言うが、それぞれの土地や国や風土を打ち壊して打ち立てるのではなく、うまく融合して、その土地土地に根ざした信仰を育んできたといってもよいだろう。どちらに本当の普遍性があるのか?そこのところを考えないとこれからの世界はますます困ったことになるように私は思っている。
現状の葬式仏教には、糾弾されるべき点はごまんとある。寺族(じぞく=住職の家族)による寺院の私物化をはじめ、僧侶の質の低下、葬式自体の形骸化と信仰心の希薄化などなど、数え上げればきりがない。
だからといって、あんなものは仏教ではないというなら、釈迦滅後、本来の仏教などというものはこの世にそんなものは存在していないことになる、と私は思う。ダライラマ法王の説く仏教だって、釈迦が聞いたらひっくり返るかもしれない。「わしゃ、そんなこと言うとらん」とのたまうかも知れないのである。
しかし仏教は厳然と今も存在し、多くの人々の生きる支えとなっている。また日本でも葬儀という厳粛なる場を通じて、やはり仏教の持つ大きな力が人々の生きる支えを担う部分もゼロなどでは決してないわけだ。
私は仏教が2500年にわたって持ち得た歴史自体が人類の叡智なのだと考えていて、そういう叡智が世界宗教としての仏教を仏教ならしめてきたといってもよいだろうと思っている。
あっちこっちに話が行って、味噌も糞もごった煮の話になってしまったが、ふと、朝からそんなことを思いついて、筆を走らせてみた。つっこみどころ満載である。それは私の不徳でしかない。多くの叱責が予想されるので、前もってお詫びをしておく。