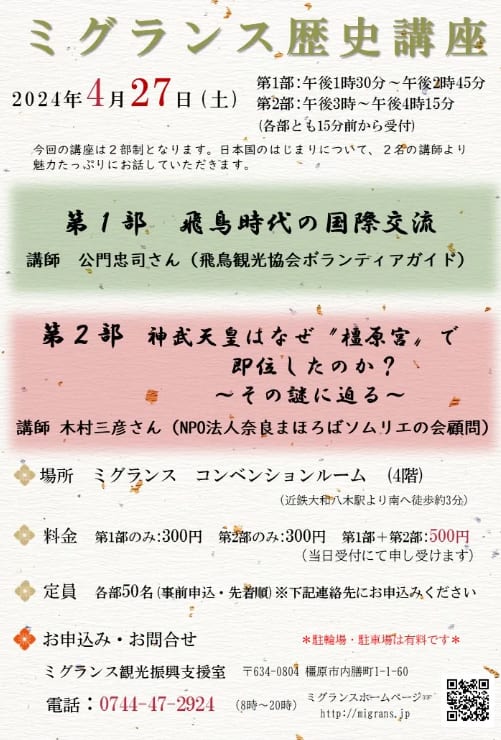昨年(2023年10月8日)、谷村新司さんがお亡くなりになった。そのあと各チャンネルが追悼番組を放送していたので、よく見ていた。谷村さんは私より5歳上(1948年=昭和23年生まれ)なのだが、ずいぶん老けて見えた、こんなおじいさんだったのか…。
それが歴然としたのが、加山雄三さん(1937年=昭和12年生まれ)と共演していた番組だった。11歳上の加山さんの方が、よほど若く見えた。肌の色艶とか声の張りとか…。
そのあと、書店で見つけたのが和田秀樹著『60代からの見た目の壁』だった。帯には〈人は中身よりまず「外見」〉〈60代からは「見た目が10割」〉〈60代以降で一気に広がる見た目格差を埋めて 10歳若く見える方法〉。
「うーん。シニア世代には、外見って大事なのだな」と思って本書を買い、一気に読んだ。その内容を紹介したのが、奈良新聞「明風清音」(2024.3.21 付)〈シニアは見た目が10割〉だ。以下、全文を紹介する。
シニアは見た目が10割
私は満70歳だが、周囲を見回すと、どうやら人は60歳代から外見が大きく変化するようだ。何となくそのように感じているとき、和田秀樹著『60代からの見た目の壁』(エクスナレッジ刊)を読んだ。かつて『人は見た目が9割』(新潮新書)というベストセラーがあったが、本書によれば、60歳代以上は見た目が「10割」なのだそうだ。
版元の紹介文には、〈見た目は寿命の長さにも影響する/粗食は見た目年齢を上げ、健康も損なう/65歳過ぎたら「健康至上主義」と決別せよ/知性こそ見た目を引き立てる妙薬〉〈どうせあと数十年しか生きられないのだから、おしゃれして、お化粧して、人生をいっぱい楽しまないと損!その意欲こそが、見た目年齢の壁を打ち破る秘訣なのです〉。本書の要点を、以下に紹介する。
▼男性は「スーツ」で若見え
見た目を若くするには、おしゃれをすることが大切だそうだ。退職して〈スーツをやめて、外出するときも、ポロシャツとかセーターを着て歩くようになると、人から見られているという緊張感がなくなるのか、表情もだらしなくなり、老け込んで見える男性が多いように思います。年をとって一番老けて見えないかっこうは、男性なら断然スーツだと私は考えています〉。
▼「ファッション」にお金を
〈男性の場合、若い頃はどんなに汚いかっこうをしていても、モテるやつはモテるものです。ボロボロのジーンズをはいていても、かっこいいやつはかっこいい。だけど、年をとるとそうはいかなくなるのです。逆に、それなりの年齢になったと自覚できれば、ファッションをはじめ、外から補っていくようにしないと、見た目のかっこよさは維持できません。だから、人は年をとるとよいものを持とうとするのです〉。
▼見た目が若返る食べもの
「高齢者は粗食にしたほうが健康に良い」という俗説があるが、これは間違いで、見た目年齢が老けている人は、たんぱく質が足りていないのだそうだ。
〈粗食とは、朝はごはんにみそ汁、納豆、漬けもの。昼はそばかうどん、夏ならそうめん。夜は焼き魚と野菜の煮物、冬なら鍋もの、といったイメージです。(中略)今例にあげたメニューは、たんぱく質が圧倒的に不足しています〉。
本書では〈肉を食べないと身長が伸びない〉〈肉を食べないとがんのリスクが上がる〉〈たんぱく質が足りないとシワが増える〉などと指摘されている。
▼「知性」は顔ににじみ出る
〈見た目が若く見える要素の1つに、私は「知性」があると思っています。知性は顔ににじみ出ると言いますが、知性のある顔つきは、若く見えるというよりも、見た目を引き立てる大事な要素といったほうがいいかも知れません。ではどういう会話をする人が知的に見えるのかというと、「人生経験が長いからこそ知っていること」を話せるかどうかということになるでしょう〉。
▼意欲が見た目をよくする
〈一番大事なことは、「若くありたい」という意欲を捨てないこと。(中略)意欲をつかさどる脳の前頭葉は、40代くらいから少しずつ萎縮していきます。意欲は外見にもっとも影響を与えるので、意欲を失わないような生活を心がける必要があるというわけです。そして、前頭葉の老化を防いで、意欲が低下しないようにするには、見た目をよくすることが大事です。
(中略)見た目というと、つい若くしないといけないように思ってしまいますが、60歳を過ぎたら、自己演出が必要だということ。自分をどんなふうに見せたら一番かっこよく見えるのか、そういう演出をしたほうがよいということです〉。
「見た目が10割」と言われると自信をなくすが、要は「いつも見られている」ということを意識せよ、ということなのだ。それなら、実行できそうだ。(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)

それが歴然としたのが、加山雄三さん(1937年=昭和12年生まれ)と共演していた番組だった。11歳上の加山さんの方が、よほど若く見えた。肌の色艶とか声の張りとか…。
そのあと、書店で見つけたのが和田秀樹著『60代からの見た目の壁』だった。帯には〈人は中身よりまず「外見」〉〈60代からは「見た目が10割」〉〈60代以降で一気に広がる見た目格差を埋めて 10歳若く見える方法〉。
「うーん。シニア世代には、外見って大事なのだな」と思って本書を買い、一気に読んだ。その内容を紹介したのが、奈良新聞「明風清音」(2024.3.21 付)〈シニアは見た目が10割〉だ。以下、全文を紹介する。
シニアは見た目が10割
私は満70歳だが、周囲を見回すと、どうやら人は60歳代から外見が大きく変化するようだ。何となくそのように感じているとき、和田秀樹著『60代からの見た目の壁』(エクスナレッジ刊)を読んだ。かつて『人は見た目が9割』(新潮新書)というベストセラーがあったが、本書によれば、60歳代以上は見た目が「10割」なのだそうだ。
版元の紹介文には、〈見た目は寿命の長さにも影響する/粗食は見た目年齢を上げ、健康も損なう/65歳過ぎたら「健康至上主義」と決別せよ/知性こそ見た目を引き立てる妙薬〉〈どうせあと数十年しか生きられないのだから、おしゃれして、お化粧して、人生をいっぱい楽しまないと損!その意欲こそが、見た目年齢の壁を打ち破る秘訣なのです〉。本書の要点を、以下に紹介する。
▼男性は「スーツ」で若見え
見た目を若くするには、おしゃれをすることが大切だそうだ。退職して〈スーツをやめて、外出するときも、ポロシャツとかセーターを着て歩くようになると、人から見られているという緊張感がなくなるのか、表情もだらしなくなり、老け込んで見える男性が多いように思います。年をとって一番老けて見えないかっこうは、男性なら断然スーツだと私は考えています〉。
▼「ファッション」にお金を
〈男性の場合、若い頃はどんなに汚いかっこうをしていても、モテるやつはモテるものです。ボロボロのジーンズをはいていても、かっこいいやつはかっこいい。だけど、年をとるとそうはいかなくなるのです。逆に、それなりの年齢になったと自覚できれば、ファッションをはじめ、外から補っていくようにしないと、見た目のかっこよさは維持できません。だから、人は年をとるとよいものを持とうとするのです〉。
▼見た目が若返る食べもの
「高齢者は粗食にしたほうが健康に良い」という俗説があるが、これは間違いで、見た目年齢が老けている人は、たんぱく質が足りていないのだそうだ。
〈粗食とは、朝はごはんにみそ汁、納豆、漬けもの。昼はそばかうどん、夏ならそうめん。夜は焼き魚と野菜の煮物、冬なら鍋もの、といったイメージです。(中略)今例にあげたメニューは、たんぱく質が圧倒的に不足しています〉。
本書では〈肉を食べないと身長が伸びない〉〈肉を食べないとがんのリスクが上がる〉〈たんぱく質が足りないとシワが増える〉などと指摘されている。
▼「知性」は顔ににじみ出る
〈見た目が若く見える要素の1つに、私は「知性」があると思っています。知性は顔ににじみ出ると言いますが、知性のある顔つきは、若く見えるというよりも、見た目を引き立てる大事な要素といったほうがいいかも知れません。ではどういう会話をする人が知的に見えるのかというと、「人生経験が長いからこそ知っていること」を話せるかどうかということになるでしょう〉。
▼意欲が見た目をよくする
〈一番大事なことは、「若くありたい」という意欲を捨てないこと。(中略)意欲をつかさどる脳の前頭葉は、40代くらいから少しずつ萎縮していきます。意欲は外見にもっとも影響を与えるので、意欲を失わないような生活を心がける必要があるというわけです。そして、前頭葉の老化を防いで、意欲が低下しないようにするには、見た目をよくすることが大事です。
(中略)見た目というと、つい若くしないといけないように思ってしまいますが、60歳を過ぎたら、自己演出が必要だということ。自分をどんなふうに見せたら一番かっこよく見えるのか、そういう演出をしたほうがよいということです〉。
「見た目が10割」と言われると自信をなくすが、要は「いつも見られている」ということを意識せよ、ということなのだ。それなら、実行できそうだ。(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)