
スマホで撮った写真
『紫式部』清水好子(岩波新書1973年4月28日第1刷、2024年4月19日第18刷)
■ 『散華 紫式部の生涯 上 下』(中央公論社1991年)の著者・杉本苑子さんはあとがきで清水好子さんの『紫式部』(岩波新書)に触れ、啓発される所が多かった、と書いていた。それで、いつか読もうと思っていた。先日、松本の丸善で買い求めて、読んだ。
帯に**クラシックス 限定復刊 往年の赤版、青版、黄版から厳選**とある。このことから、本書が名著であることがわかる。
本書の章立ては次の通り。
序章
第一章 娘時代
第二章 旅
第三章 結婚
第四章 宮仕え
第五章 源氏物語の執筆
終章
鳴き弱る籬(まがき)の虫もとめがたき秋の別れや悲しかるらむ(9頁) 夜更けに別れを告げにきた友人に対して、別れを惜しだ歌。この歌を清水さんは次のように読み解く。
**止(とど)めがたく秋は去り、夜が明けると冬の朝になっていた。そのように、友の別れも止めがたい。涸れがれの虫の声も悲しいのか、声を振り絞って鳴く。「虫も」といったのは、自分も声が涸れるほど泣いたということをあらわにいわぬためである。「も」がそのような働きをする。折からの景物に託し、比喩がひとつひとつ、現実の人間関係や心情に符合して、まともな稽古の跡が見える歌である。**(11頁)
**友だちと、その離別が数多く歌われているのが式部の娘時代の歌の特色であり、そこに私たちは、彼女が青春時代とは何かということを正確に摑んでいたことを、また、青春の核心がいつの時代にも不変であることを知るのである。**(12頁)
長々と引用したが、このように清水さんは「紫式部集」に収録されている和歌を丁寧に読み解き、紫式部の生涯をたどる。
「そうなのか、このことばにはそんな意味が込められているのか・・・」と、読んでいて、何回も思った。清水さんが優れた研究者であったことが窺える、紫式部論。
以下私的メモ
第五章の「源氏物語の執筆」に次のようなことが書かれている。**薫と匂の宮の二人から逃れて尼になった浮舟が、夢の浮橋の巻で、薫にその存在を知られた段階で物語の終る意味が、浮舟の尼生活さえも、大政治家に成長した権門薫によって庇護され維持されることを暗示しているとしたら、作者は女の生き方について、すこしも曖昧な目測をしていなかったことが解るのである。**(171頁)
塩尻市広丘の「えんてらす」で今年(2024年)7月11日に行われた堀井正子さんの講演会(過去ログ)で、堀井さんに好きなヒロインを尋ねた。その際、私は「浮舟はどうでしょう」と尋ねた。堀井さんは答えの最後に「浮舟は尼として生きていけるのかな?「夢浮橋」ですからね・・・」という意味内容のコメントをされた。少し釈然としなかったが、上掲したように、同じような見解を清水さんが示していることに驚いた。
浮舟の生き方について再考を求められたように思う・・・。
12月25日を以って閉店するスターバックスなぎさライフサイト店。この店で朝カフェ読書ができる日もあとわずか・・・。










 480
480 
 320
320 320
320 320
320






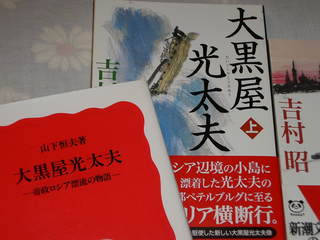 ①
① ②
② ①
①  ②
② ③
③
 他にこのような本は特にないので、これからは現代史それも第二次世界大戦の関連本を読もうと思っている。第二次世界大戦について学ぶことの意義は大きいと思うから。
他にこのような本は特にないので、これからは現代史それも第二次世界大戦の関連本を読もうと思っている。第二次世界大戦について学ぶことの意義は大きいと思うから。