
■ 昨晩、中学の時の同級生と飲みました。年に数回やっている33会でした。ン十年前(20年前?30年前?40年前?50年前?、60年前?まさか)たった2年間同じクラスだった、ということだけでなのですが、いまだに交流が続く仲間達との飲み会。いつも楽しいひと時を過ごします。
さて中学3年の時の修学旅行は電車で京都、奈良へ出かけたことは記憶にありますが、一体どこを見学したのか、悲しいかなもはや記憶ははるか彼方に流れて消えてしまっています。京都では清水寺を観たこと、奈良では興福寺を観たこと位しか覚えていないのです・・・。
街中の移動に今の修学旅行生達はタクシーを利用するそうですが、私達のころはたぶん観光バスではなかったかと・・・、でもそのことについても記憶がありません。歳を取るとよくものを忘れると聞きます。でも昔のことはよく覚えているものだ、とも聞きますが、どうもそれも私に限っては当て嵌まりそうも無く・・・。
昨晩、ワインやビール、焼酎などをかなり飲みながら修学旅行のことを話すと「東大寺にも法隆寺にも行った」ということなのですが、その記憶は・・・「無」です。
ところで今回アップした写真は、いつごろかな、15年くらい前に撮ったものではないかと思います。過去のダイアリーを調べればわかるかもしれませんが「ずく」がありません(「ずく」というのは信州の方言、意味は説明しませんがなんとなく文脈で分かりますよね)。
この光景を目にしたときは驚きました。背景の興福寺の五重塔、猿沢の池のほとり、坂の途中の旅館。はるか彼方の記憶とピッタリと符合する光景。ここはあの修学旅行で泊まった旅館です。「あの時とオンナジダ!!」
都市の光景の変化の早いこの国で、よく変わらずにいてくれたものです。
奈良、行ってみたいです。ここにもまた行ってみたいです。繰り返し書いているとその気になって実現するかもしれません。
昨晩の話では来年の春に歌舞伎を観に行こうということに、でも酒席での話ですから・・・。確か以前ベトナムに行こう!ということになったこともありますが実現していません。話の結論がどこに流れ着くことやら・・・。でも一昨年2回目の修学旅行は実現しました。



■ このところ建築トランプモード全開です。
私が最初に観た谷口吉生さんの作品は「土門拳記念館」か「資生堂アートミュージアム」のどちらかだと思います。
今回のカードは豊田市美術館、ここを見学に訪れたのはもう5、6年位前?のことです。端整なデザインが谷口さんの建築の特徴ですがこの美術館も例外ではなく知的でシャープな姿が印象的でした。
人工的に造られた「水庭」のエッジに沿って薄い壁が等間隔に何枚も並んでいます。そう、「繰り返しの美学」。水庭と壁の連なりが外観を特徴付けています。
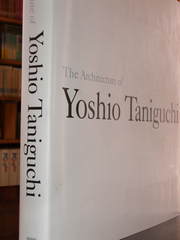
谷口さんはMoMA ニューヨーク近代美術館の増改築計画のコンペで当選しています。その応募案の展覧会が東京でありました。もう10年位前のことだろうと思いますが。応募案のプレゼン用図面が実に美しかったことを今でも覚えています。
この作品集はその展覧会会場で買い求めたものです。谷口さんの作品の写真集。欲しい本は少し無理をしても買い求める、基本です。
どうしてこんなに美しいんだろう・・・、そのポイントはどこにあるんだろう・・・。谷口さんの建築デザインの特徴を一言で、ということになると「端整」だと私は思います。少し遊んでもいいのではないかとも思いますが、隅々までとにかくビシっとおさめています。余分なもののない簡潔なディテール、魅了的です。
この作品集に載っているのは豊田市美術館に併設されている茶室だと思いますが、写真を観るとシャープな線で構成されていることが分かります。真、行、草、茶室もこのようにスタイルを分けることが出来るのですが、真以上にカチっとした茶室、谷口さんが設計すると茶室もこうなるのだな、と納得します。
http://www.tnm.jp/jp/guide/map/horyujiHomotsukan.html
上野の法隆寺宝物館も谷口さんの作品、やはり水庭を配し「和」を感じさせる美しい建築です。もう一度訪ねたい建築です。









