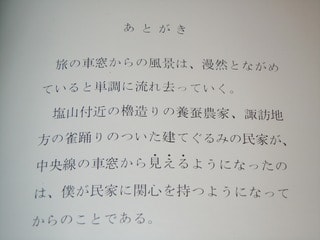『車窓の山旅 中央線から見える山』山村正光/実業之日本社
■ 1985年だから、25年前に読んだこの本のことをふと思い出した。
カバー折り返しに載っているプロフィールによると、著者の山村さんは昭和2年生まれ。国鉄で40年間、主に中央線の車掌として新宿―松本間をおよそ4000回乗務したという。
旧制甲府中学で山岳部だったという山村さんは、中央線から見える山々を車窓から観察し続けた。観察した山々について本書にまとめた。紹介されている山は100座を越える。見開き2頁に1座、塩尻松本間では鉢盛山、鉢伏山、鍋冠山、燕岳、仙丈岳、王ヶ鼻、常念岳、大滝山、有明山、そして最後に乗鞍岳が取り上げられている。
有明山の頁では山の名前の由来について、『日本名勝地誌』の有明山の項の「霖雨ある毎に河水汎濫上流より巨石を押流し来たりて雨後は必ず沿岸の景色一変す」という記述を紹介し、有は荒の転化、明は『古代地名語源辞典』から崖、湿地ではないかとし、中房川の氾濫で生じた「荒れはてた湿地」あるいは花崗岩の風化による「荒れた崖」の源頭の山という意味ではないか、と記している。さらにこの説を補強する文献が紹介されているが、引用は省略する。「荒れた崖」は有明山の特徴をよく示しており説得力がある。
このように、山村さんは取り上げたそれぞれの山を内容濃く紹介している。山に関する興味、知識がなければ中央線の車窓から、この本に紹介されている山々は見えないだろう。脳は伝えられる情報を既得の情報に照らし合わせて認識するのだから。
知らないことは見えない、認識できない。昔、撮りためた民家の写真をまとめたときも、これと同じことを書いた(下)。考え方は変わらないものだ。
ところで、山梨県にはあお向けに寝た裸の女性を思わせる山があって、勝沼駅あたりから見えるという(新宿に向かって右側)。こんど電車で東京に出かけるときに観察してみよう・・・。