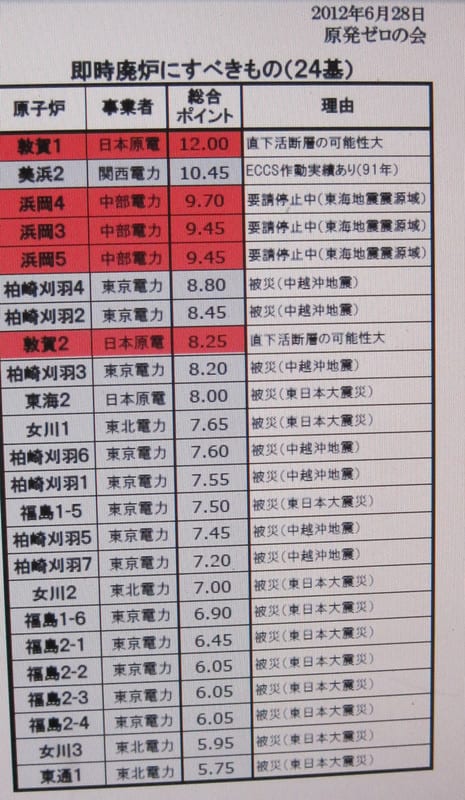この写真は武蔵野の雑木林を保存したものです。府中市の郷土の森公園にあります。
冬の雑木林は緑が見えず淋しいものです。寒風に梢が揺れているだけです。しかし青空を背景にした樹林のシルエットは美しいものです。詩的なムードが流れています。
見ているといろいろと今年の出来事を思い出します。そして何故雑木林が美しく見えるか考えてみました。
私が雑木林に興味を持つようになったのは国木田独歩の「武蔵野」を読んでからです。
その本によると雑木林が文学作品の対象になったのは明治維新後のようです。
明治4年生まれ、41年、36歳で亡くなった国木田独歩は「武蔵野」を書いて雑木林の美しさを描きました。
江戸時代以前は松の木や美しい竹林などは文学作品に登場しますが、いろいろな雑木の混じった広葉樹の混生林は美の対象になりませんでした。
明治維新は日本の政治体制や社会構造を変革しただけではありませんでした。
日本人の自然の風景の好みや美意識が変革したのです。
この広葉樹の林の美しさを国木田独歩へ教えたのはロシア人のツルゲーネフです。そのことは末尾に紹介したURLを開けてみると、国木田独歩自身が書いているので明白です。
ロシアの大地にある白樺やダケカンバなどの樺の木の林の美しさをツルゲーネフは活き活きと描いています。国木田独歩は深く感銘を受けます。
彼は明治時代の東京市の西の郊外に広がる田園地帯を広く歩きまわります。そして、そこにあるコナラ、クヌギ、カシ、エゴノキなどなどの雑木林の詩的なたたずまいを文章で表現したのです。四季折々の美しさ、朝や夕方の林の輝きを描いたのです。
それ以来、多くの日本人は雑木林は美しいと認識するようになったのです。勿論、昔の日本人も美しいと思ったに違いありません。しかし文学作品にはほとんど現れませんでした。
若い頃、この「武蔵野」という本を読んで、すっかり雑木林の魅力にとりつかれました。以来、茫々50年、60年、今でも雑木林が好きで武蔵野を広く散策して写真を撮っています。
何十年か前に山梨県の山の雑木林の中に小屋を作って、通っているのも「武蔵野」という本の影響もあると思います。
そこで下に甲斐国の八ヶ岳と甲斐駒岳の写真をしめします。どちらの写真にも高い山々の麓に広がっている雑木林が写っています。
上が甲斐駒岳で下が八ヶ岳です。
武蔵国でも甲斐国も雑木林の多くは農民が植えて育てた林なのです。
木の幹は小屋や家の材料にします。炭焼きの原料です。枝は薪にして燃料です。落ち葉は畑の肥料にします。このように人間が植えた雑木林なので木々が整然と並んでいます。木の種類も一種だけの林があるのです。
ですからこそ見て美しいと思うのかも知れません。
冬の雑木林は陽が差し込んで明るく暖かいものです。道もなくとも下草の上を散歩するのは実に楽しいものです。
武蔵野では平地ですが甲斐の雑木林にはなだらかな起伏があって散歩がより一層楽しくなります。冬の雑木林では見透しがきくので遠方にサルの群れやシカが見えます。
そんな雑木林を散歩しながら36歳で夭折した国木田独歩の生涯を想います。
小説を沢山書きました。しかし現在世に知られているのは「武蔵野」だけです。残念です。本人も、もっともっと文学作品を書きたかったことでしょう。心残りだったに違いありません。
皆様も近所の雑木林の美しさをお楽しみ下さい。冬の雑木林をお楽しみ下さい。
それはそれとして、
今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)
====参考資料===========================
「武蔵野」の詳細な内容は、http://www.aozora.gr.jp/cards/000038/files/329_15886.html にございます。
そして国木田度独歩の経歴を下にご参考までに掲載して置きます。
================================
国木田 独歩(くにきだ どっぽ、1871年8月30日(明治4年7月15日) - 1908年(明治41年)6月23日)は、日本の小説家、詩人、ジャーナリスト、編集者。千葉県銚子生まれ、広島県広島市、山口県育ち。幼名を亀吉、のちに哲夫と改名した。筆名は独歩の他、孤島生、鏡面生、鉄斧生、九天生、田舎漢、独歩吟客、独歩生などがある。 田山花袋、柳田国男らと知り合い「独歩吟」を発表。詩、小説を書いたが、次第に小説に専心。「武蔵野」「牛肉と馬鈴薯」などの浪漫的な作品の後、「春の鳥」「竹の木戸」などで自然主義文学の先駆とされる。また現在も続いている雑誌『婦人画報』の創刊者であり、編集者としての手腕も評価されている。夏目漱石は、その短編『巡査』を絶賛した他、芥川龍之介も国木田独歩の作品を高く評価していた。ロシア語などへの翻訳があるが、海外では、夏目漱石や三島由紀夫のような知名度は得ていない。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%9C%A8%E7%94%B0%E7%8B%AC%E6%AD%A9