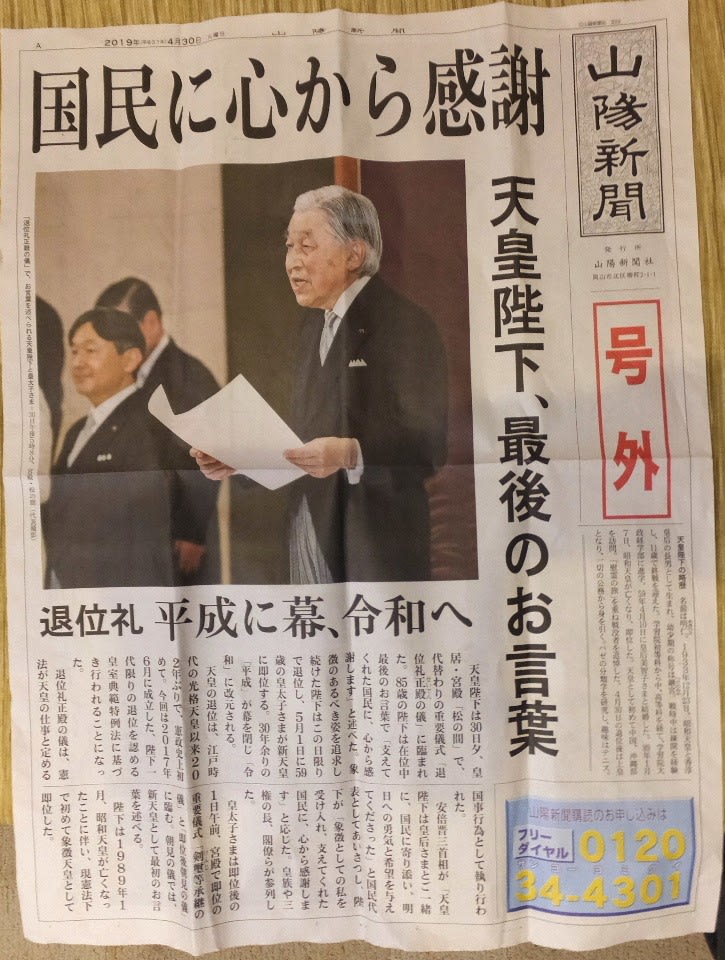(上の画像はドリアン。インドネシアでよく食べたと言ったらタイのドリアンは臭いが少ないと言われた)
亀戸神社に行く前に錦糸町の「タイランドショップ」に寄って昼食をたべた。
この店はタイの食材を売るタイ人が経営している店だが、同胞相手のタイ料理の食堂もやっている。だから味をジャパナイズしていない。

あいかたはバッタイ。

私はソーメンのように細いビーフン麺のセンレックラーメン
テーブルに沢山の調味料が並んでいるのでいろいろ入れたら味が深くよりおいしくなった。

タイビールのレオ

翌日のランチは地元の家から歩いて8分のネパール料理店「スパイス市場」でカレー料理。私はマトンカレーとジントニック

あいかたはダブルカレーで、ほうれん草とチキンカレー。

持ち帰りにチーズナンを頼んだ。プレーンナンの一枚は食べきれないのでこれも持ち帰り。
ナンは子供たちが大喜びで食べる。
神戸六甲のO先輩からメールをいただきました。⇒「この時期になると、貴兄のブログに必ず登場するだんじり地車、
今日、神戸市摂津本山で「奉祝だんじり巡行」が行われましたよ。
走る動の岸和田のだんじり(地車)にくらべ、摂津国菟原郡のだんじりは静だそうです
今日は、東灘区は勿論、宝塚、西宮、芦屋、灘区(いずれも摂津国菟原郡に属する)からも参加して、
全部で45基のだんじりが参加したそうです。
我が町・篠原のだんじりも参加、午前7時過ぎに我が家の前を通って、
摂津本山駅近くの山手幹線の会場に向かいました。
下記の動画で楽しんでください。
2019 / 04 / 04 15:30
地区紹介の一例:御影地区