●第42回反省会(昭和58年6月9日)
軍令部が最初の神風特攻隊を利用してある作戦を考えていたことがこの日明らかにされる。明らかにしたのはこのときも鳥巣健之助元大佐。
極めて重要なことを示しているとして一通の電報を読み上げる。
鳥巣「神風隊突撃の発表は、全軍の士気高揚並びに国民戦意の振作(しんさく)に至大の影響関係あるという、各隊攻撃の実施の都度、純忠至誠に報い――」
(全軍・国民を奮い立たせる目的をも持たせていたために、たいした効果を上げなくても、戦意高揚を果たすために効果あったと宣伝することになったのだろう。結果、本来なすべき作戦を改めるということをせず、効果のない作戦を続けることとなったのだろう。)
●その電報には国民の戦意や全軍の士気高揚のために攻撃の都度、発表される方針が示されている。
●昭和19年10月、神風特別攻撃隊が初めて体当たり攻撃を始めた。
海軍撮影の映画。「神風特別攻撃隊」と大書した字幕。
整列して出撃する隊員たちに対する上官の訓示「一機以って敵艦命中、生還を期せず――」
そして相歌う『海ゆかば』
●司令長官の大西中将や隊員たちの姿が映像と共に広く伝えられていった。前出電報は初めての出撃の15日前に作られていた。起案者軍令部一部で航空作戦を担当していた源田実大佐。
鳥巣「軍令部の方では作戦課の航空参謀である源田実中佐が10月13日、電報を起草して、第一部長中澤佑少将の承認を得て発信しております。従って大本営が特攻は地方の実施部隊がやったんで、大本営(軍令部)は知らなかったというようなことを言うこと自体が極めておかしいのであります」
●神風特攻隊の戦果が宣伝されていく。新聞では神風特攻隊員の動きが一面で伝えられ、国民の戦意を駆り立てる記事が掲載されていく。
新聞見出し「一機命中 一隻轟沈」
「只一言、俺に続け」
●大きく伝えられた戦果の裏で、海軍は危機的な戦局に直面していた。神風特攻隊を投入したフィリッピン・レイテ島海戦は主力艦隊の殆んど率いて臨んだ一大決戦だったが、特攻作戦も空しく、海軍は主力艦隊4隻を含む艦艇20隻以上を一挙に失う。
●戦う手立てを失う中、軍令部は特攻作戦に比重を移していく。国民に常に伝えられていたのは特攻の戦果。
●第94回反省会(昭和62年10月30日)
この日軍令部の元将校と特攻の現場を見てきた隊員との間で議論が行われる。軍令部で昭和17年まで航空作戦の参謀を務めていた三代一就(みよ・かずなり)元大佐(昭和14~17年 軍令部)。特攻は現場の熱意から始まったと言う。
三代「特攻作戦を欠くとしましても、色々な資料とか図書があって、特攻作戦を欠くのは容易ではないと、いうことは航空部隊の間には特別攻撃を必要とする機運が高まり――」
現場の航空隊にいた小池猪一(いいち)元中尉が質問する。
小池「大所高所から、先輩諸君のご意見を承りたいと思っております。航空特攻の場合はですね、志願という形は取っているが、これは命令で、編成という形で命令されているんで、戦闘機に爆装して、攻撃隊を編成したというのは、どういう根拠から、いわゆる上層部がそれを命じたのか」
小池元中尉は18年12月、学徒出陣で航空隊に配属され、そのときの上司が特攻で数多く戦死している。
小池「飛行時間80時間から120時間ぐらいの搭乗員をバラバラ、バラバラ、いわゆる纏まって出さないで、小出しにどんどん出して、どんどん消耗していった。全予備学生、予科練学生が大きな疑問を持って、今、この問題でみんなして取り組んでおります」
現場からの問いに三代元大佐は明確には答えない。
三代「これはやっぱり、その人の性格によると思いますから。性格と、それから時の情勢ですな――」
(「人の性格」と「時の情勢」が決定した特攻作戦だったとは、何という責任転嫁なのか。必要としたのは戦争を続ける能力が残っているかどうかを含めた「時の情勢」を分析する的確な判断能力だったはずだが、それを欠いていた。)
●昭和20年1月15日、最高戦争指導会議(総理大臣や陸海軍トップが出席)
ここで国家総動員によって戦争を継続し、特攻を主な戦力とすることが確認された。
この同じ1月、軍令部一部が作成したと見られる資料が今回初めて見つかる。日本列島を覆っている印はすべて特攻兵器を配備する基地。軍令部は一億総特攻の掛け声そのままに特攻で日本列島を守る計画を立てる。
●反省会には、その時期軍令部に在籍していた土肥一夫元中佐が発言。
土肥「終戦の前後、私は軍令部におりまして、軍令部の中に私のクラスでありますが、『一億総特攻』って言って、はしゃぎまわる男がいたんですが、私は喧嘩しましてね、人間をね、今の言葉で言いますと、コンピューター代わりにして飛行機を向こうにぶっつけようなんていう、そんなことはね、考えるなと。お前ら、一億総特攻なんか、言うなってね、喧嘩したことがあります」
(果して事実かどうか。自身が「一億総特攻」と言ってはしゃぎまわっていたかもしれない。確実に言えることは、その効果を隠していたために「一億総特攻」にオールマイティ(全能)を期待した軍人・国民が多くいたに違いない。その効果を知っていた軍人の間でも、ほかに打つ手を考えつくことも情勢分析をすることもできなかったことから、縋りつくように「一億総特攻」に最後の望みを果敢なくも託していたといったところではないのか。)
●特攻が行われている時期に連合艦隊参謀だった中島親孝元中佐。
中島「飛行機の搭乗員のですね、補充をということを考えないで、行き当たりばったり行っていく言って、仕方がないから、特攻へ逃げたんです。もう人間を自動操縦機の代わりをするんだと、こういう思想がある。それがですね、日本海軍を毒した最大のもんだと私は見ています」
(海軍のみならず、大日本帝国軍隊全体に人命軽視の思想が蔓延っていた。上官を絶対として、兵士を対極の人間として扱わない、将棋のコマ並みに扱う権威主義が支配していた。)
平塚清郎「日本の海軍の上層の方も、それに頼り過ぎていたんじゃないか。万止むを得なかったというなら、それは私は一億総玉砕の思想そのものじゃないか」
●(出撃シーン)太平洋の海の中に若者たちが散っていった。
(字幕)当初米軍に襲撃を与えた特攻。米軍は特攻への対策を徹底した。特攻機の殆んどは目的を遂げることができなくなる。水中特攻「回天」の命中率は2%(防衛研究所)。
●昭和20年8月15日、終戦。天皇の玉音放送。米軍の進駐。街中を走る米軍ジープ。
未使用の特攻兵器は米軍によって回収され、分析が進められることになる。
連合軍司令部(GHQ)――戦争犯罪を追及する動きが始まる。これに対して軍令部は終戦直後から戦犯裁判に向けた準備を進めていた。その対策を纏めた文書。
特攻が戦争犯罪とされることを恐れ、想定問答を用意していた。
(戦争犯罪対象となり得る作戦だと認識していたことになる。)
想定案「特攻は上級指揮官の要請で人道に違反するのではないのか。」
回答案「特攻は切羽詰った戦況の中実施した。軍人は上下こぞって総員玉砕を期していたが、青年下級者のみに必死の戦法を強いたのではない」
●特攻は上級指揮官の強制ではなく、人道に違反しないと答えている。軍令部の指示で造られた特攻兵器。現場の幹部たちは戦後もその責任を感じ続けている。桜花の製造に携わった長束麗元少佐。製造に反対したが、命令に従わざるを得なかった。GHQの追及はなかったが、兵器を造った事実は重く受け止めていた。
長束巌元少佐(97)「アメリカの戦犯狩りの情報がクラスメートから刻々入ってくるわけです。誰が捕まって、誰が喋らされた、何級上の誰々が何々の名目で捕まれたと。で、色々聞いてますと、何か、どういう罪の者が戦犯でね、扱われているっていうことを聞いてみたら、第一は人道に関する罪。人道に関する罪ということになると、ちょっと俺は危ないぞと思ったわけです。こういう全く人道に麻痺した飛行機を造ることを命じられて造ったわけですから」
●現場に特攻を支持した軍令部が組織として責任を認めた資料を見つけることはできなかった。
死ぬことで初めて目的が達せられる特攻。なぜこれ程多くの若者たちが命を落とさなければならなかったのか。反省会で特攻の議論が行われているとき、一人の元将校が発言。扇一登元大佐(昭和11~13年 軍令部)。武官としてヨーロッパで終戦を迎える。組織全体が新兵器に頼る気持に流されたのではないかと語る。
扇「新兵器が生まれてくると、使ってみたくなる。そこで私自身が、それにやっぱりよりかかる。気持の上ではおったと。太平洋戦争はそれらの日本の強みとする新兵器に引きずられたんだと言うことは敢えて言うことができませんが、しかし、頼んでおった」
●扇元大佐が指摘した組織の空気。その空気を生んだ海軍の体質を扇元大佐は考え続けていた。
扇「海軍は自分の意志、判断を持っておりながら、それはこちらに置いて、そうして流れて、海軍のこれは体質だと思うんですよ。だからこそね、思わぬ、好まぬ、自分の本位ではない方向へ流されているなと。誰彼と言わずに、みんなそうですもん」
(誰だって「意志、判断を持って」いる。それが合理性を備えた意志・判断であるかどうかが問題。合理性を備えていなければ、意味のない「意志、判断」となる。
「思わぬ、好まぬ、自分の本位ではない方向へ流され」る、それが「誰彼と言わずに、みんなそう」であるとは付和雷同の状態を言い、他の意見を絶対としてそれに無条件に従う権威主義性からきている。)
●自分の意志ではない方向へ流されていく海軍の体質とは何か。扇元大佐の息子暢威(のぶたけ・77)は父親から特攻の話を聞いたことはない。強く印象に残っているのは反省会から帰ってきた父親が時折洩らしていた言葉。
「何回かね、『それなんだよ、そうなんだよ。やましき沈黙だったんだよ、うん、海軍は』そういうね、発言は私は聞いてますねえ。要するに良心に照らしてみて、これはいかんと思ったときに言えていないと。海軍全体もそうだったと、いうそういう言い方がありましたね」
(最初触れたように日本人が行動様式としている権威主義から来ている上に対して言いたいことを言えない“沈黙”であって、特に日本の軍隊に於いて上官を絶対としていることからその権威主義性が色濃く現れた組織となっていたということなのだろう。自由に意見を言うについては自由に意見を言う機会を上から与えられた場合という条件付となる。)
●やましき沈黙。間違っていると思っても、口には出せず、組織の空気に飲み込まれていく。特攻が始まったとき作戦を担当していた軍令部一部長中澤佑元中将が亡くなる直前に講演を行ったときのテープが残されている。最初の特攻、神風特攻隊への関与を否定した。
中澤「私は軍令部の作戦部長をしておったのですが、特攻というのは、これは作戦ではないと。作戦よりもっと崇高なる精神の発露であってね、作戦にあらずと。
そのときに私はその体当たりということは考えておりませんし、ええー、勿論、命令などは出したことはありませんので――」
(体当たりなくして特攻は成り立たない。特攻と体当たりは一体となって、その存在価値を決定付けられていた。体当たりは特攻の行動性として定められたもの。偵察機が偵察を行動性とするように。「そのときに私はその体当たりということは考えておりません」は薄汚い責任逃れ。「崇高なる精神」を装わせることで納得させ、若者の積極性を引き出したにすぎないだろう。
この男は戦後源田実のようになぜ政治家に転進しなかったのだろうか。源田以上の政治家となって、総理大臣も夢ではなかったはずだが。)
息子忠久、父親が軍令部一部長だったとき語った言葉を覚えている。
「特攻はよくないってことは何回か、それはもう、1%でも帰る方向があるのならいいけど、100%死ぬような遣り方、それは戦術でないと。時々は空気には勝てないんですよねー。もう全体がそういう流れになって。個人がね、いくら心の中で反対だって言っても、大勢に反対ってことは、もう海軍をやめなけりゃあいけないことですよね」
●中澤元中将が大切にしていたアルバム。戦争末期、軍令部から台湾の航空船隊の司令官に移動し、特攻の指揮を任務とした。隊員たちの写真。その横に自ら書いた説明。「笑わんとして死地に向かわんとする特攻隊勇士」
●軍令部二部長として特攻兵器の開発を進めた黒島亀人元少将、戦後哲学や宗教の研究に没頭した。亡くなる直前までつづっていたノート。
ノートの題名「人間」、中に「霊魂」、「人生の目的」といった文字。
特攻については一言も書き残していない。
●神風特攻隊の電報を起案した軍令部源田実元大佐は戦後航空自衛隊のトップ航空幕僚長に就く。特攻については家族にも多くを語っていない。神風特攻隊の慰霊碑に源田実元大佐は自ら書き記している。
「青年が自らの意志に基づいて赴いた」
今も保管されている特攻隊員と戦死した部下の名簿。仏壇に納めて、毎日祈り続けていた。
(「青年が自らの意志に基づいて赴いた」とすることによって、自己正当化を果たすことができる。日本の軍隊の正しさが証明可能となる。)
●反省会で軍令部を批判し続けた鳥巣健之助元中佐、戦時中を振返り、家族に一言だけ言い残している。
「海軍の中で思っていても、言いたいことがあっても、口には出せないことがあった」
(権威主義に囚われた姿を言っているに過ぎない。)
神風特攻隊の隊員だった角田和夫(90)、特攻で戦死した仲間の慰霊を今でも行い、靖国神社に参拝している。特攻隊の戦果を空から確認することが任務。
角田「突っ込むのは自分だけでいいから、もう戦争はやめてくれないかというのは、誰だって、考えじゃなかったかと思います。ねえ、死ぬのは自分だけ、ここで終わりにしてしてくれっていうのがみんなの本心だったと思います」
●角田さんは反省会が開かれていたことを知らなかった。その事実を知らせた上で了解の元、反省会のテープを聞いてもらう。
――土肥一夫元中佐「この今のお話の、大西さんとの話じゃなくて、その遥か前にですね、回天も桜花も、マル四艇もみんな、海軍省で建造始めているんですよ。そうするとね、その特攻をね、(軍令部)一部長ともあろう者がね、知らないというのはおかしいとこう言うちょるとです、鳥巣さん」――
角田「いや、そんなに早くから特攻を考えていたなんていうことは、ちょっと信用できないですねえ。じゃあ、その人たちが19年の初めから、その以前から特攻兵器を造らせて、その特攻兵器を造ってどうしようと思っていたんです?、それを聞きたいですねえ。それで勝つと思っていただろうか」
●いくら墓参りしても、亡くなった人間は生きて還らぬという。角田さんは最後に見届けた広田幸宣(ゆきのぶ)(20)さん。
(広田幸宣の遺言)「ご両親さまの心尽くしの品々、嬉しく拝見して、マフラーを喜んで首に巻いて飛びます。白いマフラーで出発するのを想像してください。国のため、征(ゆ)く身なるとは知りながら、故郷(くに)にて祈る父母恋しき」
角田さんが最後を見届けたもう一人の谷本逸司(享年22歳)
(谷本逸司の遺言)「お母さん、元気ですか。長々の御恩、本当にありがとうございました。いよいよ本当に男としての生き甲斐を痛切に感じるときが参りました。くれぐれも体に気をつけて、長々と生き抜いてください。お願いします。遥かお母さんの健康をお祈り致します」
●日本海軍が始めた特攻。始まると、誰も止められずに終戦まで続けられる。
取材デスク・小貫武「反省会に参加していた一人ひとりは決して命じてはいけない作戦だと心の中では分かっていた。しかしその声が表に出ることはなかった。間違っていると思っても、口には出せず、組織の空気に飲み込まれていく。そうした海軍の体質を反省会の一人は『やましき沈黙』という言葉で表現した。しかし私はこの疚しき沈黙を他人のこととして済ますわけにはいかない気持になる。今の社会を生きる中で、私自身疚しき沈黙に陥らないとは断言できないから。特攻で亡くなった若者たちは陸海軍併せて5千人以上。その一人ひとりがどのような気持ちで出撃して行ったのか。決められた死にどう向かっていったのか。
その気持を考えると、私は反省会の証言から学び取るべきものは唯一つのことではないかと思う。それは一人ひとりの命に関わることについては、例えどんなに止むを得ない事情があろうと、疚しき沈黙に陥らないことです。
それこそが特攻で亡くなった若者が死を以って今に伝えていることではないかと私は思います」(終了)
(では、「一人ひとりの命に関わ」らないことについては「疚しき沈黙に陥」ってもいいのか。日常普段から慣習としている“やましき沈黙”――内心は反対でも上の命令・指示に無条件に従属する権威主義性を「一人ひとりの命に関わることについて」も機械的・自動的に適合させていくことによって生じせしめた上下の関係性としてある“やましき沈黙”なのだから、省察すべき対象は日本人が現在も引きずっている上下で人間関係を把える権威主義の行動様式そのものであろう。
いわばどんなにささやかな問題・事柄であっても賛成できないこと、訂正が必要なことは“やましき沈黙”に陥らず、恐れずに自分の意見を述べる、そして相手の反論を受ける議論の習慣を普段から持つことから始めなければならない。
「組織の空気に飲み込まれる」と言うが、反応するのは個人個人であって、それらが積み重なってその全体的な反応である「組織の空気」を形成するのだから、一人ひとりの反応――それぞれの権威主義性を先ず問題としなければならない。) |
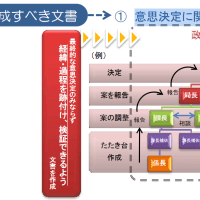 安倍晋三のケチ臭い度量から発した放送法「政治的に公平」の「補充的説明」を騙った報道自主規制の罠
2年前
安倍晋三のケチ臭い度量から発した放送法「政治的に公平」の「補充的説明」を騙った報道自主規制の罠
2年前
 野党の学習不足が招いた安倍晋三と旧統一教会との関係調査・検証要請への岸田文雄の「本人死亡、十分な把握限界」等の罷り通り
2年前
野党の学習不足が招いた安倍晋三と旧統一教会との関係調査・検証要請への岸田文雄の「本人死亡、十分な把握限界」等の罷り通り
2年前
 イジメ未然防止目的のロールプレイ――厭なことは「やめて欲しい」で始まるイジメ態様に応じた参考例をいくつか創作してみた
2年前
イジメ未然防止目的のロールプレイ――厭なことは「やめて欲しい」で始まるイジメ態様に応じた参考例をいくつか創作してみた
2年前
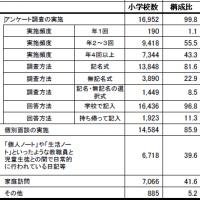 イジメ過去最多歯止めは厭なことは「やめて欲しい」で始まり、この要請に順応できる人間としての成長を求めるロールプレイで(1)
2年前
イジメ過去最多歯止めは厭なことは「やめて欲しい」で始まり、この要請に順応できる人間としての成長を求めるロールプレイで(1)
2年前
 イジメ過去最多歯止めは厭なことは「やめて欲しい」で始まり、この要請に順応できる人間としての成長を求めるロールプレイで(1)
2年前
イジメ過去最多歯止めは厭なことは「やめて欲しい」で始まり、この要請に順応できる人間としての成長を求めるロールプレイで(1)
2年前
 立憲長妻昭と小西洋之の対旧統一教会宗教法人法第81条解散命令要件に関わる時間のムダ、カエルの面に小便程度の国会追及
2年前
立憲長妻昭と小西洋之の対旧統一教会宗教法人法第81条解散命令要件に関わる時間のムダ、カエルの面に小便程度の国会追及
2年前
 2022年8月NHK総合戦争検証番組は日本軍上層部の無責任な戦争計画・無責任な戦略を摘出し、兵士生命軽視の実態を描出 靖国参拝はこの実態隠蔽の仕掛け(1)
2年前
2022年8月NHK総合戦争検証番組は日本軍上層部の無責任な戦争計画・無責任な戦略を摘出し、兵士生命軽視の実態を描出 靖国参拝はこの実態隠蔽の仕掛け(1)
2年前
 2022年8月NHK総合戦争検証番組は日本軍上層部の無責任な戦争計画・無責任な戦略を摘出し、兵士生命軽視の実態を描出 靖国参拝はこの実態隠蔽の仕掛け(2)
2年前
2022年8月NHK総合戦争検証番組は日本軍上層部の無責任な戦争計画・無責任な戦略を摘出し、兵士生命軽視の実態を描出 靖国参拝はこの実態隠蔽の仕掛け(2)
2年前
 立憲民主党代表泉健太の2022年9月8日衆議院議院運営委員会安倍晋三国葬関連質疑を採点すると30点
2年前
立憲民主党代表泉健太の2022年9月8日衆議院議院運営委員会安倍晋三国葬関連質疑を採点すると30点
2年前
 文科省の旧統一教会実体不問の名称変更認証と前川喜平氏の下村博文認証関与説、橋下徹の名称変更門前払い対応の前川喜平氏批判のそれぞれの正当性
2年前
文科省の旧統一教会実体不問の名称変更認証と前川喜平氏の下村博文認証関与説、橋下徹の名称変更門前払い対応の前川喜平氏批判のそれぞれの正当性
2年前
 尾木直樹こども基本法講演:"個人としての尊重"なしに「子どものことは子どもに聴...
尾木直樹こども基本法講演:"個人としての尊重"なしに「子どものことは子どもに聴... 尾木直樹こども基本法講演:「子どもと大人の新しい関係性の第一歩、スタートに立...
尾木直樹こども基本法講演:「子どもと大人の新しい関係性の第一歩、スタートに立... 《八方美人尾木ママの"イジメ論"を斬るブログby手代木恕之》を始めました。
《八方美人尾木ママの"イジメ論"を斬るブログby手代木恕之》を始めました。 日本人の行動様式権威主義の上が下に強いていて、下が上に当然の使用とする丁寧語...
日本人の行動様式権威主義の上が下に強いていて、下が上に当然の使用とする丁寧語... 財務省2018年6月4日『森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書』...
財務省2018年6月4日『森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書』... 名古屋入管ウィシュマ・サンダマリさん死亡はおとなしくさせるために薬の過剰投与...
名古屋入管ウィシュマ・サンダマリさん死亡はおとなしくさせるために薬の過剰投与... 民間企業と官僚の意見交換に酒食が伴い、その支払いを企業が負う官僚のたかりは人...
民間企業と官僚の意見交換に酒食が伴い、その支払いを企業が負う官僚のたかりは人... 2021年2月25日山田真貴子参考人招致衆議院予算委員会の黒岩宇洋と後藤祐一の追及を...
2021年2月25日山田真貴子参考人招致衆議院予算委員会の黒岩宇洋と後藤祐一の追及を... 東京大空襲訴訟高裁判決「旧軍人・軍属への補償は戦闘行為などの職務を命じた国が...
東京大空襲訴訟高裁判決「旧軍人・軍属への補償は戦闘行為などの職務を命じた国が... 安倍晋三の検察庁法改正案に賛成しよう! 但し不正疑惑渦中閣僚一人で検察人事関...
安倍晋三の検察庁法改正案に賛成しよう! 但し不正疑惑渦中閣僚一人で検察人事関...















