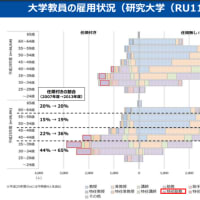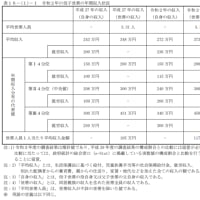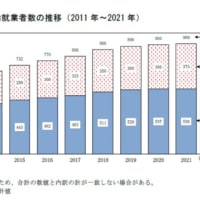今日の朝日新聞のWEBサイトに生協、個配の時代 都市で急増、班配達抜くと言う記事が、掲載されている。
マーケターとして「生協」と言う小売形態は、イマイチ分からない感がある。
と言うのも、生協の組合員は顧客でありながら、商品開発や運営(=経営)方法に参加しているからだ。
その意味で、マーケティングそのものと関係のない(ように思える)形態だとも言える。
とはいっても、生協そのものも時代の変化に伴い販売形態も大きく変化してきている。
その一例が、店舗展開だろう。
「生協」と言うと、記事にあるような「班配達」と言う数人の利用者グループを作り、共同購入をすると言うのが一般的だったし、今でも「生協=班配達」というイメージが強い。
しかし、現在では店舗展開などもしており、我が家の近所にも「生協のお店」がある。
利用者は、生協の組合員に限られているのだが、見た目はごく普通のスーパーマーケットだ。
今から15年程前、マーケティングの研修で「コープこうべ」へ視察に行ったことがあるのだが、商品企画などの生協らしさと全国展開をしているスーパーと何ら変わない店舗という2つの顔をもっていた。
店舗には食料品だけではなく、衣料品やスポーツクラブなどがあり、大手銀行系とのジョイントクレジットカードなども発行していた。
「コープこうべ」は、日本の生協発祥の地とも言われるだけに、組合員数や売上規模など、大手スーパーを遥かに凌ぐモノがあった。
それだけではなく、日本の生協スタイルを作りあげたと言っても良いほど影響力がある。特に生協組合員の声で、商品企画・開発がされるという方法は、大型スーパーの「自社ブランド開発」の基となっていると考えている。
もう一つ注目したいのは、生協の利用者の変化だろう。
と言うのも、生協利用者の多くが幼稚園入園前のお子さんのいる家庭だからだ。
子供の成長とともに主婦の時間が増え始めると、生協の利用は減っていくと言われている。
そして再び利用が増えるのが、高齢者世帯となった時なのだ。
(地域全体の)高齢化に伴い、食料品や日用品の買い物に支障がおきるようになると、自宅まで配達してくれる生協は、便利な存在となるのである。
すなわち、多くの人たちが思っているような「割高でも安心・安全な食品の提供」と言うのは、利用者にとって第一の理由ではないのかも知れないのである。
事実、今年問題となったミートホープ社の「偽装ミンチ」は、生協の「牛肉コロッケ」に使われていた(生協が悪いわけではないが、この事件によって「生協ブランド」のイメージが大きく損なわれたのは、確かだろう)。
組合員以外からみる「生協」は、どこか堅苦しく「よく分からない」気がするのだが、一つの小売形態・業態としてみた時、生活者との関係が深いだけより「生活の変化」が分かるのではないか?と感じている。
マーケターとして「生協」と言う小売形態は、イマイチ分からない感がある。
と言うのも、生協の組合員は顧客でありながら、商品開発や運営(=経営)方法に参加しているからだ。
その意味で、マーケティングそのものと関係のない(ように思える)形態だとも言える。
とはいっても、生協そのものも時代の変化に伴い販売形態も大きく変化してきている。
その一例が、店舗展開だろう。
「生協」と言うと、記事にあるような「班配達」と言う数人の利用者グループを作り、共同購入をすると言うのが一般的だったし、今でも「生協=班配達」というイメージが強い。
しかし、現在では店舗展開などもしており、我が家の近所にも「生協のお店」がある。
利用者は、生協の組合員に限られているのだが、見た目はごく普通のスーパーマーケットだ。
今から15年程前、マーケティングの研修で「コープこうべ」へ視察に行ったことがあるのだが、商品企画などの生協らしさと全国展開をしているスーパーと何ら変わない店舗という2つの顔をもっていた。
店舗には食料品だけではなく、衣料品やスポーツクラブなどがあり、大手銀行系とのジョイントクレジットカードなども発行していた。
「コープこうべ」は、日本の生協発祥の地とも言われるだけに、組合員数や売上規模など、大手スーパーを遥かに凌ぐモノがあった。
それだけではなく、日本の生協スタイルを作りあげたと言っても良いほど影響力がある。特に生協組合員の声で、商品企画・開発がされるという方法は、大型スーパーの「自社ブランド開発」の基となっていると考えている。
もう一つ注目したいのは、生協の利用者の変化だろう。
と言うのも、生協利用者の多くが幼稚園入園前のお子さんのいる家庭だからだ。
子供の成長とともに主婦の時間が増え始めると、生協の利用は減っていくと言われている。
そして再び利用が増えるのが、高齢者世帯となった時なのだ。
(地域全体の)高齢化に伴い、食料品や日用品の買い物に支障がおきるようになると、自宅まで配達してくれる生協は、便利な存在となるのである。
すなわち、多くの人たちが思っているような「割高でも安心・安全な食品の提供」と言うのは、利用者にとって第一の理由ではないのかも知れないのである。
事実、今年問題となったミートホープ社の「偽装ミンチ」は、生協の「牛肉コロッケ」に使われていた(生協が悪いわけではないが、この事件によって「生協ブランド」のイメージが大きく損なわれたのは、確かだろう)。
組合員以外からみる「生協」は、どこか堅苦しく「よく分からない」気がするのだが、一つの小売形態・業態としてみた時、生活者との関係が深いだけより「生活の変化」が分かるのではないか?と感じている。