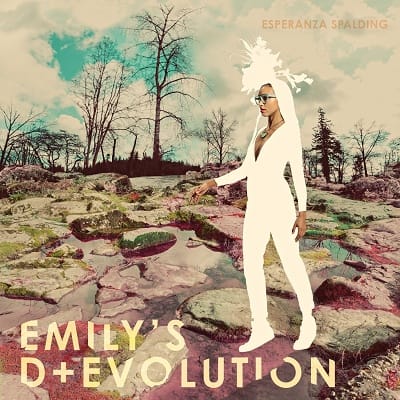佐倉市の国立歴史民俗博物館まで足を延ばし、「万年筆の生活誌 ― 筆記の近代 ―」展を観てきた。

「Fountain Pen」がなぜ「泉筆」でなく「万年筆」と意訳されたのか。そこには、おそらく、毛筆からの転換という意気込みがあった。やがて公的文書へのインクの使用が認められ、また、一般市民が記録するという近代ならではのことばのあり方も相まって、万年筆は日本において爆発的に広まっていく。
毛筆やつけペンよりも遥かに便利でモバイル的。しかし、単なる実用品としてだけではない。夏目漱石は依頼されて「余と万年筆」という面白いエッセイを書いているのだが、そこで「オノト」を使っていると書いたばかりに、後に続く文士たちにとって憧れのブランドとなった(だからこそ、いまだに丸善がオノトの形をした復刻版を出している)。
会場には、さまざまな文筆家たちが使った万年筆が展示されている。もはや漱石のことなど意識しなかったであろうが、文化的にはつながっているわけである。沖縄の施政権返還に関わった大濱信泉は、パーカーのシズレ。柳田國男は、プラチナのシンプルなもの。宮本常一は、パイロットのシンプルなもの。字がとても小さい。ブレヒトの翻訳で有名な岩淵達治は、モンブランのマイスターシュテュック。ただ胴軸が割れており、ガムテープをぐるぐる巻きにしている。こうして見ると、日本人には細字が合っていたのかなという気がしてくる。
近代は戦争の世紀でもあった。戦地から「内地」に出す葉書も万年筆で書かれることが多く、そうなるとやはり細字が好まれただろう。会場には、沖縄戦の犠牲者が持っていたものも展示されている。今なお、沖縄では遺骨とともに万年筆が掘り出されている(沖縄の渡口万年筆店)。
日本の三大万年筆メーカーといえば、セーラー、パイロット、プラチナである。実は、ほかにたくさんの中小の万年筆メーカーがあった。何だ、日本の二眼レフカメラと同じではないか(頭文字がAからZまで揃うと言われた)。大きなところも中小も、いま見ても実にハイセンスなものが少なくない。ほとんど眼福である。いいものを見せてもらった。
ところで、図録が非常に充実していて、我慢できずに買ってしまった。帰りの電車でぱらぱらとめくっていると、また夢中になってしまう。サブカルチャーにおける万年筆を論じたコラムまである。
●参照
万年筆のペンクリニック
万年筆のペンクリニック(2)
万年筆のペンクリニック(3)
万年筆のペンクリニック(4)
万年筆のペンクリニック(5)
万年筆のペンクリニック(6)
万年筆のペンクリニック(7)
本八幡のぷんぷく堂と昭和の万年筆
沖縄の渡口万年筆店
鉄ペン
行定勲『クローズド・ノート』
モンゴルのペンケース
万年筆のインクを使うローラーボール
ほぼ日手帳とカキモリのトモエリバー
リーガルパッド
さようならスティピュラ、ようこそ笑暮屋