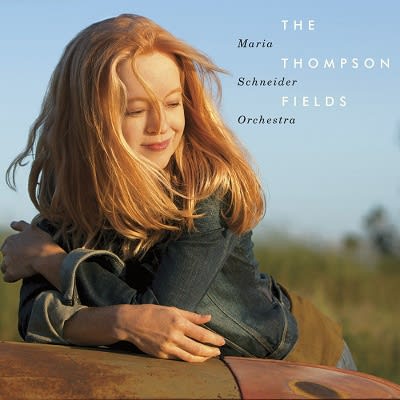齋藤徹さんによる渡欧前の最後の演奏を観ておこうと思い、横濱エアジンに足を運んだ(2016/3/25)。

Tetsu Saito 齋藤徹 (b)
バッハの無伴奏チェロ組曲。チェロのために書かれた曲を、ひとまわり大きなコントラバスで、しかもスティール弦ではなくガット弦を張りなおして演奏する。テツさんは、無謀だということはわかってはいるが、楽器にあわせて演奏するのだというようなことを言った。ときどきは自虐的なコメントをさしはさみながら。
テツさんのFacebookに、次のようにある。
「演奏においても、楽器製作・修理においても、弓においても、ヴィオラはヴァイオリンを目指し、チェロはヴィオラをさらにはヴァイオリンを目指し、コントラバスはチェロを、ヴィオラを、ヴァイオリンを目指すのが一つの大きな流れです。(流れには理由があるのです。)
なのに: 私のガット弦へのこだわりはどこから来ている?コントラバスというものは「倍音」と「雑音」が最大の特徴だ、という私のコントラバス観は、かなり変わっていると言わざるを得ません。」
「それは楽器の「発達」と逆行し、謂わば、民族楽器に戻る方向です。現代日本の民族楽器たるには何が求められるのか?そうすれば邦楽器と対抗できるのか?そんな指向・嗜好をもってバッハを弾くことにどんな意味がある?」
「現在、コントラバス演奏の主流のスティール弦だと、発音してからビブラートを強くかけて、まるでえぐり出すように音を出す傾向があります。特にクラシックの「名人」と言われる演奏で顕著です。
それは聴く人の感情を持ち去るような効果をもちます。しかしそれは感情をある方向に限定していく傾向があります。「どうです?気持ちいいでしょう?」と強制される気がしてしまいます。」
https://www.facebook.com/tetsusaitoh/posts/1173943152645927
https://www.facebook.com/tetsusaitoh/posts/1178166695556906
はじめのひと弾きを聴いて、あっずれていると思った。その場にいた聴客の多くが、思い描いていた音との差異に息を呑んだに違いない。しかしそれは、あるべき音程からずれているのではなかった。
美しい山を描く周波数のプロファイルが心に共振を与えることがあるとして、ここでの音はまったくそれとは異なる。
弓で弾いたときの周波数は、山の部分はさまざまな形をしていて、植生している樹々も雑木林のように多様である。森林とはそもそもそのように多様性を言い換えたことばではなかったか。それは生木のようにピキピキという音を立てたりもして、確かに発せられた途端に減衰していき、残るものは静かに鼓膜を震わせる残響ではなく、山の高まりが消えたあとの草叢やすすき野がお互いに触れて発する音。
ピチカートの音が鼓膜を触るときにも、草叢を歩いてズボンに沢山くっつく「ひっつき虫」のやわらかい棘棘のような印象があった。ピチカートを中心とした第6部では、不思議にも、沖縄の島のような印象を覚えた。
ここでは、精製され純化された音そのものではなく、発せられ消えていく音のありようを体感しているのだった。バッハの作品ではなく、バッハか他の誰かが音楽を立ち上がらせていくときの息遣いのようなものかと思った。
「ざわっざわっと箒の音がきこえます。
とおくの百舌の声なのか、北上川の瀬の音か、どこかで豆を箕にかけるのか、ふたりでいろいろ考えながら、だまって聞いてみましたが、やっぱりどれでもないようでした。
たしかにどこかで、ざわっざわっと箒の音がきこえたのです。
も一どこっそり、ざしきをのぞいてみましたが、どのざしきにもたれもいず、ただお日さまの光ばかりそこらいちめん、あかるく降っておりました。」
(宮沢賢治「ざしき童子のはなし」)

Nikon P7800
●参照
うたをさがして@ギャラリー悠玄(2015年)
齋藤徹+類家心平@sound cafe dzumi(2015年)
齋藤徹+喜多直毅+黒田京子@横濱エアジン(2015年)
映像『ユーラシアンエコーズII』(2013年)
ユーラシアンエコーズ第2章(2013年)
バール・フィリップス+Bass Ensemble GEN311『Live at Space Who』(2012年)
ミッシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹@ポレポレ坐(2011年)
齋藤徹による「bass ensemble "弦" gamma/ut」(2011年)
『うたをさがして live at Pole Pole za』(2011年)
齋藤徹+今井和雄『ORBIT ZERO』(2009年)
齋藤徹、2009年5月、東中野(2009年)
ミッシェル・ドネダと齋藤徹、ペンタックス43mm(2007年)
往来トリオの2作品、『往来』と『雲は行く』(1999、2000年)
齋藤徹+ミシェル・ドネダ『交感』(1999年)
久高島で記録された嘉手苅林昌『沖縄の魂の行方』、池澤夏樹『眠る女』、齋藤徹『パナリ』(1996年)
ミシェル・ドネダ+アラン・ジュール+齋藤徹『M'UOAZ』(1995年)
ユーラシアン・エコーズ、金石出(1993、1994年)