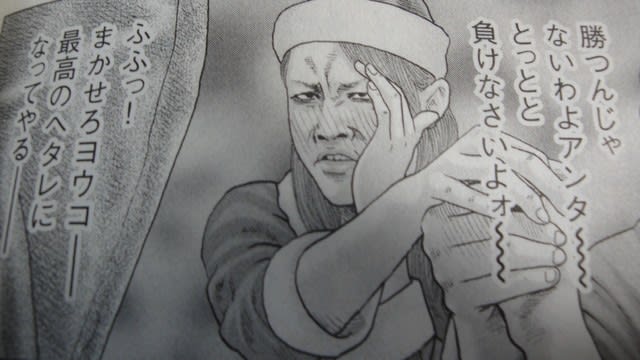「プロテスタンティズム 宗教改革から現代政治まで」深井智朗
マルティン・ルター
世界史の授業で習った「宗教改革」が、やっと分かった(ような気がする)。
硬いテーマだけど、とても勉強になった。
しかも、おもしろかった。(素人にも分かるように例え話を出して説明してくれる)
学生時代から引っ張ってきた様々な疑問が氷解した。
読んで損はない、というか、お薦めしたい作品だ。(書評サイトでも好評だ)
PⅧ
プロテスタントは、ルターの改革以後に発生したさまざまな教会とその信者たちを指す。そしてプロテスタンティズムとは、いわゆる宗教改革と呼ばれた一連の出来事、あるいは1517年のルターの行動によってはじまったとされる潮流が生み出した、その後のあらゆる歴史的影響力の総称だ。
P9
さらに教会はこう説明したのである。天国に行くためには教会の教えに従う必要がある。天国への道を知っているのは教会だけで、その道を通過せずには天国に行けないのだと。これがキリスト教的ヨーロッパの完成であった。教会は天国とそこにいたる通路を支配した。教会は「あの世」というきわめて宗教的な問題を取り扱っているのだが、実際には「この世」を支配した。
P66
東方で急速な拡大を続けるオスマン帝国が1526年にハンガリー王国に勝利し、国教に迫る勢いを見せていた。そのためカール五世は国内勢力の結集のために、ルターを擁護する諸侯に対して強く出られなかったのであろう。
カルヴィニズムについて
P96
フランスではユグノーと呼ばれるようになり、またスコットランドでは国教となっている。スコットランドでカルヴァンの影響を受けた人々は長老派と呼ばれるようになった。
P98
すべての信徒が聖書を読み、解釈する自由を認めたプロテスタントは解釈をめぐって争い、分裂し、互いに対立するようになった。「プロテスタントの宗派や教団についての本を書けばそれは必ず電話帳よりも厚くなる」という冗談があるほどだ。
P116
おそらく一番力を入れたのは、日曜日の礼拝の充実であった。(中略)
(礼拝は英語で「サービス」という)。
P185
カウンタビリティとは神学用語である。神の前での最後の審判において、人間が天国行きの最終決定を受けるための、自分の人生についてのアカウンタビリティである。神の前で人生を説明してみせるのである。
P186
アメリカの公共宗教研究所の2014年の調査によれば、所属する宗教ではキリスト教が78.2%であった。(中略)神を全く信じない人々は8%で、どの宗教団体にも属さない人が14%いる。ユダヤ教とイスラムはそれぞれ2%程度である。(この数字にもかかわらず、米国がイスラエルを擁護するってどういうこと?!政財界、マスコミの影響力が超弩級?)
日本のキリスト教徒人口は193万人、国民の1.5%、プロテスタント人口はその半分(2016年12/3、文化庁の調査)
P199
隣国の韓国がほぼ同時期にアメリカの宣教師によってプロテスタンティズムを伝えられ、今日では人口の30%以上がキリスト教徒であるのとは対照的である。
(韓国でのキリスト教徒の割合は約30%。この理由は次のように説明されている・・・以下、「教養としての宗教事件史」島田裕巳より――朝鮮王朝(李氏朝鮮)の時代になると、儒教が国教に定められ、仏教は弾圧を受けて衰退した。
儒教は基本的に男性のための宗教、上層部のための宗教であり、女性や下層階級はその枠のなかから排除されてしまう。朝鮮半島でも仏教の信仰が衰えなかったとしたら、それは女性や下層階級を含む民衆を救済する役割を果たし、宗教的な空白を作ることはなかったであろう。ところが、空白が存在したために、代わってキリスト教がそれを埋めることになったのである。P252)
【誤植】
P36
早くから理解され。
↓
早くから理解された。
【おまけ】
宗教関係としては、昨年読んだ「キリスト教と戦争」 石川明人に匹敵する良書と思う。
【ネット上の紹介】
1517年に神聖ローマ帝国での修道士マルティン・ルターによる討論の呼びかけは、キリスト教の権威を大きく揺るがした。その後、聖書の解釈を最重要視する思想潮流はプロテスタンティズムと呼ばれ、ナショナリズム、保守主義、リベラリズムなど多面的な顔を持つにいたった。世界に広まる中で、政治や文化にも強い影響を及ぼしているプロテスタンティズムについて歴史的背景とともに解説し、その内実を明らかにする。
第1章 中世キリスト教世界と改革前夜
第2章 ハンマーの音は聞こえたのか
第3章 神聖ローマ帝国のリフォーム
第4章 宗教改革の終わり?
第5章 改革の改革へ
第6章 保守主義としてのプロテスタンティズム
第7章 リベラリズムとしてのプロテスタンティズム
終章 未完のプロジェクトとして
交野山(こうのさん)の観音岩の記事が掲載された。(朝日新聞3/1.2018)
山頂をさらにその上から見るとこうなってるのか、と。
岩の右側がきれいに刈り込まれているのが分かる。(以前は草ぼうぼうだった)

「紅茶スパイ 英国人プラントハンター中国をゆく」サラ・ローズ
私事で恐縮ですが、普段、緑茶か紅茶を飲んでいる。
コーヒーは体に合わないので。
このタイトルも、もし「コーヒースパイ」なら読まなかったでしょう。
「紅茶スパイ」…なにそれ?興味津々、と。
さて、コーヒーも紅茶もカフェインを含んでいる。
「コーヒーが合わない」と言うと、「紅茶のほうがカフェイン多いんじゃないの?」と言われる。
それに対する回答もある。
P178
1ポンドあたりのカフェインの量は、紅茶のほうがコーヒーより多い。だが1ポンドの紅茶があれば二百杯近い紅茶が淹れられるが、1ポンドのコーヒー豆ではせいぜい四十杯のコーヒーしか淹れられない。カップ一杯分のカフェインについて言えば、紅茶はコーヒーのおよそ半分しか含まれない。一方、緑茶のカフェインは紅茶の三分の一、コーヒーの六分の一だ。つまりコーヒーを約二杯飲むと眠気や疲れが取れる。それは紅茶四杯分、緑茶十二杯分に相当する。それだけの量の紅茶や緑茶を飲める時間や膀胱を持ち合わせている人は、まずいないだろう。
P2
中国は茶の販売で得た銀貨で、イギリス商人からインド産のアヘンを買い、その代金を支払うようになった。いわゆる三角貿易[イギリスの綿製品をインドへ、インドのアヘンを中国へ、中国の茶をイギリスへ輸出していたので「三角貿易」と言われた]の始まりだ。
P26
東インド会社は多くの貿易相手国の実質的な支配者になり、領土を広げ、貨幣を鋳造し、軍隊を指揮した。条約に署名し、戦争を開始・終結し、法律を作り、課税制度を確立した。東インド会社はいまや国家であり、世界経済におけるまったく新しい存在となった。
P30
イギリスは百年前から外交ルートを通じて茶の製法を知ろうとしていたが、中国は決して明かそうとはしなかった。
P55
中国のバラがイギリスに紹介されるまで、イギリスにはシンクのバラはなかったと言われている。だから薔薇戦争(1455-85)でランカスター家は深紅のバラを紋章にできるわけがなく、ただの薄いピンクのバラだったはずなのだ。
P157
洪秀全は客家出身だった。客家は正当な漢民族であるが、戦乱を逃れるために中原から地方に移住したため、漢民族としての社会的地位を十分に享受することはなかった。客家は地方で農民となったが、女性は昔からの纏足の風習に従わなかった。そして中国南部に定住して何百年にもなるが、地元の人たちからは相変わらず「よそ者」として見られていた。(鄧小平が客家出身と言われている)
P194
世界征服を目指すイギリス海軍は、砂糖、紅茶、アヘン貿易で稼いだ金で軍備を強化し続けることができた。アヘンなくしてはインド貿易の繁栄はありえなかっただろうし、インドなくしてはナポレオン戦争後のイギリス植民地政策は失敗していただろう。
P242
良質の脂を使うことが、新しいエンフィールド銃にとって必要不可欠となった。
会社が選んだのはウシとブタの混合脂だった。(なんと無神経な!インド北部にはイスラム教徒の兵士がおり、信仰の篤いヒンドゥー教徒の兵士もいて、聖なる牛の死体には触れない)
P243
1857年1月のある日、カルカッタに近いダムダム兵器廠で働く生まれの卑しい肉体労働者が、バラモンのシパーヒーに向かって「だんなたち(ヨーロッパ人)はウシとブタの脂に漬けた薬包をあんたにかみ切らせるようだが、そうなったらあんたのカーストはどうなるのかね?」と言い放った。
P246
シパーヒーの反乱により、傀儡政権として東インド会社と結託してきたムガル帝国は終焉を迎えた。
P247
反乱が最終的に鎮圧されると、イギリス議会はインドにおける東インド会社の特権をはく奪し、その特許状を無効にした。議会の署名ひとつで、東インド会社は消滅したのだ。
P254
ついに1750年頃には、イギリスの磁器工場磁器焼成の秘密を発見し、新しい産業が誕生した。
(中略)
こうした技術進歩を利用した初期の陶器職人のひとりがジョサイア・ウェッジウッドであり、彼の孫のひとりが、ロバート・フォーチュンと同時代人であるチャールズ・ダーウィンだ。(ウェッジウッドやマイセンをありがたがる前に、伊万里焼を見なおした方が良い、と思うけど…フレディ・マーキュリーは伊万里のファンだったそうだ。本物の分かる男だ)
【ネット上の紹介】
19世紀、中国がひた隠ししてきた茶の製法とタネを入手するため、英国人凄腕プラントハンター/ロバート・フォーチュンが中国奥地に潜入…。アヘン戦争直後の激動の時代を背景に、ミステリアスな紅茶の歴史を描いた、面白さ抜群の歴史ノンフィクション。
一八四五年 中国の〓(びん)江
一八四八年一月十二日 イギリス東インド会社本社
一八四八年五月七日 ロンドン、チェルシー薬草園
一八四八年九月 上海から杭州へ
一八四八年十月 杭州寄りの浙江省
一八四八年十月 長江の緑茶工場
一八四八年十一月 安徽省にあるワンの実家
一八四九年一月 上海
一八四九年三月 カルカッタ植物園
一八四九年六月 インド北西州サハランプル植物園〔ほか〕