かつて日本に「アグネス論争」というものが勃発した。1987年頃から約2年間続いたそうである。当事者である歌手のアグネス・チャンを中心に巻き起こった論争をコンパクトにまとめるのは容易ではないので、ここではアグネス・チャンと小説家の林真理子の議論を整理してみたいと思う。
この議論が勃発する頃というのは1986年に日本において男女雇用機会均等法が施行されたことを忘れてはいけない。男女の不平等な労働のあり方について転換点だったのである。
事の発端は1987年に、第一子を出産していたアグネス・チャンがその乳幼児を連れてテレビ番組の収録スタジオにやってきたことがマスコミに取り上げられたことである。当時の経緯をアグネス・チャンの著書『終わらない「アグネス論争」』(潮選書 2020.1.20)から引用してみる。
「アグネス論争」は、私の「子連れ出勤」が発端となって、一九八七年に起きました。といっても、オフィスへの出勤ではなく、仕事先のテレビ局に赤ちゃんだった長男を連れて行ったことが問題視されたのです。
これは当時、すごく誤解された点なのですが、子連れ出勤は私の個人的な事情から始まったことでした。「子連れ出勤が私のポリシー」というわけではなかったし、「働く女性の代表」のような顔をした覚えもありません。また、「女性たちよ、子連れ出勤しましょう」という運動を行ったわけでもないのです。
「個人的な事情」とは、第一に、長男は初めての子どもで、私にとっては不慣れな育児だったこと。第二に、母乳育児だったため、子どもをそばに置いておきたかったこと。第三に、私の親や姉などはみな香港に住んでいたため、子育てに関して親たちを頼れなかったこと。
そしてもう一つ、当時の私が十二本ものレギュラー、準レギュラー番組を抱えていて、長く育児休業しにくかったことが挙げられます。テレビ局側からは「できるだけ早く番組に復帰してほしい。局に赤ちゃんを連れてきてもいいから」と説得され、不安を感じながら復帰したのです。
ですから、そのことが問題視されるとは思ってもみませんでした。ところが、私の子連れ出勤が新聞や雑誌などで紹介されると、少しずつ、反発・批判の声が現れ始めたのです。
作家の林真理子さんやコラムニストの中野翠さんなどが急先鋒となって、「大人の世界に子どもを入れるな」「周囲の迷惑を考えていない」「プロとして甘えている」などという批判を浴びました。
そうした言葉の一つひとつに、私は傷つきました。マスコミで報じられたことの中には誤解も少なくありません。私は一度だけ、「アグネス・バッシングなんかに負けない」という反論を雑誌に寄せ(『中央公論』八七年十月号)、その中で誤解については説明しました。(p.17-p.18)
それ以降、批判派と擁護派が様々な立場から論陣をはって大論争に発展していったのだが、社会学者の上野千鶴子が『朝日新聞』の「論壇」の寄せた「働く母が失ってきたもの」(一九八八年五月十六日付)でとりあえず決着がついた形になったように令和の今なら見える。
アグネスさんが世に示して見せたのは、「働く母親」の背後には子どもがいること、子どもはほっておいては育たないこと、その子どもをみる人がだれもいなければ、連れ歩いてでも面倒をみるほかない、さし迫った必要に「ふつうの女たち」がせまられていることである。
いったい男たちが「子連れ出勤」せずにすんでいるのは、だれのおかげであろうか。男たちも「働く父親」である。いったん父子家庭になれば、彼らもただちに女たちと同じ状況に追いこまれる。働く父親も働く母親も、あたかも子どもがないかのように職業人の顔でやりすごす。その背後で、子育てがタダではすまないことを、アグネスさんの「子連れ出勤」は目に見えるものにしてくれた。(p.19-p.20)
全くの正論で、グーの音も出ないから日本の社会はこの方向で進んで行くはずだったのだが、保育所数が増えることはなく、まして付属の託児所を持つ企業などほんのごく一部であり、ついに2016年にはSNS上の「保育園落ちた日本死ね!!!」という投稿が話題となり、確実に日本の人口は減少しつつあるのが現状である。

ということで「アグネス論争」はアグネス・チャンの圧勝ということになるのかと思ったらそうでもないということを今から書いてみようと思う。林真理子の「いい加減にしてよアグネス」は『余計なこと、大事なこと』というエッセイに収録されているので、検証してみようと思うのだが、林から見た当時の状況を林自身が『文藝春秋』(2022年6月号)で回顧しているので引用してみる。
いったい何年前だろうとウィキペディアを開いたところ(全く便利な世の中になったものだ)一九八八年とある。今から三十四年前だ。
タレントで歌手のアグネス・チャンさんは、あの頃ものすごい人気であった。憶えているのは、24時間テレビの司会をする彼女をグラビアでとりあげた『フォーカス』が、「善意の固まりみたいな」と表現していたことだ。驚いた。あの『フォーカス』がだ。そのくらいの存在だったということを知っていただきたい。
そのアグネスが長男を生み、テレビ局や講演会に連れていくようになった。それを朝日新聞が誉めたたえる。私はげんなりした気分になったものだ。コラムニストの中野翠さんも同じ思いで、舌鋒鋭くあれこれ書いた。
もし彼女が、
「迷惑なのはわかっている。だけど私はこの子と別れたくない。ずっと一緒にいたい」
と言うのであれば、私はああ、そうですか、と引き下がったであろう。しかし彼女の、
「赤ん坊を連れていくと、仕事場がなごやかな気分になるって皆に喜ばれます」
という文章を読んだ時、かなり強い反ぱつが生まれた。こういう鈍感さにかなうものは何もない、と私は思う。当時私は結婚もしていなかったし子どももいなかったが、赤ん坊を持つ母親の独特の価値観がやりきれなかった。
私の可愛い赤ん坊は、誰にとっても可愛いはず。どこに連れていっても喜ばれるはず。
アグネスさんには、マネージャーだの付き人だのが常時数人つき添っていたという。その中の一人に、うちでベビーシッターを頼めばいいではないかと思うのは私だけではないようで、週刊誌でも意地悪な記事が出始めていた。そして私の『文藝春秋』における「いい加減にしてよアグネス」になるわけだ。
この長文を出した当時は、世間からは「よく言ってくれた」という反応が多かったと記憶している。そこへ上野千鶴子さんの、朝日新聞での反論となるわけだ。
「『働く母親』の背後には子どもがいる」
「女たちはルールを無視して横紙破りをやるほかに、自分の言い分を通すことができなかった」
これに世論の針が大きく傾く。
そして論争の火蓋が切られたわけだ。(p.290-p.291)
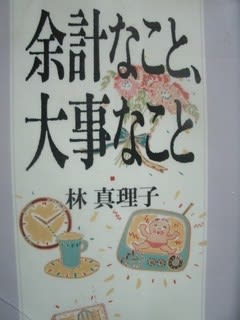
この文章に付け加えておきたい文章を引用しておく。
さて、国会でも話題になった「中央公論の記事」というのは、昨年六月に行われた彼女の講演料に端を発する。この時、『フォーカス』と『週刊朝日』が、彼女の講演料が百七十万円という高額であること、子どもにベビーシッターを含め六人連れでやってくることなどをすっぱぬいたのである。その後の彼女の強い抗議によって「百七十万円は百万円」「六人はいつもは四人」と訂正されたのであるが、それにしてもかなりの優遇である。これほどまでに恵まれている女性が、どうして全国の働く女性の苦悩を一身に背負ったようにふるまうのか、どうしても合点がいかぬと『週刊文春』に私は書いた。(『余計なこと、大事なこと』文藝春秋 p.17)
林は「いい加減にしてよアグネス」の最後を以下の引用で締めくくっている。
最後に締めくくりを、曾野綾子さんのこの文章でさせていただきたい。いまから二年ちょっと前、アグネスはエチオピアの難民キャンプを訪ねた(注:24時間テレビの取材)。その時見たものを、彼女はまた例の調子で書いたわけだ。
「私が出会った人はみんな礼儀正しかった。いい人たちばかりだった。無表情で感謝の心がないと書いた曾野綾子さんは、いったい何を見てきたんですか」
曾野さんの文章から、
「私が外国の紀行文を書く時のルールは、たった一つです。それは、ある日、私がそこにいた時、こうだった、と書くだけです。それがその国の普遍的な状況だという言い方は、私はしないことにしています。私は学者ではないので、普遍化ができないのです。しかし私は、自分の目に映ったことを、あなたから違うと言われると『ああそうですね、違っていました』と言うわけにもいきません。あなたは私の書いたものが、自分の見聞きしたものと違う、と非難しておいでですが、私は違う方が当然だと思います。僅かな時の差、運命に似て出会う人々が違うこと、それを見る人の心や眼や、それらすべてが違うのですから、見えるものが違うのも当然でしょう。(中略)しかし『どこそこの人は皆いい人です』という式の言い分は、あなたがおっしゃる分には少しもかまわないのですが、大人は少し困ります。なぜなら、そういうことはこの世にないからです」(『余計なこと、大事なこと』 p.30-p.31)
以上のことを踏まえた上で、冒頭で引用したアグネス・チャンの言い分を改めて検証してみるならば、少々首をかしげたくなる部分が散見される。例えば、テレビ局側から「できるだけ早く番組に復帰してほしい。局に赤ちゃんを連れてきてもいいから」と説得されたと書いているが、急に12本のレギュラー番組を休まれても困るから内心嫌々ながらでもアグネスの機嫌を取って出演を要請するのがテレビ局の立場であろう。どうもそこがアグネスには分かっていないように見える。
あるいは「私の親や姉などはみな香港に住んでいたため、子育てに関して親たちを頼れなかった」と書いているが、ところで夫の親には頼れなかったのだろうかとも思う。
そもそもアグネス・チャンが「子連れ出勤が私のポリシー」で「働く女性の代表」で「女性たちよ、子連れ出勤しましょう」という社会運動家であったのならばこのような不毛な論争にはならず、まだ景気は良かったからもしかしたら今の日本の人口は増えていたかもしれないのだが、アグネス・チャンは香港出身のイギリス人だから日本に対してそのような義理はないのである。
ここからは私見なのだが、アグネス・チャンは1987年3月31日をもって大手芸能プロダクションの渡辺プロダクションから独立して個人事務所「トマス・アンド・アグネス」を設立している。ちょうど「アグネス論争」が勃発した頃なのである。つまりアグネス・チャンは仕事を失うことを恐れて休めなかったという可能性は高いと思う。どのような経緯で事務所を辞めたのかは分からない。円満退社だったのかタレントとマネージャーがつるんで退社したのか。しかし個人事務所の社員が新規に募集した人たちだらけだったとしたら自分の子どもを任せられなかったと思うのである。
しかしアグネス・チャンは林が既に指摘しているように、そのようなネガティブな発言は決してしないし、それは個人事務所「トマス・アンド・アグネス」がかつて怪しい健康食品を売っていて、批判されるとアグネス本人が自信を持って体に良いものだと喧伝していながら、薬事法に抵触することを知ると販売中止にしてしまった経緯を見てもアグネスは職業病かもしれないが自分の「負」の部分を決して明かそうとしない。「アグネス論争」とは「事実」を明らかにしない人(つまりアイドル)をどこまで信用できるのかという問題だったのだと思う。いまではガチのアイドルおたく界隈に事情をよく知らない人たちが介入してしか起こらないような議論を当時は日本人がこぞってやっていたのである。


























