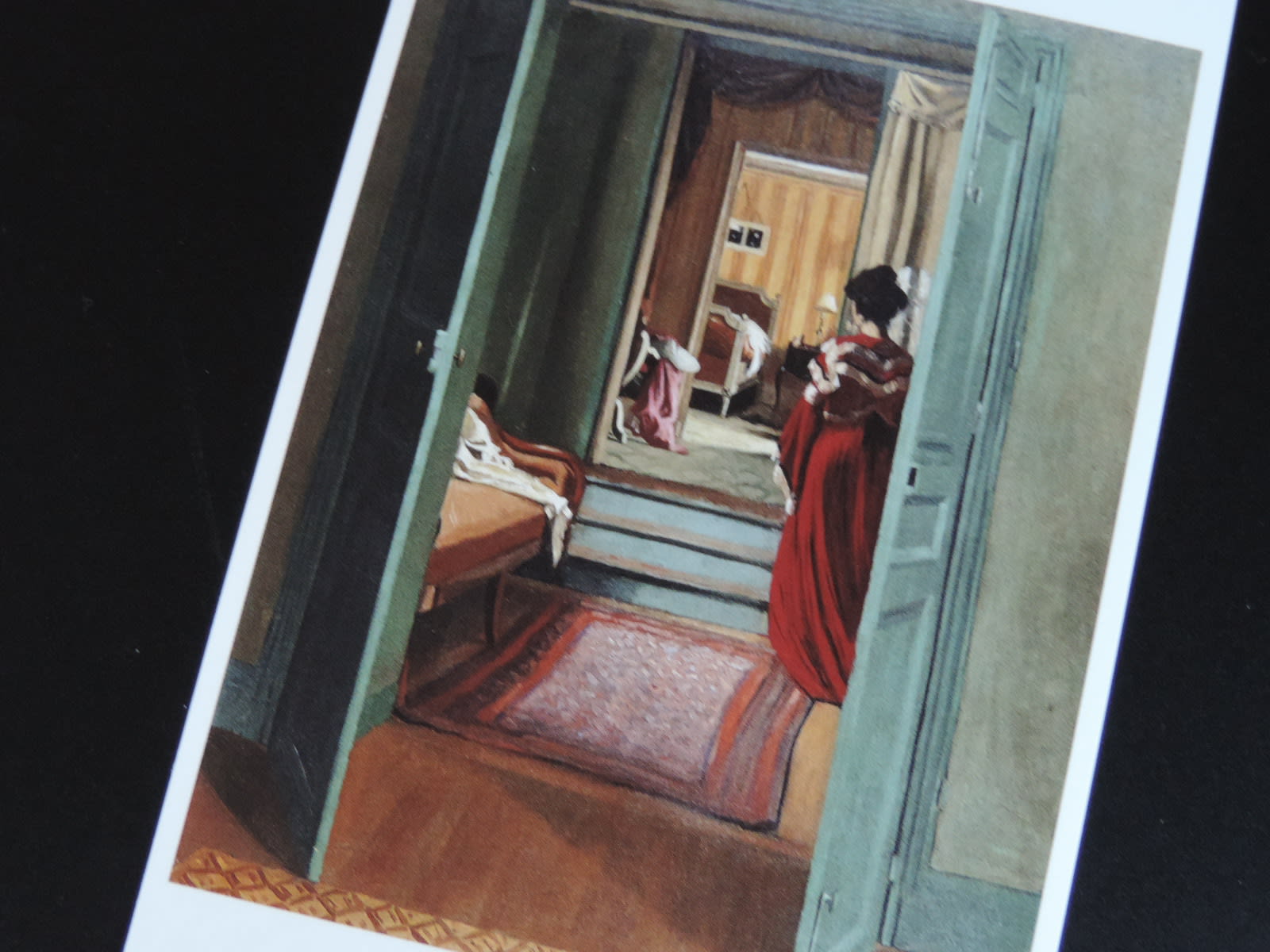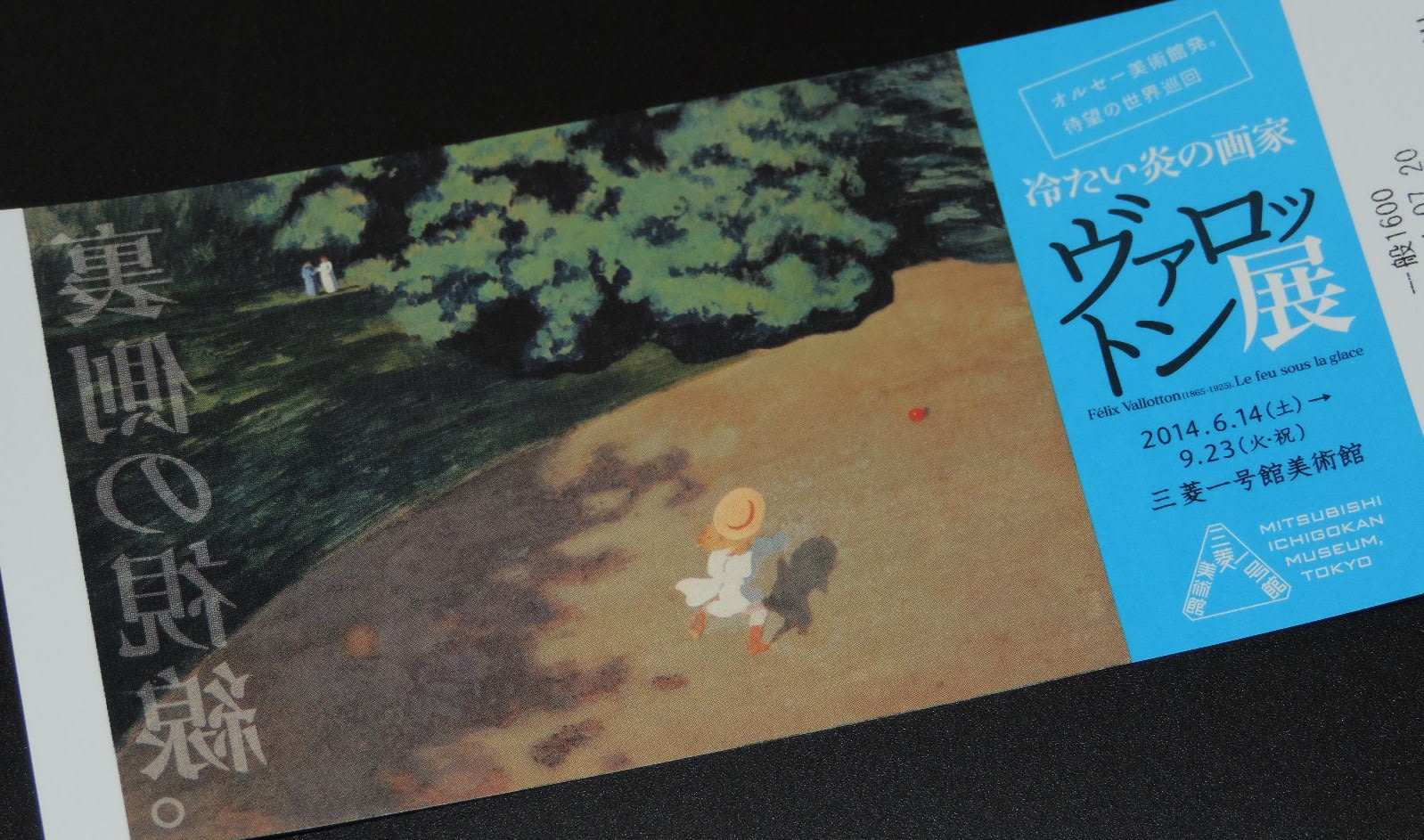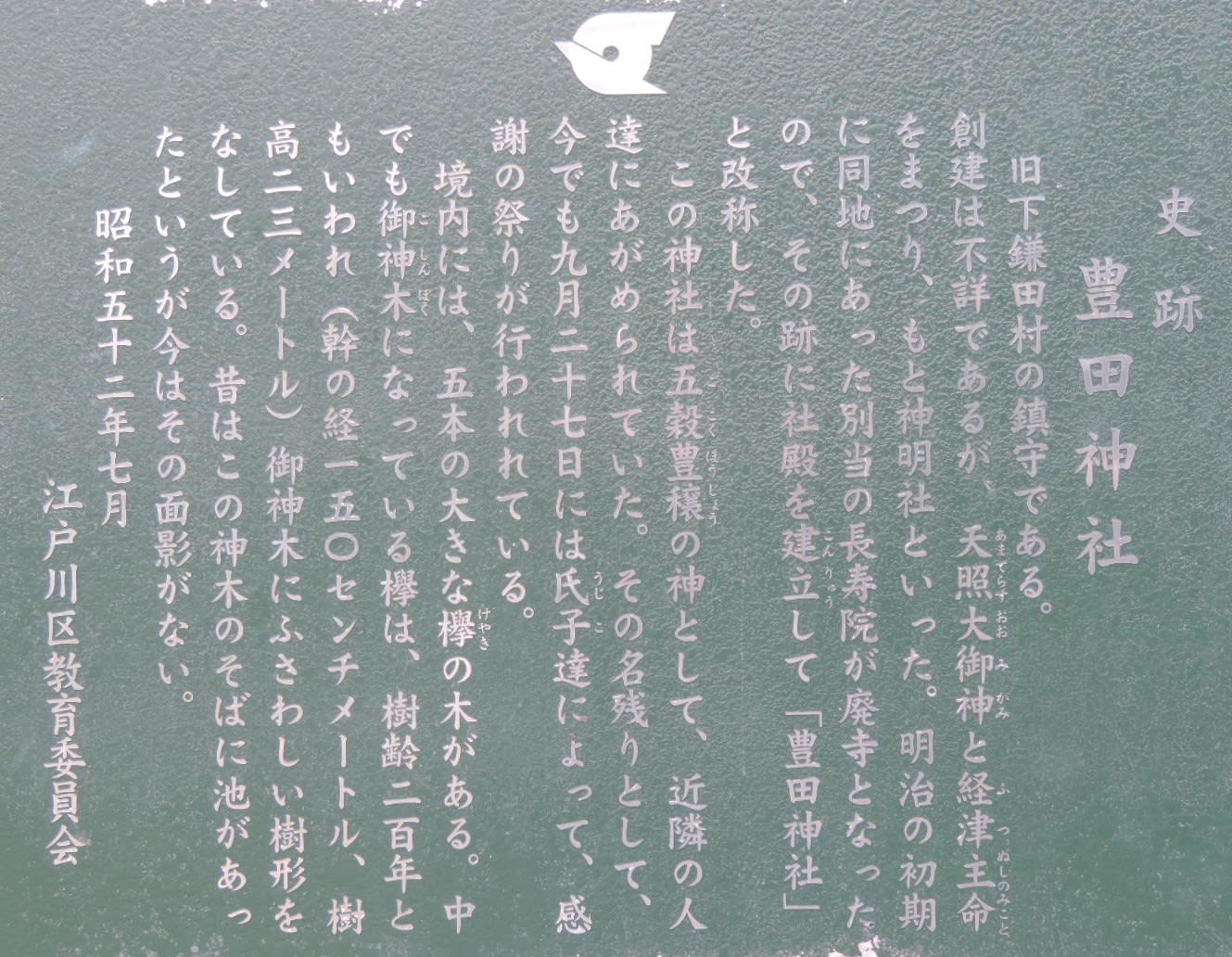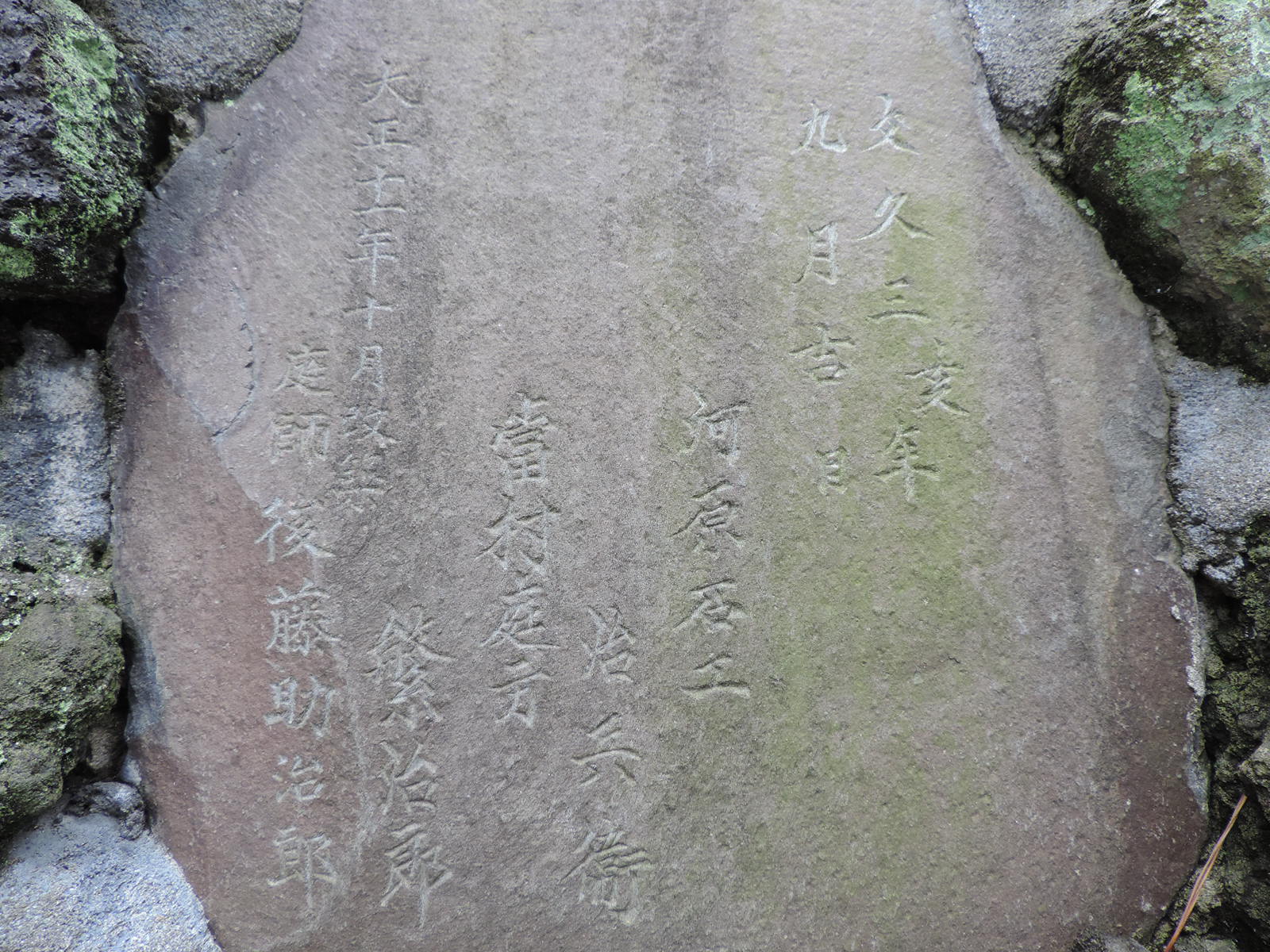■ 一泊東京で読んだ。行きのあずさで、都内の電車で、友人を待つカフェで、帰りのあずさで。
『人はなぜ集団になると怠けるのか 「社会的手抜き」の心理学』 釘原直樹/中公新書
「人はなぜ集団になると怠けるのか」という中公新書らしからぬタイトル。何だか1時間もあれば読了できる中身の薄い新書サイズの本のタイトルのようだ。サブタイトル「「社会的手抜き」の心理学」の方が中公新書に相応しい、と私は思う。
社会的手抜きって何? どういう意味? 著者は**集団で仕事をするときの方が1人でするときよりも1人当たりのパフォーマンス(業績)が低下する現象である。**(2頁)だと説明している。
分かりやすい例が運動会の綱引き、みんな経験していることだから・・・。1人の力を100%とした場合、2人の場合だと1人当たりの力の量は93%に低下し、3人の場合85%、4人だと77%。このように次第に低下して8人だと49%、半分以下しか力を出していないという。フランスのリンゲルマンという人が20世紀の初頭に実験によって明らかにしたそうだ。
社会的手抜きは綱引きのような単純な力仕事だけでなく、頭脳労働や社会生活など、さまざまな場面で出現しているという。
社会的手抜きはどうして起こるのか、さまざまな心理実験などを紹介しながら明らかにしていく、というなかなか興味深い本。
ちなみに綱引きについては個々人の集団に対する貢献度が分からないので個人を評価できないから、という分かりやすい理由が挙げられている。
さて『雁』 森 鴎外/新潮文庫の続きを読むか。