 360
360
朝カフェ読書@スタバ 2024.05.17
■ 津田梅子のことについては幼少の頃にアメリカに留学して、帰国後に津田塾大学を創設した女性、ということくらいしか知らなかった。津田梅子が新5000円札の顔になるということで、どんな人だったのか知りたいと思い(*1)、『津田梅子』大庭みな子(朝日文庫2019年7月30日第1刷発行、2024年2月20日第2刷発行)を読んだ。
著者は1968年に『三匹の蟹』で芥川賞を受賞した大庭みな子さん。大庭さんは津田塾大学出身。本書を書くきっかけは、津田梅子が1882年から1911年まで、30年にも亘る長い間、アデリン・ランマンという女性に宛てた数百通もの手紙が1984年に津田塾大学の物置で見つかったことだったとのこと。アデリン・ランマンは留学中の梅子を11年間(全期間)預っていた女性。ランマン夫妻には子どもがなく、梅子を我が子のように育てたという。
本書は発見された梅子の手紙を何通も取り上げて、それぞれの手紙について大場さんが解説するという形式を採っている。**これらの手紙には、梅子が育ての親とも言えるアデリン以外には決して言わなかった心の底からの叫びに似た痛切な訴えがある。**(21頁)と、大庭さんは書いている。
梅子が帰国して1年後(1883年、18歳の時 *2)に書いた手紙に**私自身が遠い将来、自分の学校を創ったときのためにも、(後略)**(95頁)とある。既存の学校で教えるということではなく、この時既に学校設立のことを考えていたことが分かる。梅子が私塾創設に踏み切ったのは35歳の時だったそうだ。明治という時代を考える時、この年齢に関係なく凄い人だったんだな、と思う。
**将来にわたっても絶対結婚しないとまでは言いませんが、独身だという理由で他人にへんな眼で見られずに、自分の道を進みたいと思います。**同年の別の手紙にはこのように書いている。強い意志の持ち主であることが窺える。
本書には津田塾大学の前身である私塾・女子英学塾の開校式の時の梅子の式辞が載っている。この長文の引用はしない。式辞について大庭さんは**梅子の真の目的は、その時点の世界の情勢から判断して、英語を手段に、日本女性の目を開かせ、女性に働く場を与え、社会での発言力を与え、男性と対等の立場に引き出すことにあった。**(218頁)と説いている。現在放送中の朝ドラ「虎に翼」より昔、明治時代のことだということを考え合わせると、いかに大志であったかが分かる。あのクラーク博士だって、「少女よ、大志を抱け」とは言わなかった。
梅子は多くの人たちから生涯に亘り支援を受けている。梅子には人を引き付ける魅力が備わっていたのだろう。**梅子は周囲のあらゆる星を引き寄せる巨星に似た吸引力を持っていた。**(203頁)と大庭さんは書いている。
津田梅子の気概、見識、すばらしい。なるほど、新5000円札の顔に相応しい女性だ。

*1 樋口一葉の時も同じことをしている。
*2 津田梅子は1864年12月31日生まれ










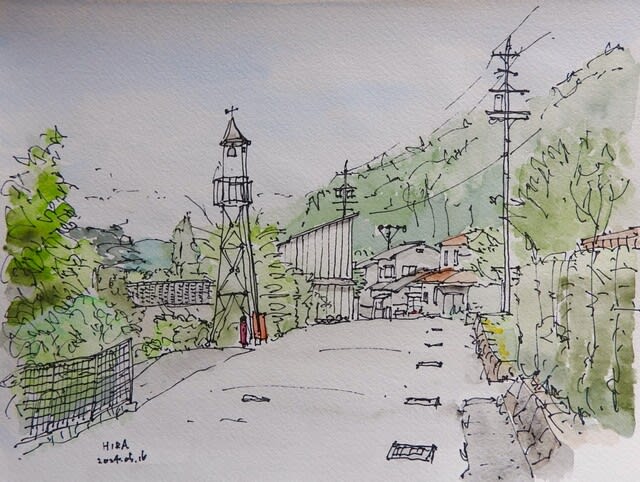





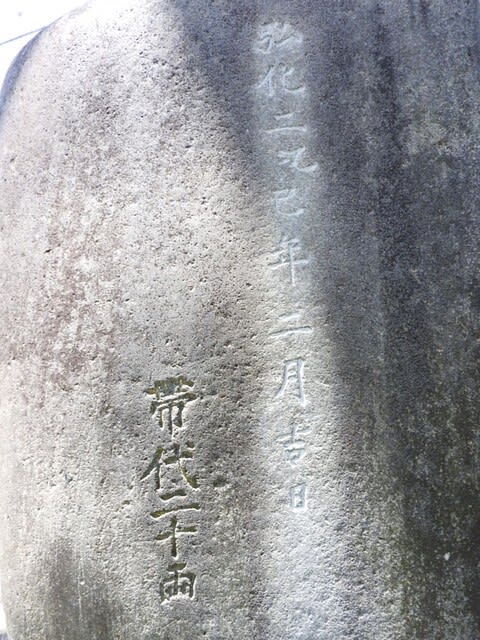

 360
360


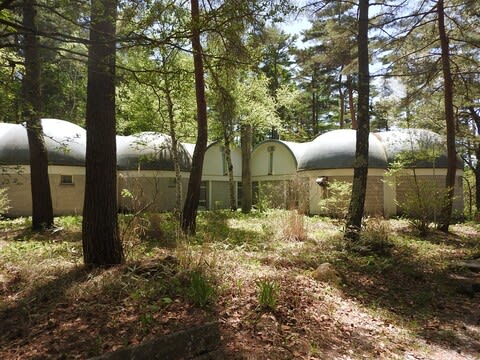


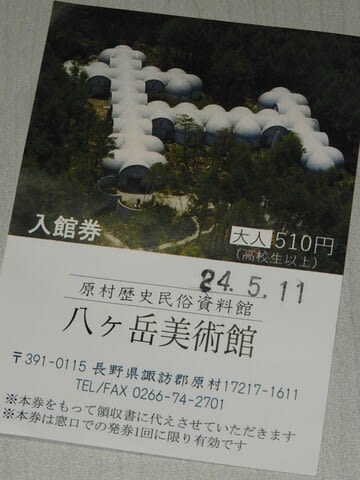
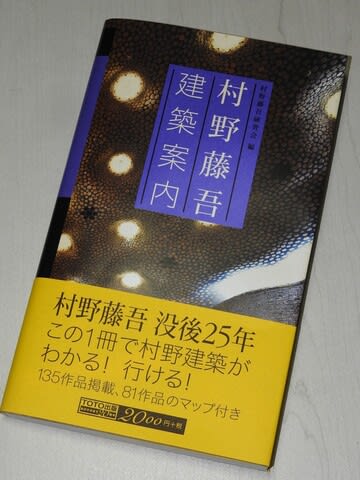






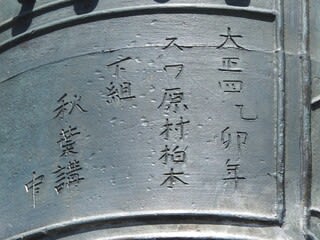

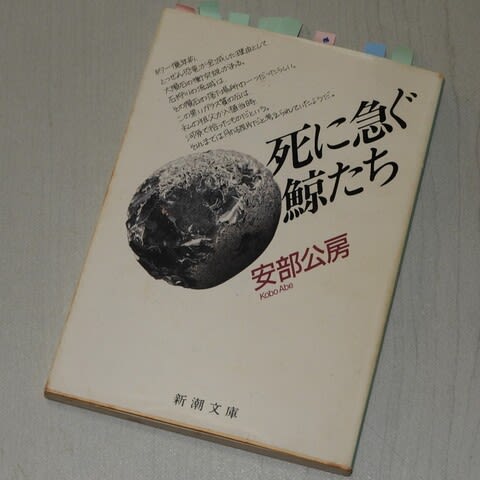









 420
420
